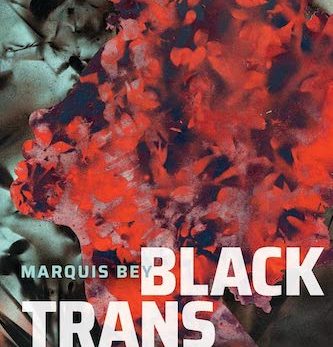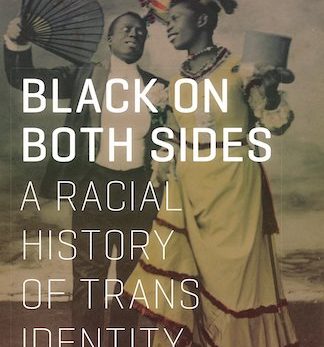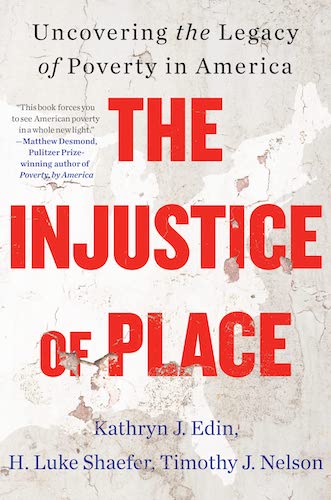
Kathryn J. Edin, H. Luke Shaefer, & Timothy J. Nelson著「The Injustice of Place: Uncovering the Legacy of Poverty in America」
アメリカにおける貧困、とくに世代間で継承されるそれを、個人のレベルではなく地域のレベルで大量のデータと綿密な取材をもとに分析した本。社会学の勝利としか言いようがない鋭い内容。
著者らはさまざまな指標を使って全国を数千に分けた地域を最も有利な地域から最も機会に見放された地域までランク付けし、アメリカで最も貧困が集中し世代間階層移動が起こりにくいアパラチア、ディープサウスのコットンベルト、そしてテキサス州南部の三つの地方で五年に渡る調査を行った。その結果それらの地域に明らかになった共通性は、それらが伝統的に「内なる植民地」として扱われてきており、またその維持のために人種差別が温存されてきたことだ。
ここでいう「内なる植民地」とは、先住民の土地や資源を奪いかれらを追放する入植植民地主義とは異なる概念であり、古くは東インド会社や奴隷制に基づいた綿花や煙草のプランテーション、そして現代のモノカルチャー的な輸出向けの大規模農場などに共通の、国ではなく資本が主体となり労働集約的な産業に依存した経済・社会体制のことを意味する。ディープサウスでは奴隷制が、テキサス南部では立場の弱いメキシコ人移民や移住労働者を使った農場が、そしてアパラチアでは炭鉱産業がその元祖であり、奴隷制が廃止されたあとにも小作農や労務囚として黒人を搾取する制度が維持されたり、炭鉱が閉鎖されたあとの土地に化学工場などが設置されたりして、経済構造は変わっていない。
近年、アパラチア地方における貧しい白人たちのあいだのオピオイド依存やオーバードーズ、自殺など「絶望による死」の増加が問題とされているが、オピオイド依存が広まった背景には、悪質な医師と組んだパーデュー・ファーマなどの製薬会社による違法なマーケティングだけでなく、炭鉱産業の危険な労働現場が大勢の負傷者や障害者を生み出してきた長い歴史がある。パーデュー・ファーマの新薬オキシコンティンが発売される以前から、多くの炭鉱労働者たちは職場で怪我をして鎮痛剤に頼る生活を送ってきた。
さらに問題を深刻化させたのは、炭鉱にかわって登場した化学工場など、アパラチア地方の緩い環境規制に引かれて移転してきた産業だった。アパラチア地方の多くの街ではたった1つの会社がそれぞれの街の経済の基盤となり、従業員の不満がたまらないようにするための「充足の社会学」という経営理論に基づき、その企業が映画館やショッピングモール、公園などさまざまな施設を直接運営する一方、労働運動を徹底的に弾圧し、従業員やその子どもたちの選択肢を増やす可能性がある教育への投資を抑止した。しかし第二次世界大戦後の経済構造の変化などによりそれらの企業が海外のさらに安い労働力を求めて撤退するとそれらの企業が運営していた映画館などの施設も閉鎖され、そこには環境汚染と労災による負傷によって健康を壊された失業者たちと、教育を受ける機会だけでなく遊ぶ場所さえ奪われた子どもたちが残された。麻薬依存が広まるのは「この街にはほかになにもやることがないからだ」というのは、著者たちがいくつもの街で聞いた意見だった。
ディープサウスの農場やテキサス南部で搾取されてきた黒人やメキシコ人たちの貧困はそうした構図に加えて、さらに人種差別による分断が要因として挙げられる。1956年の最高裁判決により公教育による人種隔離が禁止されると、ディープサウスでは多くの公立学校が閉鎖され、あるいは閉鎖されないまでの教科書や机などの設備が丸ごと撤去され、白人の子どもたちが通うための私立学校が多数設立された。ここで意外なのは、教育を受ける機会を奪われたのは黒人の子どもたちだけではない、ということだ。白人の子どもたちが通わされた通称「隔離学校」の多くは教会の部屋を借りて運営されており、教師として採用されたのも多くは教員としての資格のない人たち。黒人と一緒の学校に通わせるくらいなら自分たちの子どもが満足な教育を受けられなくても構わない、というのが当時の白人たちの考えだった。そんな馬鹿な、と思うかもしれないが、ルーズヴェルト大統領とトゥルーマン大統領が目指した国民皆保険制度が実現しなかったのは「黒人と同じ病院や医者にかかりたくない」という白人たちの反発が原因だし、現在でも白人アイデンティティポリティクスの充足を優先して福祉削減や金持ち減税を行う政治家に投票する貧しい白人は少なくない。こうした人種分断のもと、「内なる植民地」から脱却しすべての子どもたちに機会を与えるための施策は実現しない。
本書の主題は「内なる植民地」として経済的繁栄に見放された貧しい地域の分析だが、著者らは逆に最も機会に恵まれた地域も訪れ、なにがどううまくいっているのか調査もしている。著者らが作った指標によって最も恵まれた地域とされたのは、たとえば経済活動の中心地であるニューヨークでも、テクノロジー産業が活発なベイエリアやシアトルでも、あるいは大学や研究機関が多いボストンでもなく、意外にも中西部の農業地帯にある小さな街の数々だった。それらの街は一見南部の農業地帯と似たような風景にも見えるのだけれど、貧富の差が小さく、人種隔離がそれほど深刻ではなく、個人農場や中小企業が多く、また地域のなかで貧しい家庭に生まれた子どもが教育を通して階層上層することが可能だった。もちろん、それらの地域だって、先住民から奪った土地を白人に分配することで地域の経済が立ち上がったという歴史はあり、それらの街を理想化することはできないが、それらの街には「内なる植民地」としての歴史がなかった。
「自分たちは東部や東西海岸に見下されている、まるで植民地のように扱われている」というのはアパラチアやディープサウスの白人たちの多くが抱いている気持ちだが、現状それは文化的な態度ではなく経済体制としての「内なる植民地」を打破する方向には機能しておらず、むしろそれを温存するような形にはたらいている。もちろんアパラチアにもディープサウスにも、過去には白人や黒人やその他の労働者たちが人種対立を超えて協力した労働争議の歴史はいくつかあるものの、それらの歴史は忘れ去られ、歴史的教訓として残されてはいない。これらの地域が制度的な貧困を脱却し、すべての子どもたちに機会を行き渡らせるためには、人種差別の克服と産業構造の多様化を通した「内なる脱植民地化」が必要。政府も政治家が人気取りのために行う、既存の炭鉱やその他の独占産業を維持するための助成金などを続けるのではなく、より多様な産業と社会基盤をもたらすための施策を目指すべきだ。