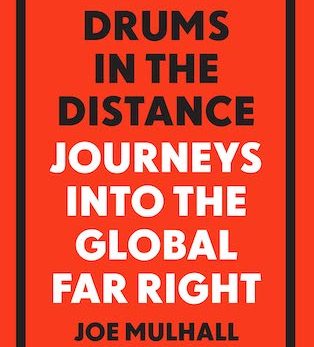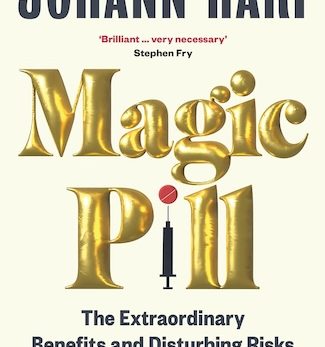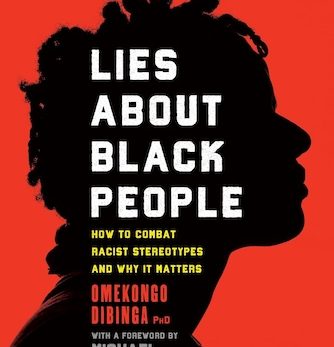Paola Ramos著「Defectors: The Rise of the Latino Far Right and What It Means for America」
アメリカの極右運動のなかで存在感を増しているラティーノたちに取材しつつ、中南米からの移民に対する排斥や差別的な発言を繰り返すトランプがどうしてラティーノからの支持を少しずつ増やしているのか問う本。著者自身もキューバ系アメリカ人でクィアなジャーナリスト。
本書に登場するラティーノ極右活動家たちは、2021年の連邦議事堂占拠事件で共謀騒乱罪に問われたプラウド・ボーイズのリーダーをはじめ、テキサスで国境をパトロールする民間のミリシアに参加している人や、スペイン人コンキスタドール(征服者)を記念する像をブラック・ライヴズ・マター運動から守ろうとしている人、トランスジェンダーの人たちをバッシングして学校教育を攻撃しているMoms for LibertyやGays Against Groomersなどの団体で活動している人、移民排斥を訴える政治家やキリスト教ナショナリズムを布教する牧師など、白人至上主義や反移民主義、マイノリティの社会的迫害に加担しているラティーノたち。近しい家族に移民を持つかれらはある意味白人たち以上に「本物のアメリカ人」であることにこだわり、リプレースメント理論が警鐘する移民流入による国家乗っ取りを危惧している。
白人至上主義や反移民主義による攻撃に晒されているラティーノたちがその担い手になってしまう理由を著者は、植民地主義と奴隷制によって中南米にもたらされた3つの要因、すなわち複雑な人種システム、キリスト教の強い影響を受けた伝統主義、そしてそもそも多くの人たちが移民する理由となった政治的トラウマだと分析する。まず人種システムについて言えば、Tanya Katerí Hernández著「Racial Innocence: Unmasking Latino Anti-Black Bias and the Struggle for Equality」でも説明されているように、人種を「白人と黒人(あるいは非白人)」に二分する北米の単純な構図と異なり、中南米では白人入植者と先住民、そして奴隷として連れてこられた黒人の混血が進んだ結果、同じ家族のなかでも肌の色や外見上の特徴が異なり白人に近い方が良い扱いを受けたり、また個人の人種的アイデンティティも必ずしも家族のそれや外見的特徴とは一致しないようになっている。アメリカに住むラティーノがスペイン人コンキスタドールの末裔を自認しそれを自らの誇りにしつつ、白人至上主義を批判されると自分はラティーノなのだから人種差別主義者ではないと言い訳できてしまう。
ラティーノの伝統主義は、伝統主義一般と同じく実際の伝統ではなく後付けで「伝統」と名指しされたものを守ろうとする考え方であり、とくに近年、カトリック信仰にかわりアメリカ発の福音主義キリスト教教会の影響が中南米でもアメリカのラティーノ・コミュニティでも広まりつつある。これらの教会はアメリカの白人福音主義キリスト教教会に同調して政治に関与することが多く、ラティーノたちを民主党から共和党に鞍替えさせ、過激な反LGBT運動に動員する役割を果たしている。また多くの中南米系移民たちは本国で内戦や革命、ギャングの抗争による無政府状態などを経験してきた人たちやその子どもたちであり、権威主義的な手段によって混乱を収めた独裁者たちを評価する人たちも少なくない。アメリカも放っておくとそうした大混乱に陥ってしまうという懸念は、アメリカ生まれの移民二世たちにとっては本国で政治的なトラウマを経験した親たちの妄想に思えたけれど、2020年に起きたコロナウイルス・パンデミックと人種差別をめぐる大規模な抗議活動を目の当たりにしたかれらは、混乱を収めてくれる権威主義的な指導者を求めてしまった。
もちろん極右運動に参加するラティーノたちは全体から見ればごくわずかで、支持政党を見てもいまのところは民主党を支持しているラティーノのほうが共和党支持者より圧倒的に多い。しかしあれだけラティーノを敵視し排除しようとしてきたトランプがじわじわとラティーノからの支持を増やしていることに、民主党だけでなくアメリカの民主主義を守ろうとしている人たちはもっと危機感を抱く必要がある。最終章では極右運動に身を投じて活動しているうちにその運動が自分自身を排斥しようとしていることを突きつけられ、そこから脱却しようとしている二人のラティーノたちのストーリーが紹介されるが、希望を感じるはずが逆にその難しさを感じてしまった。