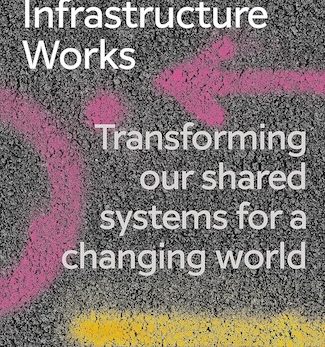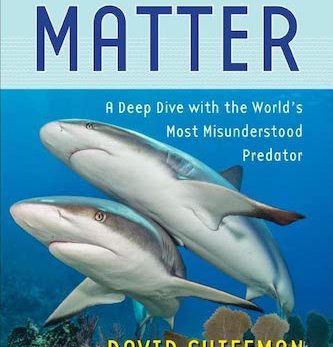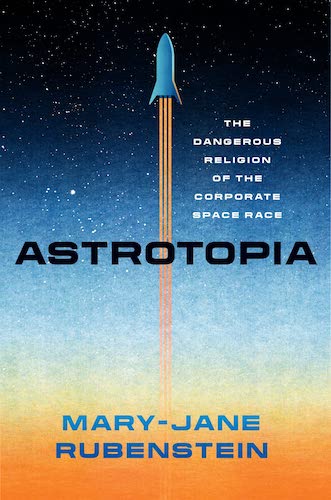
Mary-jane Rubenstein著「Astrotopia: The Dangerous Religion of the Corporate Space Race」
宗教と科学の関係を専門としている著者が、イーロン・マスクやジェフ・ベゾスらが主導する現代の宇宙産業やトランプによる宇宙軍の創設に見られるような国家による宇宙政策が過去のアメリカ大陸への侵略と植民地化を比喩として参照し、またそれを可能とした宗教的・神話的論理を中身はそのまま無神論的に変換して正当化の論理としていることを指摘する本。
「最後のフロンティア」というスローガンに現れているように現代の宇宙開発の比喩として参照されるヨーロッパ列強によるアメリカ大陸への侵略と植民地化はそれ自体、聖書に書かれたイスラエルの民によるカナン(現代のイスラエル・パレスティナを中心しとした一帯)への侵略と征服を比喩として正当化された。聖書ではカナンは神がアブラハムの子孫に与えた「約束の地」であり、それに従ってイスラエルの民はカナンを征服し、そこに暮らしていたさまざまな民族を虐殺したとされている(ただし歴史学の研究によると実際にはそのような史実はなかったと考えられている)。アメリカ大陸はヨーロッパによる侵略当初から新たな「約束の地」として語られ、そうした考え方はアメリカは神に選ばれた特別な国である、とするキリスト教ナショナリズムとして現代にも受け継がれている。
現代の宇宙開発においても、かつて植民地主義が「文明とキリスト教をもたらす崇高な行動」として正当化されたのと同じように、アメリカの政治家や事業家たちは一国の国益のためだけではなく人類のための崇高なミッションとして宇宙開発の必要性を訴えている。政治家たちが中国やロシアに宇宙での主導権を与えてはいけない、世界のためにアメリカが主導権を握るべきだ、とまるでアメリカの覇権は世界のためであるかのように語る一方、マスクやベゾスらは長期主義倫理論を援用して人類に対する実存的なリスクに備えるため人類の宇宙進出は必須だと訴える。
また、聖書が地上の全ては神が人間のために作ったものと教えていることも、土地や資源の際限ない接収と利用を後押しした。アブラハム系ではない世界中の多くの信仰では自然のなかに神性や祖先などの血縁者の存在を見出すため、自然をただ利用する対象としてではなく敬意をもって関係を営む相手として扱う意識が生まれるのに対し、アブラハム系の信仰では自然は人間が自由に利用するために神に与えられた資源として扱われる。火星の気温を上昇させるために大量の核兵器を打ち込んで氷を溶かし二酸化炭素を発生させるべきだ、と主張するマスクをはじめ、月を宇宙のガソリンスタンドにする、アステロイドを採掘して希少な金属やエネルギー源を採取する、といった主張に見られるように、こうした論理は宇宙にまで拡張されている。また軌道に多数の停止した人工衛星や宇宙飛行士が出したゴミなどが放置され、それらを回収もしくは処理する方法すら確立されていないのも、地球で起こした環境汚染をそのまま再現している。
アポロ計画でニール・アームストロングとバズ・オルドリンが月面に着陸した翌年、黒人ミュージシャンのギル・スコット・ヘロンは「ホワイティ・オン・ザ・ムーン」というスポークンワード詩を発表した。「わたしは病院の請求書を払えない、でも白人は月に立っている/十年後もまだ払い続けているけど白人は月に立っている/先月家賃が上がった、なぜなら白人が月に立っている/お湯もトイレも電気も止まったけど白人は月に立っている」と政府によって見放された黒人コミュニティの深刻な貧困と宇宙開発に注ぎ込まれた莫大な政府予算を対置させたこの詩は、コロナウイルス・パンデミックにより多くの人たちが失業や貧困に苦しむなか莫大な利益を挙げたアマゾンのジェフ・ベゾスが宇宙旅行を敢行した2021年に再び注目を集めた。マスクやベゾスは地球のさまざまな問題を解決するためにも宇宙進出は必須なのだと主張するが、税金対策によりほとんど税金を払わないばかりか、逆に政府の宇宙予算を助成金として多額受け取っているかれらが、かりに地球上の問題を解決するための手段を得たとしてもそれを公平にシェアするとはとても思えない。しかもその過程において大量の温暖化ガスや軌道上のゴミなどを生み出し問題を悪化させている。
大気や水、気温、紫外線や放射線などさまざまな問題を解決して火星や月、軌道上のスペースコロニーに多くの人類が住めるようにすることが技術的に可能だとして、どうしてその労力をいまある地球の大気や水、気温などを維持し、あるいは回復するために使おうとしないのか。火星に人類が住めるようにするためにどうすればいいのか誰にも分からないのに対し、少なくともわたしたちは、政治的な意思がまとまらないだけで、地球の環境を守るために何をすればいいのか分かっているというのに。ベゾスによるとそれは、そのような未来は退屈だからだという。自分たちの子孫は自分たちより多くのエネルギーや商品を消費し、自分たちより豊かな暮らしをするべきであり、地球上でそれを実現することはもはやできないから、宇宙に進出する以外の方法はないのだと。
著者はこうした思想に対し、かつての教えを反省し自然との共生を説くようになった(キリスト教ナショナリズム以外の)主要なキリスト教宗派や、世界各地の先住民文化、サン・ラの音楽やオクタヴィア・バトラーの小説などアフロフーチャリズムなどを対比させ、自然と生命に対するリスペクトを市場や利益より上位に置いた科学政策・宇宙政策を主張する。マスクやベゾスが(特に前者が)思想的にヤバいのは明らかだけど、著者は問題はかれらのパーソナリティや個人的な思想ではなくキリスト教から植民地主義、そして第二次大戦後の軍拡競争を経て現在の宇宙資本主義(だけでなく科学信仰を共有する宇宙共産主義にまで)に受け継がれたイデオロギーであることを指摘し、それに対するオルタナティヴを提示している。