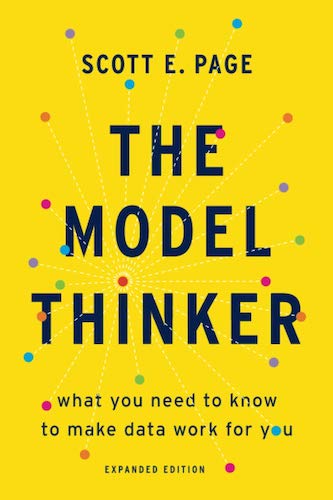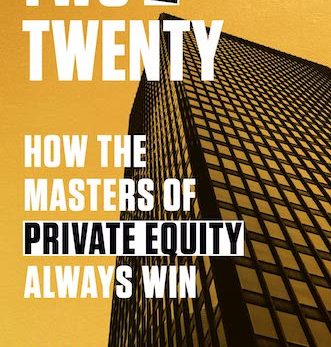Dean Spears & Michael Geruso著「After the Spike: Population, Progress, and the Case for People」
今世紀後半にピークに達するとされる世界人口がその後、急激に縮小する危険について論じる本。
2025年現在、世界の人口は80億人を超えており、今後数十年のあいだに100億人に達すると予測されているが、ここ数世紀の爆発的な人口増加は子どもの死亡率低下によるものが大きく、出生率は長期的に下がり続けている。出生率低下のトレンドが今後も続いた場合、世界の人口は今世紀後半にピークに達したあと急激に減少し社会が成り立たなくなったり、あるいはその危険を口実として女性に出産・育児を強要するような非人道的な政策が取られる恐れがあるとして、まだ余裕のあるいまの時点から人口の安定化について論じるべきだと著者らは主張する。
出生率低下という長期的なトレンドはここ数世紀にわたって一貫しており、一人っ子政策を取った時代の中国も富国強兵政策によって出産を奨励したチャウシェスク政権時代のルーマニアも長期的なグラフにしてしまえば一見どっちがどっちなのか区別すらつかない。世界の国・地域の半数以上では一人の女性が出産する人数が現状維持のために必要な2人を割り込んでおり、韓国や台湾、シンガポール、香港、マカオ、など東アジアの一部の地域では1人にすら届いていない。いまはまだアフリカを中心に一部の国では高い出生率が続いているが、それらの国も長期的には出生率が低下する傾向にあり、ピークを超えたあとの急速な人口減少はいまのところ確実。
18世紀に出版されたマルサスの『人口論』から1968年に出版されたポール&アン・エーリックの『人口爆弾』まで世界人口をめぐる議論においては、人口増加による食糧不足や環境の限界論を交えつつ、白人至上主義的な不安や優生学と結びつき、少子化が進行する欧米において主に人口減少ではなく人口増加の危険が論じられてきた。人口減少が議論されるときは白人国家における白人人口の減少が陰謀論とともに論じられたり、高齢化による労働人口の減少と社会保障制度の危機として論じられることが多い。しかし本書が訴える人口減少の危険はそういうものではない。
本書が問題とするのは、人口減少によって世界がスケールメリットを失い、わたしたちが当たり前に享受している(あるいは享受したいと思っている)豊かで健康的な生活を成り立たせることができなくなることだ。既に過疎化が進んでいる地域を考えるとわかりやすいが、地域の人口が減ると病院や学校が閉鎖され、多様な店舗やレストランも営業を続けられなくなる。それでも今なら都市に行けばそれらにアクセスできるけれど、世界全体で人口が減れば病院が減るだけでなく特定の疾患を専門とする医者は十分な患者が集まらなくなるためいなくなるし、流通網も成り立たなくなる。コロナウイルス・パンデミックが起きたときワクチン開発がものすごいスピードで進んだのは、それにかける予算とのちに売り込むことができる膨大な市場があったからで、市場が縮小すればスマホからワクチンまであらゆるモノの開発と生産が起こらない。
人口が減ったほうが同じだけのリソースを少ない人で分けることになるからより豊かになるのではないか、と考える人もいるが、人口が減少する世界ではその「同じだけのリソース」が供給されない。もちろん環境の限界はあるので人口が増えれば増えるほど良いというわけではないけれど、たとえば『人口論』の時代に比べて世界の人口が爆発的に増えた現在でも食料の絶対量は不足しておらず、飢饉はその分配が不公正だったり遮られたときに起きる。また気候変動に関連づけて人口減少を主張する人もいるが、仮に出生率を急に減らしたところでその結果が人口の総数として現れるまでには時間がかかるので、いまある気候変動の危機に対処するには完全に手遅れ。100年後、200年後の人口がどうなるにしても、気候変動については既存の対策を組み合わせて対処するしかない。
そんな遠い未来の話をいまやる必要があるのか、という疑問に対する著者らの答えは、今後必ず人口減少の危機を口実として「伝統的な家族」を押し付けたり、女性に出産・育児を強要しようとする政策が登場するという予想にある。すでに「白人人口の入れ替えが起きている」と訴える陰謀論者たちのあいだでは「白人の子どもを増やせ」として白人至上主義と女性差別が結びついた運動が広がっており、進行中の少子化・高齢化への対策として女性を「産む機会」扱いする日本の政治家たちが後を絶たないことからもこの懸念はわかる。人口と社会を安定させるレベルの出生率の実現のために多様な価値観や生き方を弾圧する必要はないとして、長期的な視野に立ち、子どもを産みたい・育てたい人がその機会を奪われないような政策を著者らは訴える。