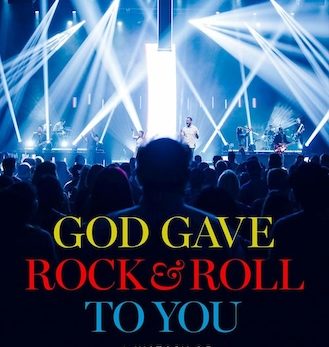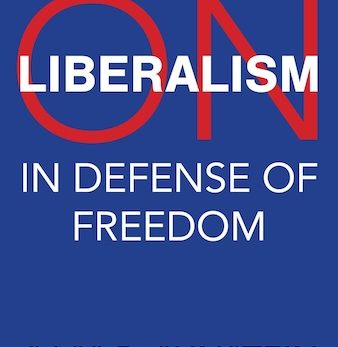Mark Blyth & Nicolò Fraccaroli著「Inflation: A Guide for Users and Losers」
インフレーション(インフレ)についての議論を一般の読者に分かりやすく紹介しつつ、インフレ抑止を口実とした利益誘導や緊縮財政政策に対抗しようとする本。著者らは経済学者として2010年代にそれぞれ別個に緊縮財政論を批判する本を出しており、本書は2021年の夏に起きたインフレをめぐる論争が2010年代に起きた緊縮財政論と同型であることに気づき本書の出版に至った。
2010年代の緊縮財政論は、2008年の金融危機を乗り越えるために実施された大規模な量的金融緩和政策に対するバックラッシュとして起きた。マネーサプライが増えすぎたせいでこのままではインフレになるという懸念が叫ばれ、まだ不況を完全に脱したわけではない段階から、インフレを防ぐために政府の予算を削減する緊縮財政が主張された。その結果しばらくのあいだ不況が長引き失業者があふれるが、長期的には経済が安定するという主張が多くの国で採用されたが、それが失敗であったことはいまでは多くの経済学者たちが同意するところ。ところが2020年代になるとパンデミック対策のために政府が給付金配布やその他の多額の支出を行なったことが2021年のインフレを招いたという議論が再び持ち上がり、今後5年間は5%以上の失業率を受け入れるべきだと主張するラリー・サマーズ元財務長官を中心に再び緊縮財政を求める声があがった。著者らはそれに反論するとともに、インフレは実際にどういうものなのか、インフレをめぐる政治的主張にどのような利害が反映されているのか論じる。
インフレをめぐる言説は政治的に中立ではない。インフレに限らず経済的事象は必ず誰かから他の誰かへの利益の移動を伴い、それによって得をする人や損をする人がいる。たとえば2021年のインフレでは石油価格の高騰が大きな要因を占めており、ガソリンや運輸を必要とするあらゆる商品の価格が上昇し一般消費者の生活が苦しくなったいっぽう、産油国や石油産業は空前の利益を計上した。経済が破綻するほどのハイパーインフレは別として先進国で一般的な範囲のインフレに話を限るなら、インフレが起こす問題は基本的に利益分配の問題であり、仮に物価の上昇に賃金の上昇が追いつかなかったとしても、たとえば石油産業の利益に税金をかけてそれを一般消費者に分配するといった形で対処が可能であり、それ自体は悪ではない。
しかし緊縮財政を主張する経済学者の多くはもともと安い税金と最低限の再分配を理想とする「小さな政府」主義者であり、インフレの懸念は政府予算の削減というかれらの目的に都合の良い口実となっている。また、物価指数やインフレにはそれぞれ有用な定義が複数存在しており、そのどれを選ぶかによって経済がインフレなのかどうか、インフレだったとしてどの程度のペースで物価が上昇しているのかなどに違いが出る。インフレの懸念を口実に政策を通そうとする人たちはそうした多数の指標のなかから持論に都合のいいものを選んで使っており、そのことが人々の理解を遠ざけ混乱を生んでいる。
インフレをめぐる議論で重要なのは、何が原因でインフレが起きているのかということだ。サマーズらはパンデミック対策のために実施された巨額の公共支出がインフレの主な原因であるとして、そのときバラ撒かれた分のマネーサプライを吸収しなければインフレは不可避であると主張するが、ポール・クルーグマンらは2021年のインフレはこれまでのさまざまなインフレと同様に供給側のショック、すなわちパンデミックによるサプライチェーンの混乱やウクライナを侵略したロシアへの経済制裁によりロシア産原油の供給が停止されたことが原因だと主張する。供給側のショックが主な原因であるなら、マネーサプライを減らしたところで景気が悪化して失業者が増えるだけでインフレは解消されないため、ショックが収まるまで物価高騰に悩む一般市民を支えながら乗り切るしかない。大半の人にとっては物価上昇の苦しみは少なくとも失業の苦しみよりはいくらかマシ。著者らは当然後者の立場に立ち、緊縮財政論を批判する。
さらに著者らはワイマール共和国時代のドイツからアルゼンチン、ジンバブエ、ヴェネズエラなどハイパーインフレーションの事例を取り上げ、それらがそれぞれ歴史的に特有の条件のもとで発生した特殊な事態であることを指摘する。そうした特殊な事情には植民地主義時代から残された支配構造だったり国有資源の国際価格の暴落などによりもとから弱かった通貨の価値が下がったことが含まれ、少なくとも現在のアメリカや日本など強い通貨を持つ先進国がハイパーインフレに陥る危険はほとんどない。ワイマール・ドイツにおけるハイパーインフレがナチスの台頭を招いたという俗説があるけれど、ワイマール共和国は1923年に新通貨への移行によってインフレをきっちり収束させており、ナチスが第一党になったのはその10年後。そのころまでには世界大恐慌のなかインフレではなく逆のデフレーションが起きており、デフレ対策を最も強力に打ち出したのがナチスだった。
本書はほかにも経済学上のさまざまな議論に触れつつ、インフレが失業増やデフレと比べてはるかにマシな状況であること、政府や中央銀行には緊縮財政や金利の上げ下げ以外にもインフレを目標以内に抑えるための道具がさまざま存在すること、そうしたさまざまな道具を取らせないようにしているのは政治的イデオロギーとその背後に隠れた政治的強者の利害であることなどを説明する。ただインフレは恐れるに足りないというだけにとどまらず、インフレで苦しんでいる人たちがどのようにしてインフレを抑えるためだという口実で押し付けられる緊縮財政や失業増を拒否し、戦えばいいのか示してくれる。