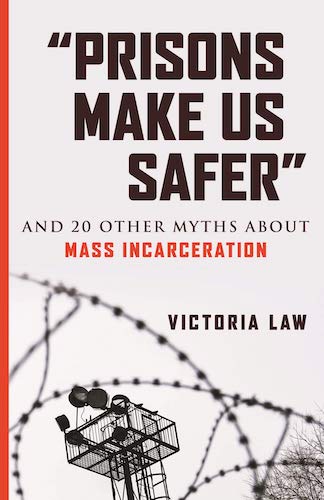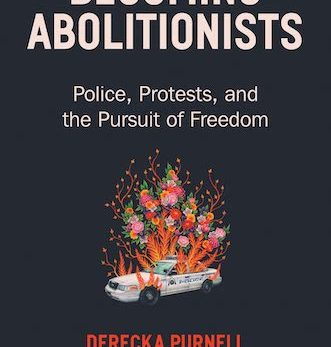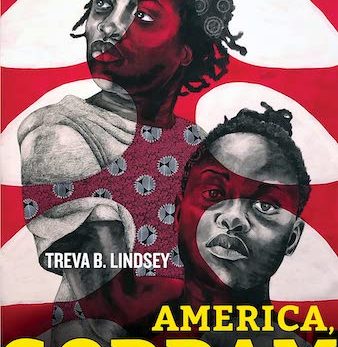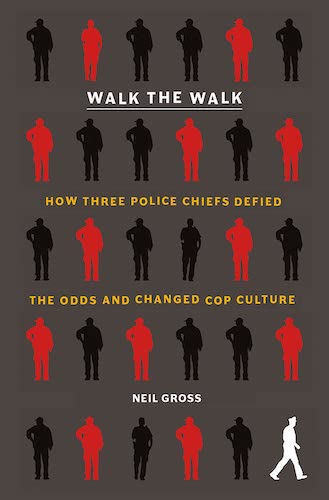
Neil Gross著「Walk the Walk: How Three Police Chiefs Defied the Odds and Changed Cop Culture」
2020年のミネアポリス警察によるジョージ・フロイド氏殺害事件いらい、警察の改革をめぐって議論が続いている。当初はミネアポリスやシアトルなどで警察予算の大幅な縮小や警察の抜本的な解体・再構築や廃止も議論されたが、その後バックラッシュが激しくなり大きな改革は進んでいない。そうした現状に対して本書は、革新的な考えを持つ警察署長のリーダーシップによって既存の警察の組織内カルチャーを変革させた3つの街の例を紹介する内容。
アメリカの警察改革の議論で問題となっているのは、警察による黒人市民への暴力や不当逮捕、証拠捏造などの不祥事が個々の警察官の過ちというよりは、組織内のカルチャーとして広く共有された人種的偏見とシニシズム、ホモソーシャルな同胞意識、そして常に戦場にいるかのような過大警戒だ。もちろんどんな組織にも問題を起こす人はいるが、警察組織のなかでは、一般市民を信用せず、法や規則に従っていたら犯罪を蔓延させてしまうと考え、いつ自分が撃たれるかわからないので少しでも危険があれば先に攻撃するよう教えられ、問題を起こした仲間を守るためには偽証や証拠隠滅などの不正行為も厭わない文化が存在する。こうした組織内カルチャーがある限り、議会や行政が警察改革を試みても実態を変えるには至らない。だから警察組織は一旦解体するほかない、という議論に対して、著者は警察署長がリーダーシップを発揮することによってそうした組織内カルチャーを変革することは可能である、と主張する。
取り上げられているのはカリフォルニア州ストックトン、コロラド州ロングモント、ジョージア州ラグランジという3つの街。人口はサンフランシスコ・ベイエリアの東にあるストックトンが30万人、デンヴァーの北にあるロングモントが10万人、アトランタの南西のアラバマ州境にあるラグランジが3万人程度。それぞれの街で、警察署長は警察の役割を「犯罪者を懲らしめる」ことから「コミュニティを助ける」ことに転換しようとしたり、修復的司法を実践したり、過去に警察が黒人のリンチに参加していた歴史的事実を明らかにして謝罪するなど警察組織が人種差別に加担していた歴史と向き合うなど、さまざまな方法でコミュニティの、とくに警察による暴力に晒されている黒人やラティーノのコミュニティの信頼を勝ち取ろうとしてきた。
こうした試みは、口先だけのことではなく、たとえば警察官の採用や評価にこうした価値観を取り入れるなど、本気で取り組まなければコミュニティの信頼を得ることはできない。また、それぞれの警察内で新たな方針を嫌った警察官たちは抵抗をしたし、署長もそれをある程度認めつつゆっくりと改革を推し進めたが、アメリカの警察では署長が短期間でほかの街に転職することが多いので、長期的に改革に取り組める環境を用意しなければいけない。一部の警察官たちは、新たな方針に反発してほかの警察署に転職するなどしていったが、それと入れ替わりに理想主義的な若い警察官たちが入ってきて順次カルチャーが変わっていったという話も。具体的な話はわりと面白いので各自読んで。
わたし自身は警察解体派で、警察が内部から変わることができる、という主張にはかなり懐疑的。たまたま今日、ロングモントで警察と連携して修復的司法に取り組んでいる民間団体にヘッドハントされた経験のある人と話をしたのだけれど(その人は性暴力サバイバー支援と修復的司法の研究をしている人で、たまたまコロラド州の人だったから「こんな本を読んだんだけどどう思う?」と聞いたら「あ、それ知ってる!」というすごい偶然)、やっぱり地元の人から見ると「ほかの街よりはマシかもしれないけど限界はある」という意見だった。でもまあ、警察解体の勢いは削がれちゃったし、できるものなら内部から改革してみたらいいんじゃない、できるものならね?くらいに生暖かく見守っていきたい。
あとただ、ドメスティックバイオレンスに関する内容については、とにかく逮捕するのが正しいという前提で、そのためにサバイバーを引っ掛けて必要な情報を言わせるみたいな話もあるのでその点はダメ。ドメスティックバイオレンスについてサバイバーたちやサバイバー支援運動がどういう議論をしてきたのか、社会学者の著者がまったく知らないのだとするとまずすぎる。