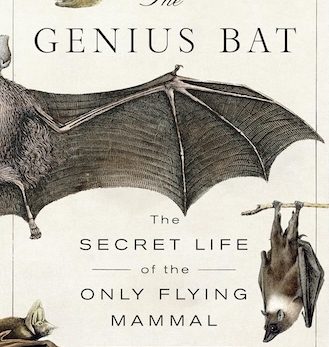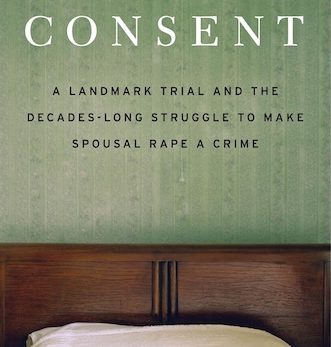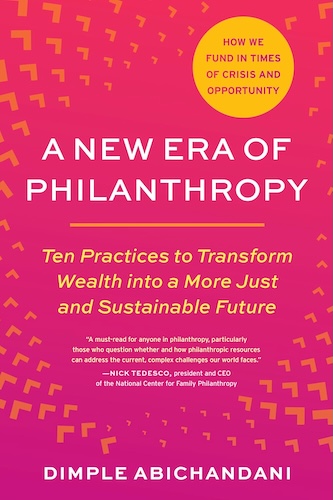
Dimple Abichandani著「A New Era of Philanthropy: Ten Practices to Transform Wealth into a More Just and Sustainable Future」
裕福なベビーブーム世代からその子や孫の世代に財産が相続され、その少ない金額がフィランソロピー(社会貢献活動)に流れていくなか、社会的な格差や不均衡を温存するのではなく変革するためのフィランソロピーのあり方について論じる本。著者は社会変革を目指す財団のスタッフであり、さまざまな財団や富裕層により良いフィランソロピーのやり方についてアドバイスする人。
ミューチュアル・エイド的な助け合いは世界各地に古くからあったけれど、巨額の資産を持つ財団や富豪が主導する現代アメリカ的なフィランソロピーの伝統は、ジョン・D・ロックフェラー、アンドリュー・カーネギー、アンドリュー・メロン、J.P.モーガンらが活躍した「金ぴか時代」に遡る。かれらはそれぞれの分野で市場を独占し、暴力組織を雇うなどして労働組合を激しく弾圧することで巨額の富を蓄積するいっぽう、社会貢献は金持ちの義務であるとして各地に大学や美術館、図書館などを設立した。それらは主に中流階層以上の出身の白人男性だけに提供され、より質素な学校や図書館が人種によって隔離された黒人向けに設置されることもあったけれど、既存の社会階層を脅かすようなものではなかった。また富豪らは自分たちの財産を家族に相続させるのではなく非営利の財団への寄付として扱うことで税制上の優遇を受けたが、その財団の運営は引き続き富豪本人やその家族が担い、給料として、あるいは契約先としてその資金を私的に引き出すことができた。
現代でもそうした仕組みは温存されており、ヘンリー・フォード一家の財産を守るために設立されたフォード財団やビル・ゲイツが設立したゲイツ財団など、貧困や差別をなくすための活動をしていると称する財団も大富豪本人やその一族の意向によって運営されている(ゲイツ財団の実態についてはTim Schwab著「The Bill Gates Problem: Reckoning With the Myth of the Good Billionaire」が詳しい)。
最近、コロナウイルスをめぐる陰謀論(こればかりは謂れのない中傷が多かったのでゲイツが気の毒)やジェフリー・エプスタイン事件への関連(こっちについてはゲイツに対する疑いは濃厚でメリンダ・フレンチさんがビルとの離婚を決意したのが良くわかる)などゲイツに対するバッシングが強まるなか、かつてゲイツ財団でビル・ゲイツの右腕として働いていて、のちにロックフェラー財団に移った著者が書いたRajiv Shah著「Big Bets: How Large-Scale Change Really Happens」という本が出ていて、それをいくつかの社会変革系の財団が猛プッシュしていたので読んだところ、ゲイツ財団に対する懸念が深まるだけだった。そういうこともあり、同じように社会変革系の財団の中で働いている著者が書いた本書にもあまり期待していなかったのだけれど、思っていたよりはだいぶよかった。
まず全ての大前提として、大企業や大富豪はその稼ぎや資産に見合った税金を払え、というのを本書はちゃんと押さえている。政府が人々の生活と健康を支えるだけに十分な財源を持ち、それを政策的にきちんと提供したうえで、政府の支援が届きにくいニッチなニーズに応えたり、政府には実行しにくいような、あるいは必要とされるスピードで実施できないような、実験的なプロジェクトを試行するといったものが、民間のフィランソロピーの役割であるべき。政府が責任放棄しているのを補完するような活動は、一時的には必要なのだとしても、本来は民間の役割ではない。また、フィランソロピーにおけるお金の使い道を資金提供者が勝手に決めるのではなく、実際に支援を必要としている人たちに決定権が与えられるべきだ、とも訴えている。
本書には、著者の豊富はフィランソロピー業界内部の経験から、フィランソロピーのおかしなところにどう気づいたか、支援を受けた側に課せられる報告書作成などの負担をどれだけ減らすことができるか、土地を奪われた先住民や奴隷として扱われた黒人たちの損害を回復するために何ができるかなど、さまざまな具体的なアイディアが含まれている。グラントの報告書作成は超絶面倒だしこっちは事務職員なんていない小さな非営利団体なのでマジなんとかしてほしいわ。わたしはグラントを受ける側なので「え、この人の財団ってわたしグラント応募できる?」と思ってしまったのだけど、フィランソロピーで働く人や、生活していくのに十分以上の遺産を相続してそれをどう使うべきか迷っている人たちにとっては良いガイドとなるかも。