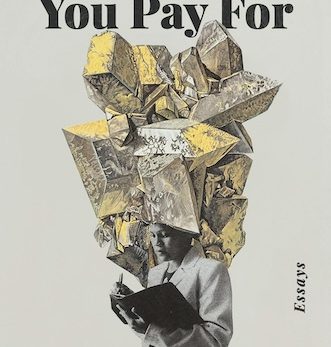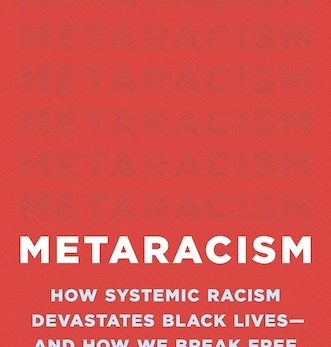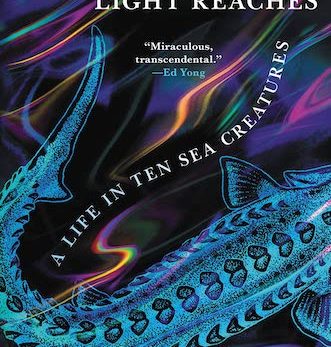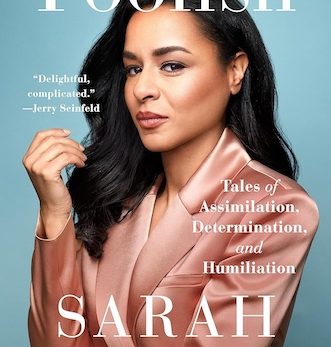Susan Lieu著「The Manicurist’s Daughter: A Memoir」
ヴェトナムからのボートピープル(難民)の娘として育った著者が、美容整形手術の失敗で亡くなったネイルサロン経営者の母親について調べるうちに、残された家族と和解する自叙伝。
著者の一家は中国系ヴェトナム人難民で、著者は一族のなかではじめてアメリカで生まれ、ヴェトナム的な名前を持たない娘。両親はアジア系移民が多く携わるネイルサロンを経営しており、ヴェトナムから親戚を呼び寄せてその多くの女性たちは同じネイルサロンで仕事をしていた。もともとヴェトナムからアメリカへの移住を先導したのは母親で、経営者として成功し親戚一同をまとめる有力者だった彼女は、しかし著者が11歳のときに美容整形目的の脂肪吸引手術の失敗により亡くなってしまう。あれだけ自信満々にサロンを切り盛りし、親戚一同を支援し、多数の従業員を率いていた彼女がどうして?という疑問に答えがみつからないまま、著者は母親の死について父やその他の家族に問うことを禁じられて育つ。
本書の最初の三分の一くらいは一家のなかに生まれたタブーに悩まされ、またヴェトナム人の親戚にもアメリカ社会にも溶け込めずに孤立感を高めた著者が、スタンダップコメディに挑戦してスベリ倒したり、ヨガをきっかけにカルトにハマって搾取されたりという話で、わたしは一体なにを読まされているんだと思い始めたのだけれど、大人になった著者が母親は実際どういう人だったのか、どうして彼女は美容整形を受けようと思ったのか調べはじめるあたりから、本書はめっちゃおもしろくなっていく。
著者の両親が育ったのは、ヴェトナム戦争が進行中だった南ヴェトナムの首都サイゴン。米軍が当時の南ヴェトナムの支配層を連れて撤退し、北ヴェトナム軍がサイゴンを占拠し街の名前をホー・チ・ミンと改称すると、つい最近まで敵側だった住民を信用しない共産党政権による厳しい管理がはじまる。そういうなか著者の母は違法な宝くじを運営するなど早くから経営手腕を発揮し、家族を連れて国外への脱出を試みる。軍の監視に見つかりそうになり逃げ出したり、全財産を持って国外逃亡しようとする人たちを狙う盗賊にお金を差し出して見逃してもらったりして、六度目の試みでついにタイへの脱出に成功。そこから運良くアメリカに難民として移住することを認められる。カリフォルニアに移住した両親はネイルサロンを開店、その後親戚を呼び寄せてビジネスを拡大していく。
母の美容整形手術を担当したのは、ヴェトナム戦争への従軍経験のある白人の医者。過去に問題を起こして医師資格の適格性が審査されているばかりか、医療瑕疵保険に加入すらしていない人物だったが、ヴェトナム人女性をターゲットとしてヴェトナム人移民向けの新聞に美容整形の広告を出していた。当時、ヴェトナム人移民女性の多くは、ヴェトナムから一緒に移住してきた夫がアメリカ人女性に奪われることを恐れ、美容整形に関心を寄せていたという。またヴェトナム人コミュニティのなかでは女性の体型に対する基準が厳しく、アメリカ人としては平均的な体型だった著者は繰り返し家族やヴェトナム人の親戚に痩せるよう言われたり体型をからかわれたりする。当時の資料を調べた著者は、医者が十分なインフォームドコンセントを実施していなかった証拠や、母が呼吸困難に陥ったにもかかわらず医師がすぐに対処しようとしなかった事実を突き止め、責任追及を考えるも、そのほんの数ヶ月前にその医師は亡くなっていた。謎の行動力により医師の遺族にコンタクトを取るも、まあ当然協力は得られない。
著者はさらに、母のことをもっと知りたいと考え、アメリカにいる父や親戚だけでなく繰り返しヴェトナムを訪れ彼女の子ども時代を知る人たちを尋ねるも、あまり話を聞かせてもらえない。あとから分かったのだが、母が生まれ育ったのはヴェトナム戦争が起きている最中であり、かれらはかれらなりに戦時中に起きたことはトラウマとして心の底に埋めていたのだった。子どものころ、母がどうして亡くなったのか知ろうとした著者が父や親戚たちによって黙らされたのも、戦争を生き延び、難民として言葉もわからない土地で生活をやり直そうとしているかれらにとって、悲しさも心の傷も黙って受け入れやり過ごすことが生きるための方法だったからだった。
そのことを理解してから、著者はトラウマを抱えた親戚たちにより上手に話を聞くことができるようになったし、パフォーマンスアーティストとして母親をテーマとした一人劇を演じるようになった著者がパフォーマンス後のステージに家族を招いてパネルに出てもらったときには家族のあいだでは出てこなかったような話が聴衆のまえで飛び出したりもした。そこで著者が気づいたのは、母の死に深く傷つき、答えを知りたいと思っていたのは著者だけでなく、家族みんなが同じだったという事実。アメリカで生まれ育った著者はそれをストレートに表現し、また周囲の人たちから話を聞こうとしたけれど、戦争と国外への脱出によるトラウマを抱えていた家族・親族はそれとは異なるかたちでその経験と折り合いをつけようとしていた。移民二世の著者が母親について調べるうちに、母親だけでなくそれ以外の家族や親戚との関係とともに、自分自身に対する理解も深める物語。
著者はシアトル在住だけれど、わたしは知らなかった。彼女のサイトでは母をテーマとした演劇「140 LBS: How Beauty Killed My Mother」を視聴することもできる(有料)ようなので、これから観たいと思うし、機会があれば彼女のパフォーマンスも観に行きたい。