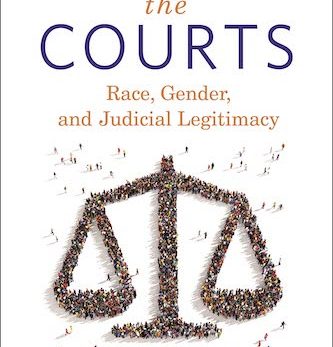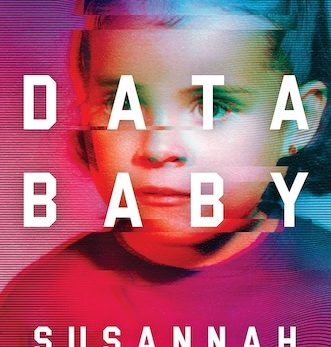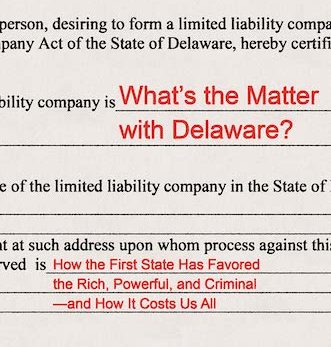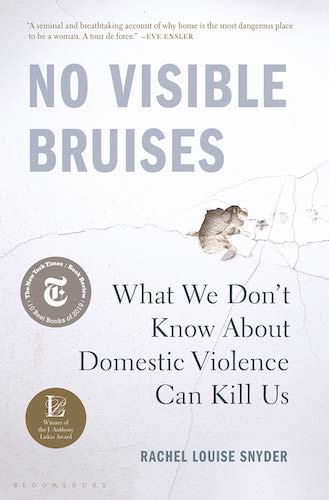
Rachel Louise Snyder著「No Visible Bruises: What We Don’t Know About Domestic Violence Can Kill Us」
ドメスティック・バイオレンスに対する警察や大手民間支援機関の近年の取り組みを紹介する2019年の本。この本ではとくに、DV被害者が殺害される危険が高いケースを判定してほかより優先的に介入する試みや、刑務所内における加害者に対する更生プログラムについて詳しく書かれていて、刑事司法制度の外側での取り組みに関わっているわたしのアプローチとはかなり違うのだけれど、興味深かったし考えさせられる点も多々あった。著者はジャーナリストで、長いあいだカンボジアやアフガニスタンなど内戦が起きた(起きている)国で女性に対する暴力について取材していたけれど、自国アメリカのそれを無視していたことに気づいて調査をはじめたらしい。
殺害の危険が高いケースを判定して介入するプログラムは各地にあって、わたしの知り合いにも一人そういうプログラムで働いている人がいたので少しは話を聞いたことがあるのだけれど、本書ではマリーランド州反DV連盟が作成したLethality Assessment ProgramとCampbell et al.によるDanger Assessmentという2つのアセスメントツールが紹介されている。それぞれ違いはあるものの、大部分は共通で、加害者が銃を持っている、殺すと脅したことがある、失業中である、被害者が命の危険を感じている、などの要素を満たす場合に「特に殺害の危険が高い」とされる。中でも「加害者が被害者の首を締めたことがある」という要素があり、統計上殴る蹴るなどほかの暴力に比べ、首絞めがあったケースではのちに殺害に至る危険がとくに高いとされている点は注目したい。
問題は危険が高いとされた場合にどのように対処するかだ。アセスメントの結果、あなたはほかのDV被害者に比べて特に殺される危険が高いと思われます、と被害者に通知するとともに、被害者が望むならすぐに逃げるために必要なリソースを提供したり、その被害者の住んでいる地域を警察が頻繁にパトロールするとともに、とくに危険だとされた加害者を法的に可能な限り勾留し続けたり、釈放するにしてもGPS錠を付けさせる、という取り組みが自治体によっては行われているけれども、裁判で有罪が確定したわけでもない人の権利を制限することには人権上の問題があるし、もし仮にアセスメントツールに人種的その他のバイアスがあればさらに大きな問題になりうる(そして、失業などの要素がアセスメントに含まれる以上、バイアスは存在すると思われる)。またアセスメントを使ったビッグデータ的・アルゴリズム的決定には「アルゴリズムによって危険だと判定される→警察による巡回や監視が強化される→結果として逮捕される確率が高まり、危険だというデータが積み重なる」というフィードバックループが働くので、バイアスは是正されるどころか増幅される危険がある。著者は最初の人権上の問題だけ軽く「批判もある」と言及しているけど、最近議論されているほかの論点には一切触れておらず、DVに関する議論が「警察を重要なパートナーとみなしより関係を強化すべきと考える側」と「警察を暴力の一種とみなしできるだけ警察に頼らない解決を目指す側」で分断されていることを痛感する。
刑務所内におけるDV加害者更生プログラムについての記述で著者は、ありがちなアンガー・マネージメント(怒りの感情をコントロールするための心理プログラム)はDVには向かないと正しく指摘したうえで、(加害者の大部分を占める)男性たちがどのようにして物事を解決するために暴力を使うことを学んだのか、女性たちに対する見下した視線や態度を身につけたのか、ほかの男性たちとの関係を競争とみなすようになってしまったのか、というように、「有害な男らしさ」を解きほぐすためのプログラムが必要だと書いている。ただ刑務所自体が暴力的な環境であり、ほかの収容者たちの前で弱さを見せたり女性を尊重する態度を示すことは自分のステータスや安全を脅かすことになってしまうので、きちんと立ち直ることは難しそう。また刑務所を出所しても、もといたコミュニティに戻ればまた強い男を演じなければ仲間や就職機会を失ってしまう場合も多い。
DV加害者は更生できるのか、という問いに対して、著者はこのように書いている。警察や支援者は「更生できない」と言う、加害者本人たちは「更生できる」と(自己愛性パーソナリティそのままに)自信を持って宣言する、それに対して被害者たちはこう言う、「更生してほしい」と。わたしは更生は「できる」と思うけれども、それは本人が本心から変化を望み、そしてそれをコミュニティが支えた場合、という条件がつく。ところが加害者が自ら「変わりたい」と思って更生プログラムに連絡するケースはごくわずかで、裁判官に命令されたからとか、裁判で有利になるためだとか、より早く釈放してもらうためとか、あるいは別れたいと言っている被害者を繋ぎ止めたいからだとか、そうした「自分を変えたい」以外の理由でプログラムに参加する人が大多数。そういう人たちの中に交ざってしまうと、本当に変わりたいと思ってプログラムに参加した人までスポイルされてしまうので、「自分の意思で参加した人だけ」なおかつ「参加しても自分が変わるチャンス以外になんの利益もない」プログラムでないといけないとわたしは思っている。
この本はまた、DVに対する研究において重要性が認識されてきている「威圧的な支配」および「自己愛性パーソナリティ」という概念について触れている点も良いのだけれど、著者が「威圧的な支配」を犯罪として扱うような法改正を肯定的に紹介している点や、ドメスティックバイオレンスは「親密な関係によるテロリズム」と呼ぶべきだ、と言っている点など、同意できない部分も多い。前者については、DVの本質が「威圧的な支配」であるというのは正しいのだけれど、警察や刑事司法制度はそのような目に見えない関係性の不公平を扱うようにはできておらず、バイアスに基づく逮捕や、被害者の側が間違えて逮捕されるケースを連発してしまう危険がある(ワシントン州でも「威圧的な支配」を犯罪と規定する法案が今年出されたけど、DVサバイバー支援団体は反対した)。後者については「テロリズム」という言葉の持つイメージが少なくとも米国では特定の人種や宗教の人たちに対する強烈な偏見と結びついており、DVの深刻さを世間に訴えるよりはそこまで極端ではない大多数のDVを「これはテロリズムというほどではない、つまりDVではない」と世間や加害者本人や被害者にまで認識させ、むしろ加害者の責任追及を難しくしするおそれがある。また、「反テロリズム戦争」のなかでさまざまな政府による違法行為や戦争犯罪が(テロリストだけでなく、無関係の民間人たちを対象に)行われたことを考えると、あまり使いたい言葉ではない。
このようにわたしは著者とはアプローチがかなり違うのでいろいろ不満な点もあるのだけれど、DVと闘っている多くの人たち、とくにサバイバーやその家族たちのストーリーには勇気づけられた。