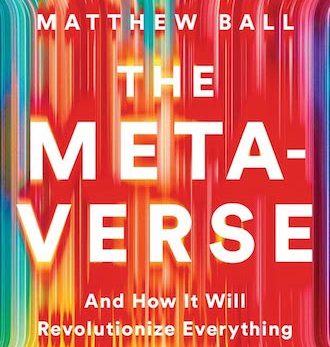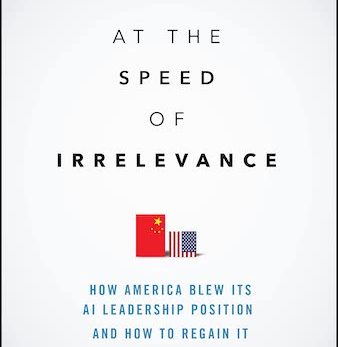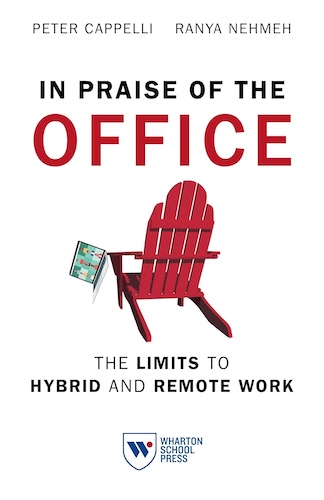
Peter Cappelli & Ranya Nehmeh著「In Praise of the Office: The Limits to Hybrid and Remote Work」
コロナウイルス・パンデミックを契機に広まったリモートワークやリモートと出社を組み合わせるハイブリッドワークについての研究をまとめたビジネス書。ビジネス目線というか経営コンサル目線なのでリモートワークの社会的な側面にはあまり触れられていないけど、十分の興味深い内容。
2010年代になってから技術的には可能になったリモートワークだけれど、それが実際に広く使われたのはパンデミックになってから。必要に迫られて導入がはじまるまで採用が見送られてきたのは、リモートワークなんて導入したら労働者がサボるようになる、生産性が落ちる、という経営陣の不安が主な原因だったけれど、実際に導入してみたら(リモートでできる業種については)思っていたよりうまくいったし、労働者も通勤する時間が浮くし家でほかのことをやりながらマルチタスクできるので歓迎する人が多く、テクノロジー企業を中心にパンデミックが収束してもリモートワークを続ける、と宣言する会社も出てきた。
それから数年、リモートワークを歓迎していたテクノロジー企業は軒並み前言撤回し、社員の出社を求めるようになっている。どうしてこうなったか、という疑問に応えようとするのが本書。まあ理由はいろいろあるけれど、リモートワーク導入直後はそれまで職場で培ってきた非公式なネットワークがあって、そこで築いた関係性が機能していたけれど、数年たって人がどんどん入れ替わるとそれが希薄化し、職場を成り立たせていた非公式な教え合いや助け合い、先輩から後輩への知識や技術の伝授、その他もろもろが機能しなくなっていったというのが大きいポイント。また、そもそも経営陣がリモートなんてうまくいくはずがないと思いこんでいたせいで、もともと期待値が低かったことも「やってみたら意外とうまくいった」という初期の評価に繋がった側面もある。さらに、労働者のなかにもかつてのような職場の繋がりを求める人は少なくないし、採用されたばかりの新人にとっては仕事を教えてくれる人も相談相手もおらず、普段の仕事ぶりを評価してくれる上司との関係も希薄となると、キャリア上昇のチャンスを得られないという問題も生じる。
しかし企業側は、リモートへの移行を逆転させようにも、パンデミックのなか少しでも費用を削減しようとオフィスを閉鎖したり大幅に縮小してしまっているので、全社員に出社させることもできない。そこでハイブリッド制を導入して一定の日数の出社を義務付けたり、個々の社員の個室やデスクを廃止して共有にしたりするけれども、これが最悪で、個々の個室やデスクを持たない社員は仕事の意欲を削がれるし、出社したところでほかに誰が出社しているのか分からないのであればチームが集結することもできず、結局リモートで会議をすることになってしまう。個室やデスクを固定しないオフィスや、そもそも個室がなく大部屋で働くタイプの職場設計はパンデミック以前から一部では導入されていたけれども、自分のスペースとしてパーソナライズできず後で同じスペースを使う人や周囲の人たちに迷惑かけないよう気をつけなくちゃいけないので実際の労働者たちからは一貫して不人気で、それがオフィスの経験となったらますます出社したくなくなるのは当たり前。オフィス内でいろいろな人に頼られていた有能な人がリモートで働いたら邪魔が入らないため快適に仕事ができるようになり生産性が向上した、というのはまあそうだろうと思うのだけれど、その人に頼っていた人たちの生産性が下がっていたら総合してマイナスになっている可能性が高いので、非公式に頼られる有能な人たちには職場内で果たしている非公式な役割に見合っただけの評価を与える方法が必要そう。
リモート導入により会議が長くなった、参加者も増えたけれどマルチタスクしている人が多くて実際にどれだけの人が注意を払っているか分からず無駄なフォローが増えた、などの指摘については、リモート会議のやり方がもう少し洗練されればある程度解決できるんじゃ、と思わないでもないけれど、職場を共有することは業務に直接関係しない部分で非公式なさまざまな効果があった、というのは解決しなさそう。フルタイムでメタバースに入って仕事をするということも当面なさそうだし。オフィスにホワイトカラー労働者が集まるのは、ただ単に生産資本であるコンピュータや電話やファイリングキャビネットがそこにあるからでなく、職場をともにする人たちの非公式な関係性が生産性を高めているからだということが、パンデミックをきっかけとした世界的な実験によってようやく認識されだした。