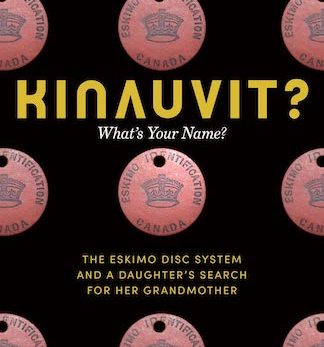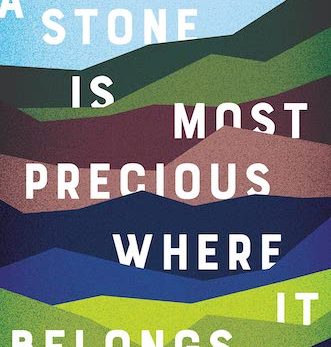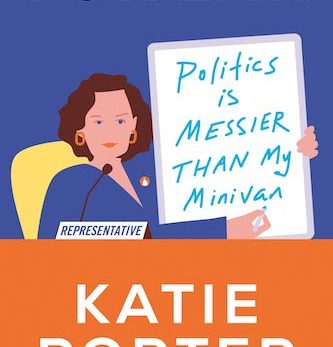Melody Glenn著「Mother of Methadone: A Doctor’s Quest, a Forgotten History, and a Modern-Day Crisis」
維持療法・医薬補助療法と呼ばれる薬物依存治療の現場で働く医師の著者が、1960年代に合成オピオイドのメサドンを使った維持療法を普及させた医師マリー・ナイスワンダー氏の存在を知り、時代を経て同じ分野で働く女性の医師として彼女の人生と著者自身の過去を振り返りつつ並置させていく複合的な伝記。
著者はもともと緊急医として働いており、オピオイド鎮痛剤を求めて頻繁に忙しい緊急治療室を訪れる薬物依存者たちに不満を感じていた。事故や病気で今すぐ治療を行わなければいけない患者がたくさんいるのに、なんらかの症状を訴えて薬の処方を求める薬物依存者たちの相手をしている暇はないが、それでも規則上、かれらの話を聞いて検査もしなくてはいけないし、そのせいで治療が必要な急患患者たちが待合室で待たされるのは不公平だと。しかしかれらが本当に治療を必要としているかもしれないのに「どうせ依存症だろ」とはなから相手にされるなどあまりにひどい扱いを受けているのを見続けた著者は、かれらも依存症という疾患を抱え支援を必要としている患者なのだと気づき、薬物依存治療の道に進んでいく。
複数のクリニックで仕事を掛け持ちしていた著者が新たな職場に選んだのは、オピオイド依存の治療のためにメサドンを処方するクリニック。メサドンはヘロインなどと同じオピオイドの一種だけれど、強い作用がないが禁断症状を抑えることはできるとともに、代謝が遅く一日持つため、毎日同じ時間に摂取すれば違法な薬物への必要性を代替できる。「それは他のオピオイドへの依存をメサドンへの依存に置き換えているだけだ、薬物摂取をやめられるのでなければ治療とは言えない」という根強い反対論もあるが、現代の精神医学では依存症を本人や周囲が被る被害・損害から定義しており、本人が問題なく社会生活を送れるのであれば医学的問題とはみなされない。糖尿病患者がインシュリン投与を続けるように、あるいは足が不自由な人が車椅子を使うように、薬物依存のある人にもメサドンやブプレノルフィンなどを使った維持療法によって安定した生活を取り戻してもいいはずだ、という考えがそこにある。
この療法を普及させたナイスワンダー氏は、1944年に当時ごくわずかな女性医大生として卒業し、多くの同級生たちとともに第二次世界大戦に軍医として参加しようとしたが、女性の医師をどう扱っていいかわからない、受け入れる体制がないとの理由で本来望んでいた外科医の道を閉ざされ、当時医学の中でも比較的女性の進出が進んでいた精神医学を専門とした。しかしナイスワンダー氏は薬物依存の専門医として有名になったあとのインタビューで自分は性差別を経験したことは一度もないと言ったが、米軍や外科からの拒絶はもちろん、医学界ではのちのちまで彼女の功績を薬物依存とは別の分野の専門家である三番目の夫のものだとする説が信じられるなど、どう見ても性差別は受けている。また彼女はのちにフェミニズムを強く否定し、女性は家庭を守り男性に尽くすべき、性的に夫に求められたら全て応じるべき、などと主張する本を書いており、生涯を通して男性社会の中で仕事を続けただけでなく二度も離婚した本人の履歴との乖離が激しい。彼女の業績に敬意は払いつつ、彼女のことを先駆的な女性医師として持ち上げるのは難しいけれど、どうしてこんなことになったのかという著者の想像は興味深い。
著者自身もキャリアを通して、薬物依存症のある患者のことを「医療のリソースを無駄遣いさせる迷惑な連中」と見下していた時期からはじまり、薬物依存を倫理的な間違いではなく病理的な疾患と理解してより良い医療を届けようとした時期を経て、薬物依存が個人の病理ではなく人種差別や貧困など社会的な不公正に根ざしていることや薬物政策が人種差別や移民やホームレスの排除に基づいていることに気づき、ハームリダクションの理念に共鳴し州で違法とされている注射器やパイプの配布に参加するまでの考え方の移り変わりが記されている。また、ナイスワンダー氏も著者も、理不尽な政策や病院のポリシーによって薬物依存治療を妨げられたり「薬物依存者が集まる病院だと思われたら困る」として治療プログラムの存在を隠蔽されたりする経験をしており、これだけ薬物依存症の蔓延が叫ばれているのにエビデンスに基づいた薬物依存治療がなかなか広まらない理由もよくわかる。
とくにおもしろいのは、著者が一時期シリコンバレーの女性起業家に誘われて、維持療法に全国どこでもアクセスできるようにするスタートアップに参加した話。アメリカでは過去に一部の医師が大量にオピオイド鎮痛剤を処方したせいで薬物依存が蔓延したという認識が広まった結果、オピオイドの処方に対してさまざまな厳しい制約が課されることになったが、そうした制約は依存治療のために使われるメサドンやブプレノルフィンにも適用されてしまう。自然と地方ではそれらを処方する医師が不足し、治療を受けたくても受けられない人が大勢いるのだが、それを解決するためにリモート医療でそれを処方しようというのがこのスタートアップの試み。法律上、最初の処方箋をもらうためには対面医療を受ける必要があるので、そこは一度だけ少し遠出してもらってでも全国のどこかのクリニックに足を運んでもらって、それ以降は著者がリモートで面談して処方箋を出すという仕組み。
詳しくは説明しないけれども、合法的に活動するために著者が頼りにしていたスタートアップ企業の専属弁護士は医療ではなくテクノロジー・スタートアップを専門としている人で、著者が「これは大丈夫か」と相談したことに大して調査もせずに「大丈夫大丈夫」と後押ししてきたり、間違っていたことが判明した際も匿名で州政府機関に電話して質問して「一度きりのミスなら大丈夫だって」と報告してきたけど、実際には全然大丈夫でなくて、著者は医師としての責任に違反したとして調査対象とされてしまう。会社の弁護士は「罰金を大目に払うことで違反の程度を軽くしてもらう」という取引を実現させたけれども、調査を受けた記録は永久に残り、著者が新たな仕事に応募するたびに説明しなくてはいけないハメになる。自分だけ責任を負わされるのやってられんわ、と著者はその会社を離れるのだけれど、これって典型的なシリコンバレーのやり口でしょ。既存の法やルールに合致しているかどうか気にせず一気に新たな市場を独占し、のちに利益を得るというシリコンバレーのやり方は、uberやAirBnB、OpenAIなどでは通用するかもしれないけれど、医療に手を出したら(少なくとも現政権より前は)政府が黙っていない。最近だと23andMeが痛い目を見て思い知ったところ。
ハームリダクションの活動に関わっているわたしにとっても維持療法の歴史について新たに学んだこともあり、またナイスワンダー氏の自己否定的なアンチフェミニズムだけでなく著者の発言にもいくつか「うーーん」と唸ってしまうところがあった本だけれど、いろいろ興味深い内容ではあった。しかし、本書のタイトルの「メサドンの母」はナイスワンダー氏のことを指していると思うけど、メサドンはもともと化学兵器開発やホロコースト政策にも関与していたナチスドイツの大手製薬会社が開発し、第二次大戦後にドイツ人研究者たちを吸収したアメリカの大手製薬会社が発売したものであり、「メサドンの父」はナチスの科学者なわけだけど、それを考えるとこのタイトルはどうかと思う。