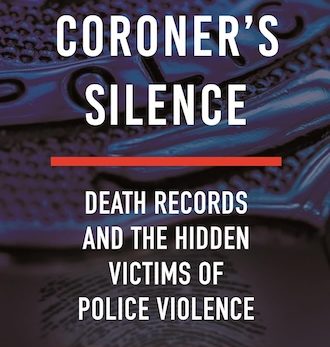Megan Greenwell著「Bad Company: Private Equity and the Death of the American Dream」
ブラックストーン、カーライル、アポロ、KKRなど近年急速に規模を拡大しているプライベート・エクイティ(PE)投資ファンドが人々の生活に与えている影響を、PEによって買収された企業で働いていた労働者や、PEによって買収されたあと閉鎖された地方の病院の医者、地元に根づいた独自の取材を行えなくなった地方新聞の記者ら、多くの人たちの経験を通して伝える本。
プライベート・エクイティは本来であれば、何らかの問題を抱えている非公開企業を買収して、経営改善し、その後売却することで利益を挙げる投資ファンドとされている。その経営改善の過程で多数の従業員を解雇したり、事業の一部を個別に売却したり廃止したりするが、それでも一応は経営を向上させ企業の価値を高める、そうすることで最終的に企業を高く売却して投資の利益を挙げるのだ、というのが建て前だったが、それは実態の全てではない。少し前のトイザラス(おもちゃ屋)や最近だとレッドロブスター(レストラン)の例に見られるように、買収先の企業に借金をさせそのお金で買収したことにする(ファンドは投資額を抑えられるが、借金返済により経営は悪化する)、買収した企業が店舗を展開するために持っている土地を自分たちが運営する別のファンドに売却させ、その売り上げを利益としてファンドに還流させたうえで、買収先の企業に高額な家賃を払わせる、などの手法により、最終的にそれらの企業を倒産させてでもファンドが利益をむしり取る手法が次々に開発されてきた。
もともと大きな企業を投資の対象としていたPEファンドはいま、リテールや医療、地方新聞に加え、不動産、老人ホーム、漁業、エネルギー産業、ファッション産業、民営化された刑務所、営利目的の大学、さらにはサーカスのシルク・ドゥ・ソレイユや最近本人が買い戻すまでテイラー・スウィフトの初期のアルバムの原盤権まで、ありとあらゆる業界に触手を伸ばし、アメリカの労働者の8%はPEファンドが所有する企業で働いていると言われている。一見独自に経営されているように見える地域の小さな託児所やペットクリニックの多くがいつの間にかPEファンドによって買収され、寡占化され、経営合理化という口実のもと労働条件やサービス内容が犠牲とされている。その影響は地方で特に大きく、地方の病院が統廃合され医療を受けられなくなったり、地元の消防署や救急搬送、水道局などがPEファンドによって経営合理化され料金が上昇するなど人々の生活が圧迫されている。
アポロのファンドマネージャをやっていた人が書いたPE礼賛の本「Two and Twenty: How the Masters of Private Equity Always Win」にあるように、ファンドマネージャは投資による利益の20%と投資家から預かった金額の2%を報酬として受け取るが、これは利益を挙げなくても多額の投資額さえ集めればそれだけで大きな収入を得られることを意味する。また買収した企業から利益を流出させる先に自分が投資しておけばそこからも利益を得られるし、PEファンド関係者から多額の寄付を集める政治家たちによって税法的にも優遇されている。一方、PEファンドに投資してお金を預ける側のインセンティヴもそうしたファンドマネージャに対する牽制にならないことは、Jeffrey C. Hooke著「The Myth of Private Equity: An Inside Look at Wall Street’s Transformative Investments」に書かれている。
最近こればかり言ってるけど、アメリカ終わりすぎててまじ終わってる。エリザベス・ウォレンせんせー助けて。