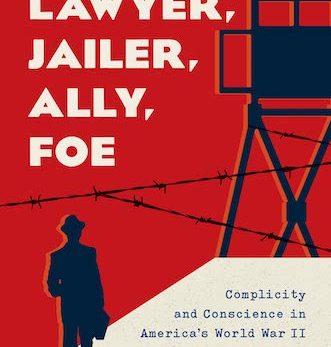Helen Lewis著「The Genius Myth: The Dangerous Allure of Rebels, Monsters and Rule-Breakers」
かつて投資家や世間に天才として崇められていたイーロン・マスクのメッキが剥がれ落ち木っ端微塵に消え去ったいま、そもそも天才とはなんだったのか、どこからそんな概念が生まれ、どのような働きをしてきたのか、どのように終焉を迎えつつあるのか探る、普遍的にしてタイムリーな本。
本書は西洋における天才という概念の拡散を18世紀のロマン主義の時代に求めるが、しかしそれが指すものは主に白人の男性がそれに該当するという部分以外は現代とは異なっていた。上流階級出身の、あるいは上流階級のパトロンを持つ、詩人や文学者、作曲家らが天才と呼ばれ、男性でありながら中性的、あるいは女性的な繊細さを持つことが要件に。John Green著「Everything Is Tuberculosis: The History and Persistence of Our Deadliest Infection」にも書かれていたように、結核による吐血や若くしての死がその繊細さの象徴とされた。
19世紀から20世紀にかけて科学が進歩し、リネアの分類学やダーウィンの進化論、さらにそのダーウィンの従兄弟だったゴルトンが創始した優生学が広まると、人類を知性によって序列化し、天才を遺伝的形質として捉える考えが影響力を得る。遺伝的形質であるならば、繊細さやか弱さは進化的に不利な要因であり、身体的・精神的に頑強であることと天才としての素質が結びつけられていく。また社会的強者である天才は社会的規範や法からも逸脱しているのが当然であるとして、自閉症など一般には優生学的な抹消の対象となるような形質ですら天才には必要な社会的逸脱として好意的に評価されるようになった。ビジネスや政治の世界では天才を自称する人たちが社会的逸脱を周囲に受け入れさせることで天才という評判を定着させ、さらに自己中心的に権力をふるまうようになる。
しかし天才というのは、あくまで優生学と政治権力の行使によって社会的に作られた概念でしかない。もちろん特定の分野で優れた才能を発揮する人はいるけれど、才能があれば必ず成功するというものではなく、生まれてきた社会がどういう社会であるのか、どういう機会が与えられるのかによってそれは大きく左右される。また、ある分野で天才と呼ばれるほどの才能を見せた人でもその名声をもとに別の分野で権力を行使した結果おかしなことを巻き起こしているのもよく見る。あれほどの天才だったマスクがどうしてこんなことになったのか、とか、マスクは実は天才ではなかったのではないか、というのは、天才という概念をあまりに自然化・全面化した間違った問いの建て方。マスクはたまたま生まれてきた時代や環境に恵まれ、またそれにマッチした資質を持っていたかもしれないが、それだけでしかない。どんな時代や環境に生まれても成功する天才もどんな分野でも成功できるような天才も存在しない。自分がそうした超人であると思い込み、自分の社会的逸脱は許容されるのが当然だと振る舞う自称天才は迷惑でしかない。
マスクは今後も財力や権力を謳歌するのかもしれないけれど、かれを天才として崇める人は確実にかつての何分の一にも減った。マスクだけでなくシリコンバレーの「天才」たちの評判もここ十年くらいで大きく失墜し、metoo運動などによって他者に対する危害を加えるタイプの「天才」の逸脱もかつてほど許容されなくなりつつある。このままでは天才が実力を発揮できなくなる、社会的損失になる、というアイン・ランド主義者らの声も出ているけれど、もともとそんな天才が存在しなかったのであれば、より人々が「天才」に対する現実的な懐疑を向けるようになりつつあることは良いことのはず。
本書はほかにもトマス・エジソンのなりふり構わない自己プロデュースや、優生学や「知能指数」の暗黒の歴史、ビートルズが失われた社会でビートルズの楽曲を覚えていて自分のものとして発表する人がいたらどうなるかをテーマとした作品群についての考察、「天才」とニーチェの「超人」との関係、その他さまざまな話題に触れ、天才という概念がどういう歴史を辿ってきたのか明らかにしている。