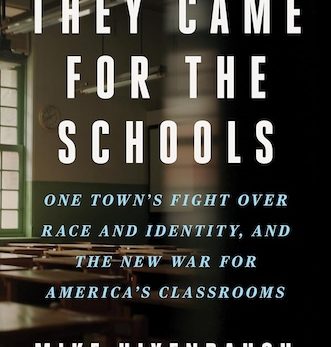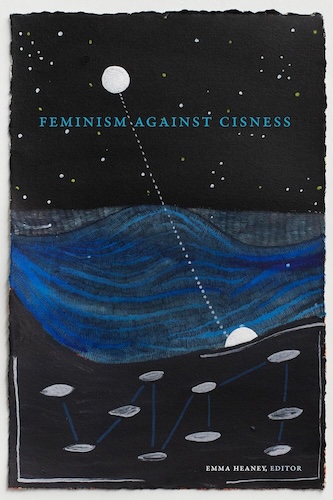
Emma Heaney編「Feminism Against Cisness」
シスネス(シスジェンダー・シスセクシュアリティ)に反対するフェミニストによる論集。ここでいうシスネスとはシスジェンダーの個人ではなく、二元化された「生物学的性」を自然で標準であるとする非歴史的・非社会的な解釈と、それを通して性差別やシスヘテロセクシズム、人種主義、植民地主義などを温存しようとする仕組みのこと。本書は「シスネスはフェミニズムにおける反革命である」という言明にはじまる編者による序章に続き、「Black Trans Feminism」著者のMarquis Bey氏や「A Short History of Trans Misogyny」著者Jules Gill-peterson氏を含むさまざまな論者による9つの論文と終章で構成される。
「Before We Were Trans: A New History of Gender」を書いたKit Heyam氏のように歴史のなかから現代のトランスジェンダーに繋がる存在を探す研究者たちは、性自認やトランスジェンダーという概念が普及する以前の人たちをトランスジェンダーと呼ぶことはできない、として現代のカテゴリを歴史上の存在に当てはめることを避けているが、かれらがそうした学術的にまっとうな態度を取ることが、トランスジェンダー概念が登場する以前の人たちはみんなシスジェンダーだったのだ、という間違った解釈を後押ししてしまっている。トランスジェンダーという例外が社会的に認知される以前はデフォルトとしてシスジェンダーだったのだという認識はしかし、シスジェンダーがトランスジェンダーより後発の概念である事実や、自然で二元的な性別概念を社会的に流通させるために、そしてそこから逸脱したアフリカ大陸や南北アメリカ大陸の文化を反自然的で劣ったものだとして奴隷制や植民地主義の根拠として利用するために動員されたさまざまな宗教的・政治的な権威と権力の行使を不可視化してしまう。
トランスジェンダーの権利に反対する右派運動が、子どもたちが性別違和に社会感染するのを防げとか、トランスジェンダーの女子と同じトイレを使ったりスポーツで競合させるなといった形で、シスジェンダーの白人少女たちの保護を念頭に一部の親たちに支持を広げていることは、こうした運動がシスネスと白人女性性の保護を掲げた白人至上主義の歴史的な結びつきの現代的な表現であることを示している。そういった指摘をすると同時に本書は、主に白人トランスジェンダー活動家らによる黒人フェミニズムの濫用やヘイトクライムや自殺によるトランスジェンダーの若者たちの死をスペクタクルとして消費するトランスネクロポリティクスへの批判も忘れない。
前述の「A Short History of Trans Misogyny」にも書かれているように、シスネス(およびトランスミソジニー)はトランスジェンダーの抑圧だけに関係する概念ではなく、植民地主義や白人至上主義、奴隷制やジェノサイドを正当化するために自然化された性別二元制とそれに伴う性役割規範や女性差別を動員するメカニズムであり、したがってシスネスはトランスジェンダー女性の包摂云々以前の話としてフェミニズムが標的とするべき対象。一部にそれ自体として興味深くはあるけど全体とどう繋がるかよく分からない論文もいくつかあったけど、トランスフェミニズムの新たな重要文献になりそう。