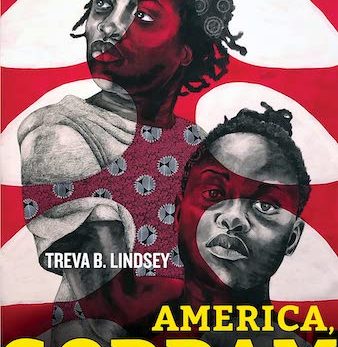Claudia Rowe著「Wards of the State: The Long Shadow of American Foster Care」
親元から引き離され里親や施設で育てられる子どもたちの多くが大人として生きていくための最低限の機会すら与えられず、生活のために犯罪に手を染めるようになったり成人するとともにホームレスになる現実を告発する本。著者はシアトル在住のジャーナリストで、わたしの身近なところで起きている、一部は聞いたこともあるケースが取り上げられている。
タイトルの「wards of the state」というのは政府の庇護下にある子どもという意味。なかには孤児となった子どもや親による育児放棄や虐待から救い出された子どももいるが、Dorothy Roberts著「Torn Apart: How the Child Welfare System Destroys Black Families—and How Abolition Can Build a Safer World」にもあるように、その多くは一家が貧しかったり親自身が必要なケアを受けることができないために十分に子どもの面倒を見ることができないために親元から引き離された子どもたち。政府が庇護するというのだから、当然そうした子どもたちは十分に面倒を見てもらう権利があるはずだし、少なくとも引き離された元の状況よりは良い状況に置かれていなければいけないはずだが、現実問題としてそうなってはいない。
里親制度の問題としてはよく里親による虐待が話題となるが、著者はセンセーショナルな報道は里親制度そのものによる弊害を軽視し、特定の加害者の存在だけにその問題を見出すことになってしまうと警告する。親から引き離されいくつもの里親をたらい回しにされ、そのたびに異なるルールを与えられ学校を転向させられたり、里親によって「この子はいらない、面倒見きれない」とアマゾンの商品のように政府に返品されたりといった経験を重ねる子どもたちは、とくにこれといった虐待行為がなくても里親制度を逃げ出そうとし、その結果犯罪に巻き込まれたり自ら関わっていくようになってしまう。
本書には実際にそうした経験をして大人になった人たちに多くの取材をしてかれらがどのようにしてまっとうに生きる機会を奪われていったのか語られるが、その中心となっているのは16歳で殺人犯として逮捕され19年の刑を受けたマリアン・アトキンスさんの事例。彼女は8歳で里親をはじめて経験し、いくつもの家庭を渡り歩いたあと、12歳で養子として受け入れられるも、やっぱりいらないと再び里親制度の元に返される。10代前半から彼女は家を出て大人を相手に売春行為をして生活費を稼ぎつつ、夜は1日中走っている電車の中で休む日々。16歳のときに彼女が殺害した相手は年上の男性で、彼女はレイプされそうになって自衛したと主張したけれど、検察は彼女が金銭目的に被害者を強盗殺人したと決めつけた。16歳を数週間過ぎていたために子どもとしては保護されずその瞬間彼女は大人として裁判にかけられ、検察は彼女が日常的に嘘をつき犯罪を重ねる危険人物だとして、長期刑によって彼女を数十年に渡って社会から遠ざけるべきだと主張した。政府が責任をもって育てるはずの子どもを、政府が育児放棄し、政府が公共の安全を口実に処罰したことになる。
現在23歳となりまだ十年以上の刑期が残されている彼女のケースはシアトルで性暴力や性的人身取引に取り組む人たちのあいだでは有名な話だけれど、著者は彼女が特殊なケースではなく、政府の庇護を受けるはずだったのに受けられず人生を奪われた多くの子どもたちのうちの一人だったことに気づく。ビル・ゲイツやジェフ・ベゾスを筆頭に数万人ものミリオネアやビリオネアが住んでいるこの裕福なシアトル地域で、貧困のせいで子どもを奪われる親たち、親から引き離されるだけでなく政府の庇護という約束を反故にされる子どもたちがこれだけいるのは、子どもたちにまともな機会を与えようという政治的意思の欠如にほかならない。アトキンスさんや彼女と同じような状況に置かれた人たちの減刑を求めるのはもちろんだけれど、それだけでは弊害を軽減するだけにしかならないのも確かであり、本書がシアトルの人たちのあいだで政治的な優先順位の再考につながることを願う。