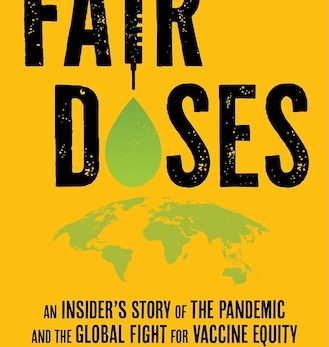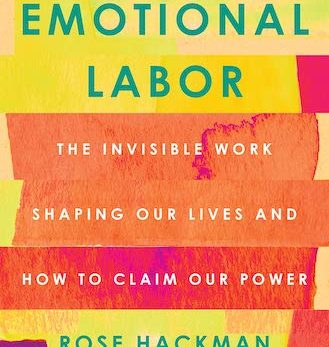Brian Barth著「Front Street: Resistance and Rebirth in the Tent Cities of Techlandia」
シリコンバレーのテック企業がもたらす貧富の差の爆発的な拡大やその他の問題を追っていたジャーナリストが、そのシリコンバレーで住居を追われホームレスとなって街のなかでテントを張ったり車中生活して生きている人たちに取材をするうちにかれらの人間性に触れ、「テックブームの弊害、犠牲者」的な紋切り型の自身の報道姿勢を反省しホームレス問題の解決について考え直す本。
著者はシリコンバレー各地でホームレスの人たちやかれらが形成するコミュニティを取材しているが、その中心にあるのはアップル社が50億ドル(当時はもう少し低いけれど現在のレートでは約8000億円)かけてクパチーノに建設した新社屋アップル・パークの近くにあるテント街。街の賑やかな場所や企業の施設が集まる場所に設置されたテント街はたいていすぐに警察によって排除されるものだけれど、アップルという大きすぎるそして世間の評判を気にする企業のそばに集まることで逆に排除されにくくする、というのは天才だと思うのだけれど、そこで暮らすホームレスの人たちを不幸な犠牲者としてのみ扱うのは間違っていると著者は指摘する。
19世紀から20世紀前半にかけてのアメリカでは、(白人の)ホームレスの人たちは仕事や家庭に縛られるのを嫌って仲間とともに自由に生きることを望んだ人だという認識が一般的だった。当時は住む家があっても大抵は小屋のようなもので今ほど便利でも快適でもなかったし、仕事をする気があれば学歴や人脈に頼らずともできる仕事がたくさんあり、そもそも入居にかかる費用もそれほどの負担ではなかった。20世紀中盤以降、精神病院からろくな支援もなしに放り出された人や戦争でトラウマを負った退役軍人たちがストリートに溢れ、貧富の差の拡大や住居不足により望まない形でホームレスになる人が増えたが、ホームレスの人たちはストリートにおけるコミュニティへの帰属心や自由への指向を完全に失ったわけではない。どんな犠牲を払ってでも住居に入居したいと思う人がいる一方で、窮屈なルールに縛られたり生活の全てを家賃を稼ぐための労働に駆られるくらいならホームレスのままでいるほうがマシだと、かれらを管理して自由を奪おうとするホームレス支援プログラムを拒絶する人も多い。わたし自身もよく見てきているけれど、「こうすれば住居に入居することができます」という支援プログラムに参加して努力しても裏切られ続けた結果、自分はそもそもそんなに住居がほしいわけじゃないし、と開き直る人もいる。
また、ストリートには共生的なコミュニティがあり、支援プログラムを受けてアパートに入居した人が孤独に苦しんでまたストリートに戻ってくるということも少なくない。実際、コロナウイルス・パンデミックの初期段階において、感染防止と業績が悪化したホテルの救済を兼ねてホームレスの人たちをホテルに収容し食事を届ける(かわりに、外出や他者の訪問を厳しく管理する)施策が各地で取られたが、その結果ホームレスの人たちのメンタルヘルスはストリートで生活していたときよりも悪化した。Gregg Colburn & Clayton Page Aldern著「Homelessness Is a Housing Problem: How Structural Factors Explain U.S. Patterns」のタイトルにもあるように、ホームレス問題はなによりもまず住居不足の問題なのだという主張は正しいし、ほかにどのような施策を取るにしても住居不足の解消は大前提となるのだけれど、それだけではない。
本書はホームレスの人たちの環境を改善させる取り組みとして、Kevin F. Adler & Donald W. Burnes著「When We Walk By: Forgotten Humanity, Broken Systems, and the Role We Can Each Play in Ending Homelessness in America」で紹介されているミラクル・メッセージズの活動を高く評価している。これはホームレスの人たちが過去に失った家族や友人たちとの関係性の回復を手助けすることを通してかれらが無理をすることなく立ち直ることができるよう導くもの。
まあわたしは公共政策に関わる人なので、基本的に住居政策・都市政策を中心に考えているし、実際に住居が不足していない地域ではどれだけ貧困や薬物依存の問題があってもホームレスとなる人は少ないというデータもあるので、ホームレス問題の解決にはそっちが主題だと思うのだけれど、自尊心の尊重や関係性の復活といった取り組みももちろん重要だと感じる。