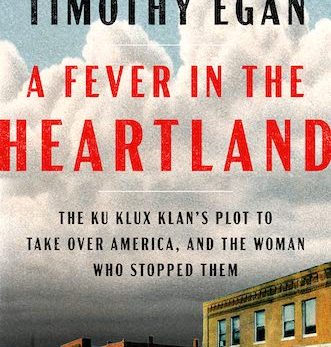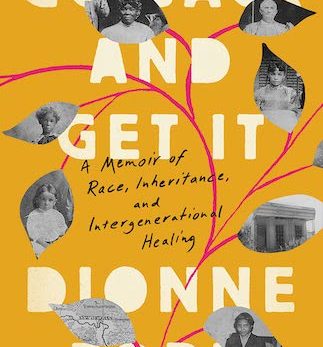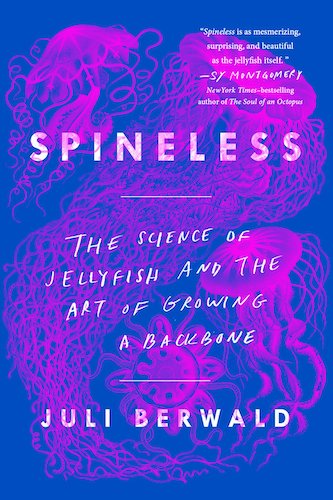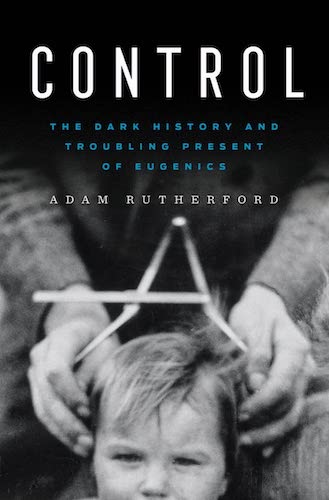
Adam Rutherford著「Control: The Dark History and Troubling Present of Eugenics」
優生学・優生思想の歴史と現在についてサイエンスライターの著者がコンパクトにまとめた本。序盤にコロナウイルス・パンデミックに触れ、医療リソースが限られるなかで障害のある患者らに対して勝手に「心肺停止状態になった場合、蘇生措置を行わない」と決められたことが言及されているので、そういう話が優生思想の現在として論じられるのかと思ったけど、実際にはそうではなくてがっかり。
本書の前半は優勢思想が20世紀の前半、どのようにして政治やビジネス、学界の有力者たちによって支持されてきたのか、そしてそれがナチスによるホロコーストという衝撃的な結末にほんの数十年のあいだに行き着いたことを受け、少なくとも公然と優勢主義を訴えることがタブーとなったかという歴史が、そして後半は近年の遺伝子技術の発達、とくにゲノムワイド関連解析(GWAS)研究やCRISPR技術による遺伝子編集の簡易化によりヒトの生殖細胞に対する遺伝子編集を防ぎきれない状況になっていることが説明される。
著者はもちろん優生主義には批判的なのだけれど、かれの批判の中心は生命倫理的なものでも社会的公正に基づいたものでもなく、「それって科学的に実現できないよ」というもの。たとえばナチスドイツが自閉症などを根絶しようと収容所で虐殺したり強制的な避妊手術などを行っても戦後のドイツにはほとんど影響がなかったことや、原理的には遺伝子によって説明できるはずの人の目の色ですら多数の遺伝子の相互作用が関わっていると思われいまだに解明されていないことなどが挙げられる。知能や運動能力などより複雑な形質について科学者が親に結果を保証できるようになるまではさらに時間がかかると思われるし、そもそも体外受精は母体への負担が大きくコストも高いので一般化は難しい。
まあ遺伝子技術の進歩による危機を煽るだけの声が聞かれるなか、そんなに簡単な話じゃないんだよという落ち着いた話があってもいいとは思うんだけれど、この本では優生学をそのもともとの意味、すなわち悪質な遺伝子を排除して人類の質を向上する考え方、という意味でしか扱っておらず、いまここで「価値のない命」として殺されつつある障害者やその他のたくさんの人たちの存在には目が向いていない。序盤に言及されたコロナの話は優生主義の話を始めるためのただのフリであって、最後まで読んでも議論がそこに戻って来ないのが残念だった。