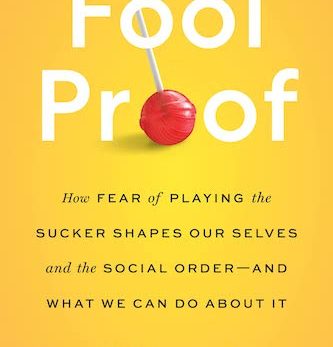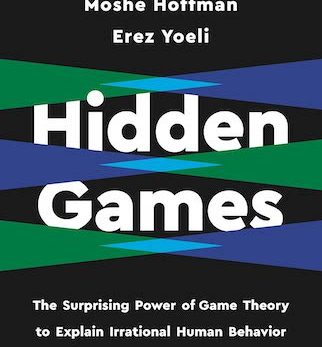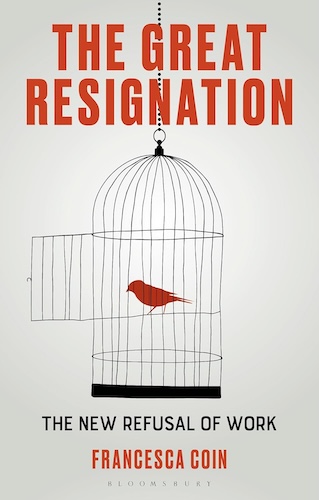
Francesca Coin著「The Great Resignation: The New Refusal of Work」
コロナウイルス・パンデミック後の経済回復のタイミングで労働力不足が深刻な問題となった欧米で2021年頃から話題となった「大退職時代(グレート・レジグネーション)」についての本。アメリカやイタリア、イギリスを中心に、どうして多くの労働者が職を放棄したのか問う。
そもそも労働者が特定の仕事を続けることがスタンダードとされたのは、戦後の欧米(や日本など一部の国)に特有の現象。大恐慌や世界大戦からの復興のため、そして冷戦下にあって労働者が社会主義革命を目指すことを阻止するため、政府や企業が労働者の生活の保護を掲げ、それと引き換えに労働者たちに企業に対する忠誠心を要求することで、20世紀中盤の欧米では離職率が低下し労働市場が安定した。もともとこうした社会契約は白人男性など一部の労働者にしか適用されていなかったが、1970年代からネオリベラリズムの進行により労働者の置かれた境遇はさらに悪化。企業の側から社会契約が反故にされていき、労働者は職の保証や企業内福利などの好条件を取り上げられ、ただ生きていくために職にしがみつく状況が続いた。
コロナウイルス・パンデミックが発生すると、企業の都合によって多くの人が職を追われ、また学校やケア施設の閉鎖などにより家庭内のケアを押し付けられた女性が一挙に離職した一方、救急医療や精肉産業・食料品店など「エッセンシャル・ワーク」と呼ばれた現場で働く労働者たちが、十分な個人防護具も与えられず、命を危険に晒して働くことを強いられた。経済的余裕のある人たちがステイホームしたために労働者不足に陥るなか、より多くの仕事を同じ時間でやれと言われ、コロナ感染が分かると面倒なことになるから検査は受けるな、多少病気気味でも休むな、親戚がコロナで亡くなっても葬式に行くな、と言われた労働者は少なくない。
家族に感染させり危険があるからと家に帰ることもできず職場とホテルの部屋を往復するだけの生活をずっと続けた看護師、職場で同僚がコロナに感染したことも知らされず狭い作業場に押し詰められた移民の精肉作業員、丸一日かけてなれないリモート授業の準備に必死になっているのに「子どもたちはコロナにかかっても重症になりにくいのだから」と親たちから学校再開を迫られ攻撃される教師、医療保険もなくすべて自己責任でアルゴリズムに従って食糧を配達する運転手ら、末端の労働者たちはいかに自分たちが人間として扱われていないのか、自分たちの命が軽く扱われているのかあらためて認識させた。また同時に、多数の人たちが家族や友人をコロナで亡くし、あるいは失いかける経験をしたことで、多くの人たちはあらためて自分が何のために生きているのか、自分の人生にとって大切なのは何なのか再確認した。
ワクチンが普及しパンデミック後の経済回復がはじまったとき、多くの労働者たちは「もとどおり」の職場に戻ることを拒否した。またパンデミックの最中は使命感を持ってエッセンシャル・ワークを続けていた人たちの多くも、自分たちの犠牲に一切報いることがなかった職に愛想を尽かせて離職していった。それが「大退職時代」の正体だと著者は言う。実際、退職者が多いのはパンデミックにおいて「エッセンシャル・ワーク」と呼ばれた業界であり、労働組合に守られるなどして比較的労働者の権利が守られている業界ではそれほど多くの退職者は生まれていない。労働者たちは仕事をすることを拒んでいるのではなく、企業によって一方的に破棄された社会契約に縛られ続けることを拒否している。ロバート・ライシュ元労働長官が大退職時代は「現代的なゼネラル・ストライキ」だと言うのはこういう意味だ。
失業保険や食費支援などの福祉制度があるから怠けて仕事をしない人がいるのだ、という保守派の意見はよく見るが、働いても豊かになれず、階層上昇の機会もなく、家族との暮らしを犠牲にさせられ、命すら危険に晒されるのに、雇用者側はなんら自分たちを守ろうとしないのであれば、それでも仕事をしろというのはまったく無茶な要求。女性の労働参加率は1970年代並みの低い水準がコロナ以来続いており、男女平等の観点からは問題が大きいが、ケアの社会的欠如が相変わらず続いているのに女性に職につけと言ってどうにかなる問題ではない。ネオリベラリズムの浸透移行ずるずる続いていた不公平な構図がパンデミックというきっかけにより限界に達した結果が大退職時代であり、これ以上低所得層を経済的に締め付けても人々がより苦しむだけで労働力回復には繋がらない。ケアの社会化と労働者の権利擁護を進めていくしかない。