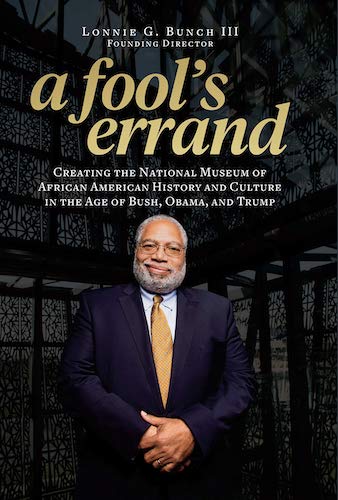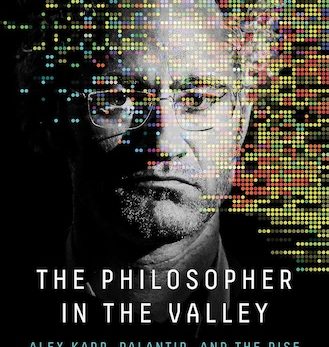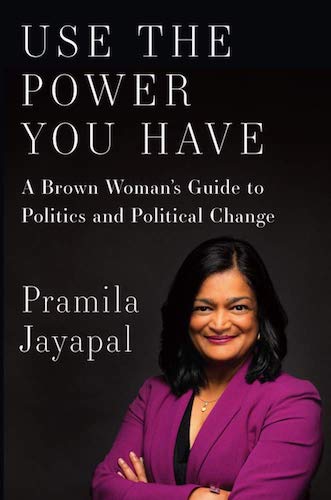Ugo Gentilini著「Timely Cash: Lessons From 2,500 Years of Giving People Money」
古代アテネから現代のコロナ救済金まで、国家や教会などから人々への現金や現物による経済支援の2500年の歴史とそれをめぐる言説を振り返る本。著者は世界銀行の上級エコノミスト。
ヨーロッパだけでなくアジアやアフリカなど世界中から集められた歴史的事例の情報量がすごすぎて読み終わるころには個別の話はほとんど忘れているのだけれど、国家や教会による現金や現物の支給(職の保障を含む)の歴史がそれこそ国家や教会の歴史と同じくらい長いこと、そしてそのあり方をめぐって同じような議論が繰り返されてきたことはイヤというほど理解できる。こうした制度の多くはもともと国家のために戦争に参加した結果負傷して働けなくなった元兵士や戦士した人たちの未亡人や子どもに対する保障としてはじまったが、次第に障害などそれ以外の理由で仕事ができなくなった人や親を失った孤児にも拡大していった。しかしそれが障害の有無などと関係なく生活に困窮し支援を必要としている人全般に広げられたとき、貧しくても頑張って仕事をしている人に失礼だとか、怠け者やフリーライダーを容認していては他の人たちも労働意欲を失ってしまうといった意見が広まり、受給資格にさまざまな条件が付けられたり厳しく審査されるようになる。
貧困や失業の存在についての考え方としては、主に本人の責任であるとする個人モデルと、主に社会的な要因によって生じるとする社会モデルが拮抗している。もっとも前者の考えを主張する人たちも、生まれつき重い障害があったり、出産・育児中の女性や幼い子どもなど、ほんとうに仕事をして収入を得ることが難しい人が存在していることは認識しており、だから受給を希望する人がほんとうに支援を受けるに値するのか厳しく審査しようとする。かつてはこうした主張はキリスト教的な労働倫理や財政規律を守るために展開されていたが、ニクソン政権以降、ダニエル・パトリック・モイネハンやチャールズ・マリーらによって「福祉は依存を生み出し、結果的に貧困を減らすのではなくむしろ黒人などのあいだに世代的な貧困を定着させてしまう」という論理が広められる。リベラル的な善意の政策が意図せざる負の結果をもたらすことを指摘するのはかれらのような保守論客のあいだでポピュラーな主張だが、この件についてはのちの研究によってほぼ否定されている。
本当に支援を必要としている人は救済すべきだが、そうでない人が制度を悪用することは絶対に認められない、という考え方からいま米国などの政府が行っているのは、ただ受給資格を厳しく審査するだけでなく、手続きを面倒にするなどしてより多くの取引コストを支払わせることで、本当に必要な人以外はそもそも受給を申請しない状況を生み出すことだ。著者はこれを、本当に泳げない人を選別するために浮き輪を求める人たちを全員一旦水中に放り出し、実際には泳げる人が自力で逃げたあとで溺死しかけている人をすくい上げようとすることに喩えているが、そんな選別が行われると分かっていれば本当に浮き輪が必要な人も申請を避けるようになる。実際、第二次トランプ政権になって実施が決まった貧困層向けの食料支援や医療支援の予算削減計画の詳細を見ると、直接受給資格を奪うのではなく、不正受給者ではないと証明するための手続きを面倒にすることで、本来受給資格がある人が申請を断念したり証明できない状況に追い込むことで結果的に受給者を減らそうとしているのが分かる。そうすることで予算を削減するとともに、「受給資格には一切手を付けていない、でも自分の政策により多くの人たちが福祉への依存を断ち切り経済的に自立することができた」と宣伝することができるというわけ。
著者は現金・現物支給の長い歴史と近年の研究を踏まえたうえで、福祉が貧困を生み出すのではなく貧困が福祉の必要性を生んでいることや、コロナウイルス・パンデミック初期に各国政府がものすごいスピードで受給資格を細かく問わない救済措置を実施しそれによって多くの人たちが一時的にではあれ貧困から救われたこと、パンデミックに限らず経済構造や社会制度の転換期に現金や現物の支給が人々の苦しみを軽減してきた確かな実績があることなどを説明したうえで、現金の支給によってすべてが解決するわけではないことも加えて訴える。たしかに個人の貧困はお金を与えれば解決するが、激しい貧富の差を生み出す社会構造があるならそれを是正しないことには社会的な貧困問題は解決しない。また、複雑化したさまざまな救済措置や受給資格の厳格化が膨大な非効率性と人々の不自由を生んでいることからリバタリアンの一部はあらゆる救済制度をベーシックインカムに一本化することを求めているが、そうした考え方にも著者は与さない。
大量に紹介されている歴史的な記述については、あ、これ、この5分の1くらいの例示でわたしは満足だったなと思うんだけれど、福祉や再分配をめぐる現代の議論にも通じる論争がそんな昔からあったというのはおもしろかったし、とはいえ「福祉は貧困層をさらに貧困にする」というモイネハン的ないやらしい理論や福祉受給資格のある人が実質的に受給できなくなるようにする制度の改悪など現代の保守派のやり口は歴史的な例と比べても特に悪どすぎることを再認識した。