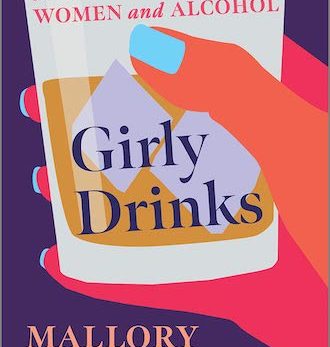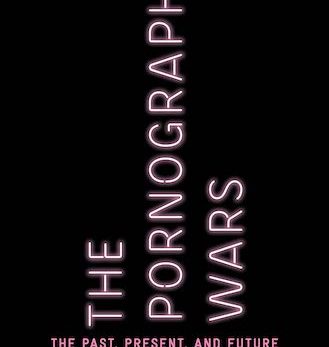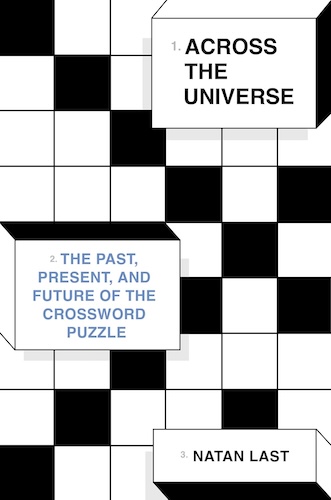
Natan Last著「Across the Universe: The Past, Present, and Future of the Crossword Puzzle」
ニューヨーカー誌などにクロスワードパズルを提供しているパズル作家の著者が、クロスワードパズルの歴史と未来について語る本。わたしは言語(とくに英語の文法、単語、用法など)オタクでワードゲームも好きだけどクロスワードパズルは守備範囲外なんだけど、本書の内容はとても興味深い。
コロナウイルス・パンデミックによるロックダウンをきっかけにワードルをはじめとするワードゲームに熱中する人が増えているけど、ワードゲームの王道といえばやはりクロスワードパズル。それぞれの言語に影響されてか各国で微妙にパズルのデザインのルールが異なるけれど、世界中の多くの国で楽しまれており、最も格調高いとされるクロスワードパズルを掲載しているニューヨーク・タイムズ紙など、もはや報道機関というよりはゲームのサブスクを売るゲーム会社に報道部門が付属しているみたいなビジネスモデルになりつつある(言い過ぎ)。
しかしクロスワードパズルはただ単に楽しい時間潰しの道具ではなく、その時代時代の主流社会がなにを一般的な物事や概念だと考え、それをどう捉えていたかを示す、歴史的資料でもある。クロスワードパズルの答えとなる単語は一般的によく知られた単語だとされているが、なにが「一般」でありなにが「特殊」であるかは人種や階級などに基づいて決められるし、その答えを導き出すための鍵にも主流社会の思想が反映される。たとえば白人男性の文学作品や音楽は一般用語としてパズルの答えになるいっぽう非白人や女性のそれをパズル作家が採用しようとしても編集者によって「一般的に知られていない、特殊すぎる」としてボツにされたりするし、非欧米文化に関連した言葉の鍵にカリカチュアライズされた間違った定義が使われたり、反植民地主義闘争が「野蛮人の暴動」として扱われたりもする。
そうした主流メディアのパズルに対して、なにが「一般的」とみなされるかを意図的にずらそうとして、自分たちが親しんでいるマイノリティ文化やサブカルチャーの用語をパズルに盛り込もうとする作家たちもいる。それに対して「パズルに政治を持ち込むな」という反発が起きるが、そもそもパズルが規定する「普通・一般」こそが政治的に生み出されたものだ。「クリーン・コール」(石炭を燃焼させたときに発生する有害物質を極力取り除く技術)という解に対してパズル作家が「環境に優しいと称する疑わしいエネルギー技術」という鍵を付けたのにニューヨーク・タイムズの編集者によって勝手に「環境に優しいエネルギー技術」と改竄された事件では、激しい批判が集まりパズルコーナーとしては異例の訂正記事が掲載された。
政治的なパズルという意味では、現職で民主党のビル・クリントンに共和党のボブ・ドールが挑んだ1996年の大統領選挙当日にニューヨーク・タイムズが掲載したクロスワードパズルはわたしもよく覚えている。CLINTONとBOB DOLEの文字数が同じことに気づいた作家が、7文字の横の枠にどちらの名前が入ってもいいようにそれぞれの文字の縦に答えが2つある鍵を付けた力作で、正答を一つに確定できないという意味ではパズルとして邪道だけどこんなおもしろいことができるんだ、と当時思った。
さてパーソナル・コンピュータが普及すると、パズルの製作にもコンピュータを利用することが増えてくる。最初はパズルを製作する際に利用できる、何文字で構成されており何番目にこの文字がある単語をリストアップする、といった単純なプログラムからはじまり、単語ごとにその一般性や意外性をスコア付けしてどの単語を選ぶべきか推奨するプログラムなども作られたが、その単語にあったウィットの効いた、そして新規性のある鍵を考え、難易度や面白さのバランスを取るのはやはり職人芸。LLMを採用した現代の人工知能ならパズルと鍵を自動生成すること自体は可能だけれど、少なくともいまのところこういった面ではAIはプロのパズル作家にはかなわない。
本書はほかにも文学や映画、音楽などのなかにクロスワードパズルが登場する例などをあげて文化的な影響についても論じられていて、ラップとクロスワードパズルの共通点の話などは特におもしろかった。わたしはNYTのゲームの中ではConnectionsが好きなんだけど、作家さんたちの苦労に思いを馳せつつ久しぶりにクロスワードパズルやろうかなあと思ったり。