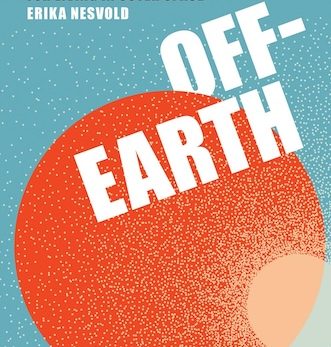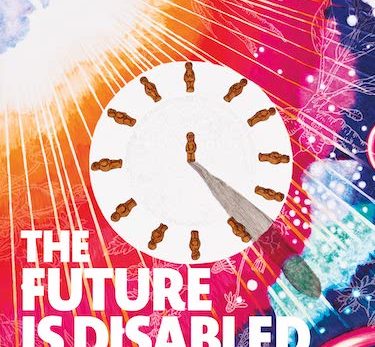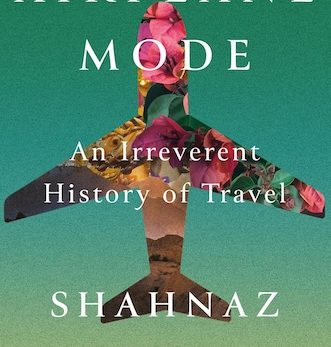Premilla Nadasen著「Care: The Highest Stage of Capitalism」
2023年に出版された、社会再生産フェミニズムの決定版。「資本主義の最高の段階」という副題はもちろんレーニンによる『資本主義の最高の段階としての帝国主義』(通称『帝国主義論』)に倣ったもので、著者自身「いやケアが最高の段階かどうか本当のところ分からないけど、とりあえず現時点ではそれで良くね?」と言っていてなにそれ!?と思ったけど、とりあえず目を引く副題ではあるし、内容はレーニン関係なくきっちりしてる。
2020年に世界的に拡大したコロナウイルス・パンデミックにより「ケアの危機」が叫ばれたが、ケアの危機は2020年にはじまった話ではない。第二波フェミニズムは家庭内におけるケア労働からの解放を求めるリベラル・フェミニズムと、ケアの経済的価値を認めるよう求める社会主義フェミニズムを生み出したが、多くの場合「ケアの危機」は家庭内の子どもや老人に対するケアを必要とする消費者側の視点から語られ、結論として「ケア労働者に対するより手厚い手当て」を求めたとしても、一貫としてその目的はケアの確保であり労働者の地位向上ではなかった。本書は著者自身も研究者・活動家として関わる家庭内労働者運動やその他の労働の現場からの視点を取り込み、「ケアの危機」に対する市場主義的ではない解決を目指す。
そもそもケアとは何なのか。女性が行う労働、女性的な労働、感情労働などさまざまな概念が重なり合うなか、その範囲は必ずしも定かではない。著者はケア労働という言葉の範囲が実際の労働の内容ではなくそれを行うとされる主体の性別や人種によって影響を受けることを指摘する。たとえば家庭内で仕事をする人がケア労働者なのかというと執事や庭師は多くの場合ケア労働者とはみなされない一方、掃除や洗濯をする人たちがケア労働者とみなされたり、看護師と医者、小学校教師と大学教授など、家庭以外の場所で働いている人たちもその性別や人種によってケア労働に従事しているとみなされる度合いが異なる。同じ子どもに対するケアでもStephanie Kiser著「Wanted: Toddler’s Personal Assistant」にも書かれていたように幼い子どもの世話は黒人やラティーノの女性に任されていても一定の年齢以上になると大卒の白人女性が求められるなど、労働そのもの以外の感情的・知的な要素を求められる傾向にも性別や人種による差がある。
社会再生産とは市場の外側にあり、しかし市場を成り立たせるために不可欠な家庭内の経済行為を指す。市場は人々を労働者や消費者として必要としているが、かれらが生活していくためには誰かがかれらの生活を支える労働をしなければいけない。20世紀中盤のアメリカでは労働組合によって守られた(白人)男性労働者が一家を養うのに十分な収入を得ることで女性に家庭内の社会再生産労働を任せる仕組みが出来上がったが、経済自由化と労働組合の弱体化によりこうした仕組みは崩壊した。黒人や移民らの家庭ではそもそもこうした仕組み自体が成立しないまま、男女がともに収入を得るための労働を行いつつ、主に女性が家庭内の社会再生産労働を行う形が続いていたが、20世紀末にはそれが白人中流家庭にまで広まっていく。必然的に家庭内ではケアが不足し、また女性の負担が重くなったことから、ケアの危機が叫ばれるようになった。しかしそこで採用されたのは、不足した社会再生産労働を移民女性やその他の立場の弱い女性たちに行わせるという市場的な対処であり、ケア不足は解消されるのではなくより立場の弱い女性や家庭に転嫁されることになった。
また、かつてのアメリカの資本主義は、男性が労働者として出勤してくるために女性の社会再生産労働を必要としていたが、派遣労働の一般化、さらにはアプリを使ったギグ・エコノミーの拡大により労働と雇用が切り離され、企業が決まった労働者を必要としなくなった。限りなく雇用が流動化した結果、企業は社会再生産に寄与し労働者の生活を支える必然性を完全に失った。ケア労働自体も(ケア・ドットコムを代表例として)ギグ・エコノミーに飲み込まれ市場化され、「ケアの危機」に対応するための政府の補助もケア市場に向けられる、この状況を著者は資本主義の最終形態であると指摘する。
社会再生産フェミニズムは家庭内労働者運動やその他のケア労働者たちの運動が雇用者との関係のなかで待遇改善を求める動きを支持しつつ、消費者の視点を優先したケアのさらなる市場化はケア不足のしわ寄せをさらに悪化ささえることになると考える。必要なのは、身近な家族や知り合いのケアをしたいと思う人たちへの十分な手当てと、身近な家族や知り合いがいなくても十分なケアを受けられるだけの保証であり、市場の論理のなかではそれは実現されない。ケア労働者が生活できるだけの報酬を得られるべきであることはもちろんだが、労働しなくても生活できるだけの保証は必要であり、市場を通した報酬の適正化だけではすべての人の生活を支えることはできない。社会生産フェミニズムの分析を丁寧に説明した重要な本。ていうかこれからますます重要さを増していきそう。