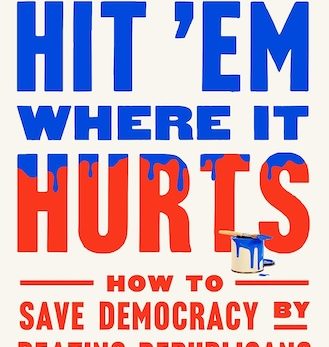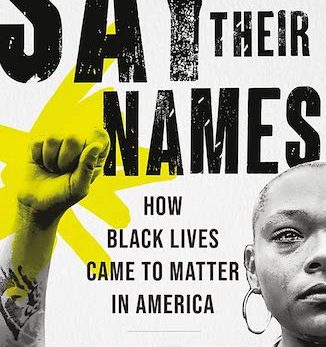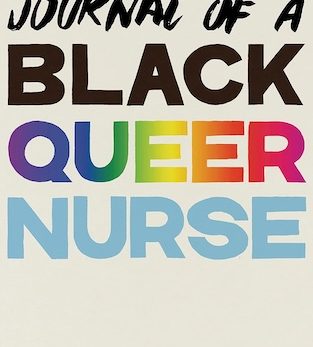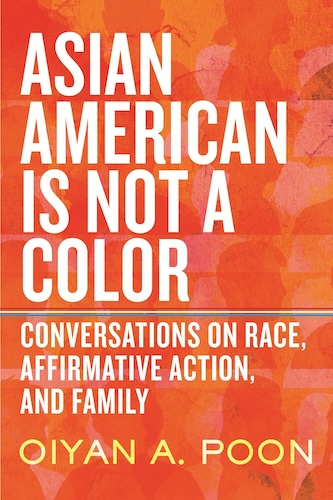
OiYan A. Poon著「Asian American Is Not a Color: Conversations on Race, Affirmative Action, and Family」
アジア系アメリカ人コミュニティとアファーマティヴ・アクションの研究者である著者が、3歳の娘から突きつけられた質問をきっかけに、彼女が成長したらアジア系アメリカ人アイデンティティについて理解できるようにと書いた本。
著者の娘が生まれたのは2015年。それから数年のうちにトランプが大統領に就任し移民排斥の動きが加速するとともに、相次ぐ警察による黒人たちの殺害に対抗してブラック・ライヴ¨・マターの運動も拡大。幼い娘を連れてデモに参加していた著者は、娘から「自分たちは黒人なのか、そうでないなら白人なのか」と問われる。どちらでもない、自分たちはアジア系アメリカ人なんだ、と答えるが、それに対して娘は「でも、でも…アジア系アメリカ人は色じゃないよ!」。
アメリカ政府はもともと白人にしか市民権を認めておらず、奴隷とされた黒人たちや国外勢力とされた先住民はアメリカ人とは認めていなかった。南北戦争の結果奴隷が解放され、憲法改正によりアメリカで生まれた黒人にも白人と同じく市民権が与えられることになったが、すぐにそれを実質的に無効化し黒人を二級市民に貶める政策が取られたことはよく知られている通り。いっぽう黒人奴隷に変わる安価な労働力として中国人らアジア系労働者たちが導入されるも、白人でも黒人でもないかれらは市民権を否定され、一時的な労働力として搾取されるいっぽう移住には厳しい制限がかけられた。当初中国人を対象としてたそうした制限はアジア人全体に拡大され、白人とも黒人とも異なる「オリエンタル」という人種が社会的に認識されるようになる。
「アジア系アメリカ人」というアイデンティティは、黒人公民権運動などに影響された文化も言語もさまざまなアジアのさまざまな民族にルーツがある人たちが自分たちの権利を訴えるために「オリエンタル」に替わる連帯のキーワードとして生み出した言葉。しかしアジア系アメリカ人の権利を求める運動は、アメリカの歴史において常に「白人至上主義のヒエラルキーのなかで白人と同等の地位を求める運動」と「白人至上主義のヒエラルキー自体の解体を目指す運動」に分かれてきた。たとえばアジア人の市民権が認められなかった時代には、自分は白人と同じ文化的な人間なので白人として市民権を与えられるべきだとか、インド人は元来コーカイソイドであり白人と起源が同じだという過去の人種科学を根拠に白人としての扱いを求めたりする人がいた一方で、黒人や先住民の運動と連帯し人種平等を推進する運動も存在してきた。
そうしたアジア系アメリカ人社会のなかの二つの流れの現在現れているのが、アファーマティヴ・アクションをめぐる議論。大学の入学審査、とくにアジア系アメリカ人学生が増加しているエリート大学のそれにおいて、黒人やラティーノを優遇するためのアファーマティヴ・アクションによってアジア系アメリカ人志願者が不当に点数を引かれている、という批判があり、一部のアジア系アメリカ人たちが訴えた最近の裁判では右傾化した最高裁によって入学審査において人種を考慮に入れることを禁じる判決が出た。また住んでいる地域による教育格差を解消するために設立される特別な公立学校の入学審査においても人種的多様性を確保するためにアジア系アメリカ人の子どもたちの割合が不当に制限されているとしてアジア系アメリカ人の親たちが抗議活動をすることが増えている。これらの運動では、黒人やラティーノの子どもたちを優遇するためにアジア系アメリカ人の子どもたちが割りを食っているとされ、入学審査において人種を考慮に入れるべきではないと主張している。
著者はアファーマティヴ・アクションに反対するアジア系アメリカ人の団体に取材を試みるも、それらの団体の多くは代表者や連絡方法も明らかではなく、誰がどういう理由で支持しているのかも見えにくい。のちに分かったのは、それらの団体は中国に家族や親戚がいる人たちが多く使っている中国のアプリWeChatを中心に活動しており、支持者の多くは1990年代以降にアメリカにはじめは留学生として移住してきた中国出身のエリートたちとその家族だったという事実。もちろん中国人以外にもアファーマティヴ・アクションに反対するアジア人はいるけれど、運動を起こしているのはほとんどその層であり、アファーマティヴ・アクションについて「優秀な中国人に対する差別だ」としてさまざまな間違った情報を拡散する中国語のエコーチャンバーが生まれてしまっている。
またアファーマティヴ・アクションのことは中国語では積極的補償行動(积极补偿行动)や平權措施(平权措施)と翻訳されるが、補償や平等の権利といった表現がアファーマティヴ・アクション反対運動に都合が悪いからか、中国語のソーシャルメディアではアファーマティヴ・アクションのことをあえて「AA」と表記し、カリフォルニア大学が中国人の入学を禁止しようとしている、といったデマや陰謀論とともに広められている。香港出身の中国人とタイ人の両親を持つ著者をふくめ、アメリカ生まれの移民二世・三世以降が知り得ない中国系アメリカ人のコミュニティがそこには存在する。
わたし自身、日本から来た新移民たちがアメリカで日本語メディアなどを通してカリフォルニア州などで「慰安婦」碑設置反対の運動を起こしたとき、そうしたコミュニティの存在すら知らなかった現地の日系人コミュニティが困惑したことを目にしてきたが、それと同じ状況が中国系アメリカ人コミュニティでも起きている様子。アファーマティヴ・アクションに反対するだけでなくブラック・ライヴズ・マター運動を批判し警察支持を訴えるなど、反黒人主義に与するような声が「アジア系アメリカ人」の主張として表に出てきていることと、わたしが知る進歩的なアジア系アメリカ人コミュニティとの温度差が気になっていたけれども、過去にアジア系アメリカ人たちが黒人や先住民らと連帯して権利獲得をしてきた歴史を知らずそうした連帯をぶち壊すような動きがどうしてアジア系アメリカ人のなかから出てきているのか、より深く理解できた気がする。
いっぽう、以前から存在するアジア系アメリカ人団体の多くは黒人やラティーノとの連帯と多様性の価値を重視しアファーマティヴ・アクションを支持しているが、かれらも入学審査におけるアファーマティヴ・アクションの実態を正しく理解していたわけではない。著者が取材したアファーマティヴ・アクション支持派の人たちの多くは、一面としてアジア系アメリカ人が不利となっていることを認めつつ、反黒人主義の歴史的な経緯や今も残るその影響を理由として、黒人やラティーノに対する優遇措置は平等の実現のために必要だと論じる。しかしBollinger判決以降、アメリカでは過去や現在の人種差別を是正するために特定の人種を入学審査において優遇するタイプのアファーマティヴ・アクションは明確に否定されており、「大学における多様性は白人を含め全ての学生にとって利益があるから」という理由しか認められていない。すなわちアファーマティヴ・アクションの目的は平等の実現ではなく「より良い学習環境」にとっくに置き換わっている。
アファーマティヴ・アクション支持派の誤解はそれだけではない。賛成派も反対派もともにアファーマティヴ・アクションはクォータ制や加点制などにより黒人やラティーノを優遇する仕組みになっていると誤解しているが、そうした方式はとっくの昔に禁止されており、長らく「志願者に対する個別の審査において、ほかのさまざまな要因とともに申請書のエッセイに書かれた人種差別の経験やそれに打ち勝ってきた経緯を評価対象とする」ものになっている。その点において、アジア系アメリカ人はアファーマティヴ・アクションから利益を得てきており、とくに親世代のあいだの貧困や低学歴の割合が多いカンボジア系、モン系、ラオス系の学生たちはテストの点数だけで審査されるよりも総合評価になることの利益が大きい。
また中国系など平均的に見て総合評価ではテストの点数だけで評価されるよりは不利になる学生たちも、あくまで他の要素が評価対象となるためにテストの点数の比重が下がるというだけであり、アジア系だからと特別に不利な扱いをされているわけではない。むしろエリート大学においては「卒業生の子息かどうか」「家族から大学への寄付があるかどうか」といった、白人富裕層に有利で歴史的にそれらの大学から排除されてきた非白人には不利な要素が審査に含まれている点がアジア系アメリカ人に不利に働いており、それはアファーマティヴ・アクションのせいではない。アジア系アメリカ人のなかには「アジア系だと知られると不利になる」という誤解に基づきあえてエッセイなどにおいて人種に触れない戦略を取るようなアドバイスが広がっているが、実際にはそれは得策ではない。いずれにせよ、最高裁判決により入学審査において人種を考慮に入れることが禁止されたが、それが今後中国系アメリカ人やその他のアジア系アメリカ人に有利にはたらくという保証はない。
さらに近年、トランプ大統領が「中国ウイルス」と呼んだコロナウイルス・パンデミックのなか、とくに女性やお年寄りをターゲットとしたアジア系アメリカ人に対するヘイト・クライム(憎悪犯罪)の増加が広く認識されるようになっている。しかしここにおいても既存のアジア系アメリカ人団体の多くが黒人やラティーノらの運動との連帯を表明するいっぽう、アジア系アメリカ人コミュニティの一部ではアジア系アメリカ人に対する憎悪犯罪は主に黒人によるものだとする事実に反するデマが広められ、ブラック・ライヴズ・マター運動によって警察予算が削減され黒人が調子に乗っている、といった反黒人主義的なヘイトスピーチも見られる。著者はアファーマティヴ・アクション賛成派が反対派のことをレイシストだと決めつけるのはよくない、少なくともかれらは白人至上主義者たちと異なりアジア人に対する差別の存在を認識しその撤廃を目指しているのだから、と言うけれども、アジア人差別批判が反黒人主義と直結するあたり、正直なところこの問題においては白人至上主義者たちが「白人に対する逆差別」を批判するのとあまり違いが感じられない。
黒人たちと連帯し公民権運動やブラック・ライヴズ・マター運動に参加してきたアメリカ生まれの二世・三世と中国語を母語とする新移民との世代格差・アメリカ社会への浸透格差があるという点では、アジア系アメリカ人の歴史を踏まえず中国や日本(やインドなど)の排他的ナショナリズムをそのまま持ち込んでいるように見える新移民のコミュニティを一方的に断罪するべきではないとは思うのだけれど、反黒人主義や白人至上主義と結びつき名誉白人の地位を求める、もう一つのアジア系アメリカ人の伝統を体現する動きの広がりに対しては強い危機感を感じている。それに対抗するためには、機会を奪われている黒人やラティーノの地位向上のためにアジア系アメリカ人は不利を受け入れるべきだという論理ではなく、アファーマティヴ・アクションが決してアジア系アメリカ人を不利にするものではなく、また連帯こそがアジア系アメリカ人自身の利益になるのだ、という議論が必要とされる。