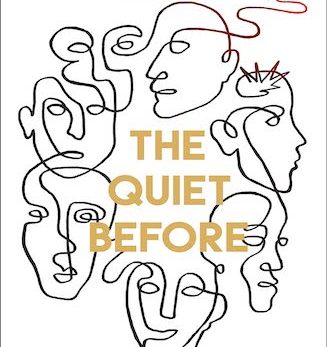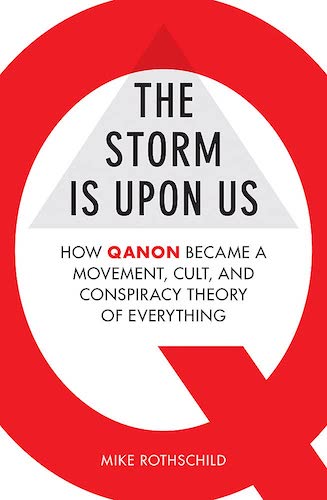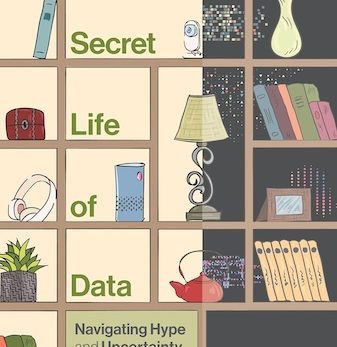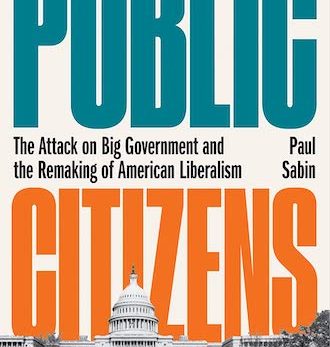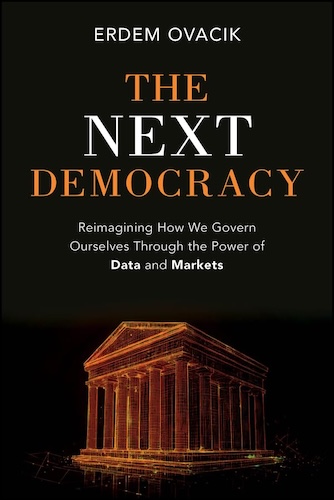
Erdem Ovacik著「The Next Democracy: Reimagining How We Govern Ourselves Through the Power of Data and Markets」
トルコ出身でデンマークでバイクシェア・サービスを起業した著者が、データと市場を利用した新たな民主主義「メリット・デモクラシー」を提唱する本。
データや市場、メリットなど、民主主義についての本にしては出てくる単語が胡散臭いものばかりなんだけど、土台となる著者の現状分析はかなりまとも。政府は民間の経済活動の前提となる法秩序・インフラストラクチャー・教育などの公共財を整備する役割を持つが、現状の民主主義では決定権を持つ政治家たちが次の選挙で勝つために短期的な支持を集めることばかりに必死になり、結果に対する責任を負わない。また、そのため適切な政策が取られず、その結果、民間企業は社会への影響を度外視して自らの短期的な利益だけを求めるようになってしまっている。
このように著者は政治と経済の両方で適切なインセンティヴが整備されず、気候変動をはじめとする環境への負荷や貧富の格差などの問題が悪化していることを指摘する。このうち経済の面については経済学において外部生と呼ばれる問題であり、正の外部性(社会の利益にはなるけれど行為者自身がその利益を十分に回収できない)や負の外部性(行為者自身の利益になるけれど社会に不利益を押し付けている)について、その外部性を内部化する(社会の利益になる行為に対して適切な報酬を出す、社会の不利益になる行為に適切な罰金や税金などをかける)という回答が既に提示されている。問題なのは、民間におけるインセンティヴを是正するためのこうした政策を推進するようなインセンティヴを、どのようにして政治家たちに持たせるか、という政治におけるインセンティヴ設計だ。
本書は民主主義のインセンティヴを是正する試みとして、最近ニューヨーク市長選挙で話題となった優先順位付投票制をはじめいくつかの選挙制度改革、台湾やアイルランドなどで特定の問題についての人々の意見をまとめるために行われた議論の仕組み、予算の一部について使い道を人々が決める制度などを紹介するが、それらが根本的に現行制度の内部の改革であり、政治に強い関心を持つ一部の人たちをのぞき多くの人にとっては政治に参加するだけのインセンティヴを提供していないと指摘する。それに対して著者が提唱するのは、すべての市民に政治参加トークンを分配してDAO(分散型自律組織)を通して政策を立案・改善する仕組み。政治参加トークンは売却はできないが第三者に委任することはでき、委任対象はいつでも任意で変更できる。
ただDAOを利用するだけなら直接民主主義の新しい形に過ぎず政治参加するだけのインセンティヴは生み出さないが、ある政策が実現した結果として社会的な利益が生まれた場合、その利益のごく一部をその政策の実現のためにトークンを出資した人たちに分配する制度を著者は提案する。これは予測市場の一種であり、予測が当たったら配当を受け取るのではなく、政策が実現して社会に利益があったときに配当が受けられるという仕組み。予測市場は人々が単に個人的な予測を持ち寄るのではなく、結果について何らかの知識や見識を持つ人が自らの見解を開示するようなインセンティヴを設けることで、個々の意見を平均したよりも高度な予測を可能にしているが、著者が提案する制度も同様に、専門的な知識を持つ人がその知識をトークンの出資という形で明らかにすることを期待している。
もちろん特定の政策分野を専門としていない大多数の一般人にとっては、どの政策を応援すればいいか分からないし、あらゆる分野で大量に生まれてくる政策案に目を通し理解することすら難しい。そこで登場するのが新たな政治インフルエンサーたちで、かれらの意見を参考にして出資先を決めてもいいし、かれらにトークンの運用を委任してもいい。これは現制度における政治家への投票と似ているが、運用結果によって出資者に配られる配当に違いが生じてくるとともに、運用実績がデータとして残されるので、結果を出せない政治インフルエンサーは淘汰されていくと著者。
著者が提唱するこうした制度の実現には、ある政策が社会にどれだけの利益あるいは損失を生んだか正確に計測できることが前提となる。だからビッグデータの収集と洗練された統計分析が重要となるのだけれど、どう考えてもそれがうまくいくようには思えない。政府の統計資料は複雑な現実を地域や年度などで比較できるような数字に押し込むため、どうしても恣意的な判断が介在するものになってしまうし、政権の意思によって定義やデータ収集方法が政治的な理由で歪められることもある。著者が主張する制度の導入のためには政府がさらに多くのデータを収集・分析することを必要としているが、そこに巨額の配当金の分配という目的が追加されたら、さらに恣意的なものになりそう。少なくとも公平で客観的な数字であると人々が納得できるとは思えない。
そもそも、個々の政策の結果をそこまできちんと検証することができ、その分析を世間が公正であると受け入れるのであれば、現状の民主主義がここまでおかしなことにはなってない。陰謀論の拡散による広告収入や大手献金を通した政治的影響力など、政治の分野でインセンティヴがぶっ壊れているのはそれらを直接なんとかするしかなくて、政策実現による配当金ごときでは対抗できそうにない。あと著者は、データを使って政策を改善する方法としてランダム化された政策実験とそれを通したアジャイルな政策変更も訴えているけれども、ウェブサイトのボタンの色や大きさを変えて反応の増減を検証するみたいなノリで教育や福祉や医療の現場を混乱させるのはやめてほしい。いまの社会においてデータが十分に政策決定に利用されていないというのはその通りだけど、そう簡単にできない理由はちゃんとあるんだよ分かれ。
ところでこんなこと書いてしまっていいのか分からないけど、データと市場を使って民主主義を更新することを主張するこの本のオチ、なんとジョン・レノンの「イマジン」の歌詞で終わってたりする。いやレノンの夢は否定しないけど、それで本を終わらせるってめっちゃ恥ずくない?いつかわたしもそれに加わって世界が一つになるの?わたしの読書史上もっとも唖然としたオチの一つだった。