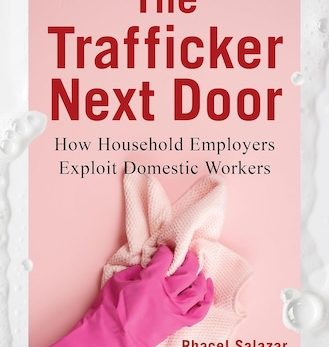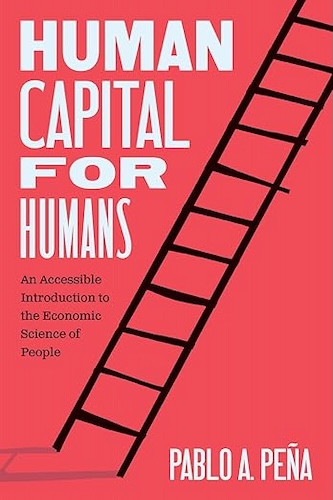
Pablo A. Peña著「Human Capital for Humans: An Accessible Introduction to the Economic Science of People」
新古典派経済学の牙城として有名なシカゴ大学経済学部で教える著者が、シカゴ大学経済学部の巨匠の一人ゲリー・ベッカーの40年にわたる研究の展開をとおして「人的資本」について解説する本。
ベッカーといえば犯罪や結婚、差別などそれまであまり経済学的な分析の対象とされてこなかった分野に経済学を適用したことで知られ、人的資本の研究を広めた一人でもある。人的資本とは土地や工場などとともに富を生み出すための資本の一つで、労働力やその生産性を高めるための教育・訓練・技能などが含まれる。それらに投資することで生産性が向上し資本としての価値が高まるが、人的資本は個々の労働者に付属しており切り離せないため、売買したり融資を受ける際の担保にしたりできる不動産や設備などとは異なるインセンティヴが働く。また、子どもの生産性を高めることが将来よりよい暮らしをさせるために必要だと考える親のインセンティヴと、労働者本人による自己投資のインセンティヴ、雇用した労働者を訓練したり経験を積まさせてもその個人に退職されると投資が回収できなくなる雇用者のインセンティヴはそれぞれ異なる。
ベッカーの過去の著作や論文、講演をベースにしているだけあり、現代の視点からみると当たり前なことが多く書かれているけれど、それを何十年もかけて展開してきたベッカーはすごい。しかし同時に、こんなことまでインセンティヴや合理選択で説明してしまうのか、という不気味さは拭えない。投資をするにも原資が平等ではないので自己投資していないように見える人はサボっているわけではない、なんらかの対処は必要と著者はフォローするけれど、たとえば学生たちがインターンシップと称して無償労働を強いられるのは双方のインセンティヴのバランスを取ったうえでの最適解だとしたうえで、貧しくてインターンシップのあいだの生活ができない人には公的な補助金を出すべきだと言われても、実際そんな補助金が出る動きは見えないし、不平等がさらなる不平等を生み出すことを追認してしまうように思う。
まあこれは著者のせいではなくて、ベッカーおよびシカゴ学派や合理選択理論、法と経済学運動などに共通の問題で、不審感を抱きつつもそのローカルな有用性は認めざるをえない、的な。ベッカー的な人的資本理解をベースとしたまま、シカゴ学派とは異なるアプローチからの社会政策を主張することはできなくないはず。