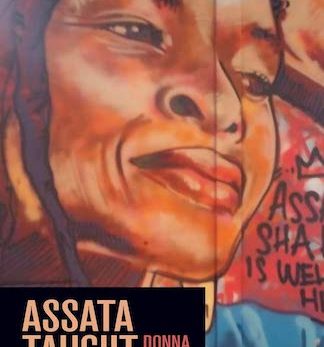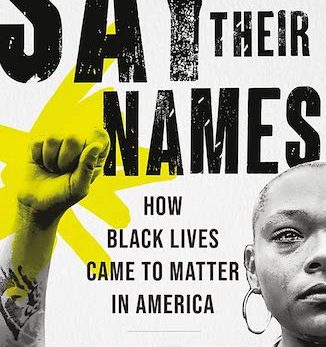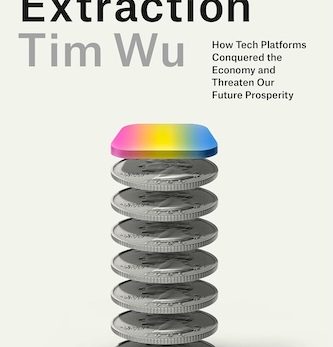Mischa Honeck著「No Country for Old Age: America’s War on Aging from Valley Forge to Silicon Valley」
子どもを未熟な存在として見下す一方、若さを過剰にありがたがり、若さに固執するアメリカ社会のあり方を、建国時から現在までの歴史をたどりつつ分析する本。サブタイトルに「バレーフォージからシリコンバレーまで」とあるように、独立戦争の宿営地だったバレーフォージの時代から、老いを否定し永遠の命を目指すシリコンバレーのヴェンチャーやトランスヒューマニズム運動までカバーしている。
世界各地に不老不死にまつわる神話や伝承、そしてそれを求めた権力者の歴史が残っているように、若さを追い求めるのはなにもアメリカ社会だけではない。しかし老いに対する極端な隠避感とタブーが広まっているのは、そして文化を通してそれを世界に広めつつあるのは、アメリカをほかにおいてない。アメリカは建国時点で自らを老いたヨーロッパと対比させて若くエネルギーと可能性に満ちた存在という自己像を描いてきたし、アメリカ議会で活躍した議員たちも若さを武器に「老害」と対決する姿勢によって支持を集めてきた。
「若さ」の称賛と「老い」への恐れはしかし、全ての人に平等に適用されることはない。たとえば女性にとっての「若さ」が男性にとってのそれとは異なる価値を与えられ厳しい評価の対象となったのはもちろん、黒人の「若さ」や「老い」は奴隷としての有用さ、しいては金銭的価値の基準にもなった。いずれも「若者」ではなく「未熟な子ども」と「役に立たない老害」のどちらかとして扱われ、「若者」は白人男性だけに許された特権的な立場だった。ヨーロッパを成熟の基準としてアメリカは若者、その他は未熟な子どもだとする論理は外交にも持ち込まれ、第二次世界大戦後に議会で証言したマッカーサーが、ドイツは成熟した国だが、日本はまだ12歳の男の子のようなものなのでアメリカによる躾や教育が可能であると発言したのも有名な話。
本書は政治や外交とともに公衆衛生行政やポップカルチャーの歴史を紐解き、「若さ」と「老い」をめぐるアメリカ社会の偏執性を明らかにするとともに、その現代的な展開として、「老い」を疾患だとして技術的に不老を実現しようとするシリコンバレーのヴェンチャーや、機械への記憶の移植や身体のパーツの置き換えによってそれを実現しようとするトランスヒューマニズムの思想にも触れる。テック富豪たちがかつての王侯貴族がそうしたように成功する見込みの低い不老の技術に大金を注ぎ込む一方で、世界の大部分において貧困や紛争、防げるはず・治療できるはずの感染症で多数の命が失われ、それが気候変動によってますます悪化しつつあるのだけれど。