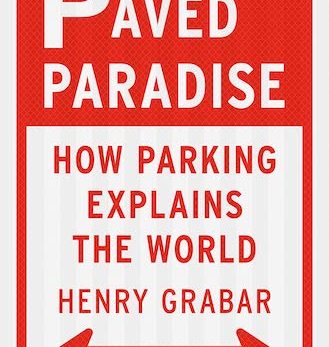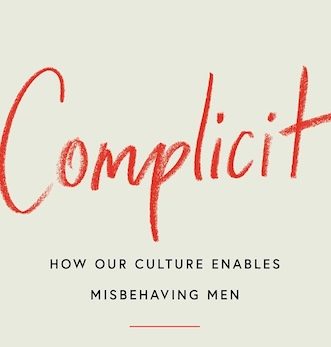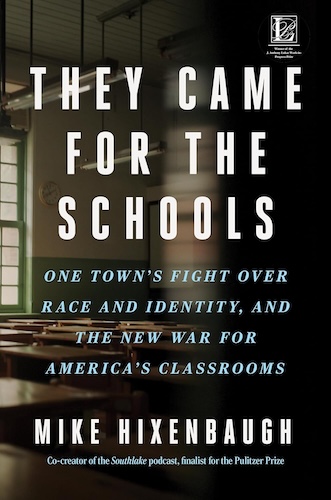
Michael Hixenbaugh著「They Came for the Schools: One Town’s Fight over Race and Identity, and the New War for America’s Classrooms」
現在アメリカに広がっている、公教育における人種やジェンダーの扱いをめぐる騒動の震源地の一つであるテキサス州ダラスの郊外サウスレイク市で何が起きたか、自身もテキサス州ヒューストンの郊外に住んでいたベテランジャーナリストが細かく解説する本。
テキサス州サウスレイクは裕福な郊外の街で、市内の公立学校は全国でもトップランクの優良校として知られる。一般のプロフェッショナルや富裕層だけでなく、ダラス・カウボーイズの元フットボール選手たちも多く家を構え、治安も良好。人口の7割近くが白人だが、近年アジア人の住民が増えてきている。多くの人たちは子どもが安全に学校に通い良い教育を受けられることを期待してこの市に引っ越してくるが、そのうち黒人の住民たちはその安全や良い学校と引き換えにカジュアルなレイシズムに頻繁に晒されることになる。
サウスレイクにおけるレイシズムが全国の注目を集めたのは、2018年に市内の高校に通う白人生徒たちがソーシャルメディアで公開した、笑いながら黒人に対する差別用語を連呼する動画が炎上したことがきっかけ。それを契機にそれまで学校区によって無視されてきた多数のレイシズムの訴えが取り上げられ、事態を重く見た学校区理事会は多様性と平等を実現するためのプランの策定をはじめる。理事会がその作業を進めているうちにコロナウイルス・パンデミックが起き学校は一時閉鎖、そしてミネアポリス市警察によるジョージ・フロイド氏の殺害をきっかけに全国にブラック・ライヴズ・マターのデモが広がる。当初は大企業や保守政治家もブラック・ライヴズ・マター運動への支持を表明していたものの、右派メディアによる攻撃などもありすぐに運動はアンチファによる暴力と結び付けられる。このころ著者が住む街でも、それまで地域の平和な話題がやり取りされていたフェイスブックのグループで突然「アンチファが銃を持ってこの街にやってくる、みんな銃を手にとって応戦しよう」と呼びかけるコメントが掲載されるなど、地域のムードが一変する。
こうしたムードの変化に寄与したのは、2020年に「批判的人種理論は連邦政府の全ての機関に浸透している」として、それまでほとんどの人が知らなかった、そして大学の法学や社会学の授業でなければ見聞きすることがなかった批判的人種理論という用語を、ブラック・ライヴズ・マター運動を目の当たりにし恐怖を感じた白人たちの被害意識に訴えるかたちで流用した保守活動家クリストファー・ルフォーと、かれを頻繁に番組に呼びセンセーショナルに取り上げたFOX Newsホストのタッカー・カールソンだった。サウスレイク学校区理事会が数年かけて策定した多様性と平等のためのプランを議題とすると、とくに議論を呼ぶことなく承認されるだろうという思惑と反対に、このプランの内容を吟味することもなく批判的人種理論の奨励だとか、白人の子どもに対する攻撃だと訴える親や親ですらない地域の住民たちが理事会に乗り込み、反対運動を繰り広げる。それでも当初は賛成する親のほうが多かったのだけれど、反対派のなかには反妊娠中絶の運動で有名な法律家などもおり、右派メディアに取り上げられたりして反対運動はさらに拡大、プラン策定に関わった理事たちをアンチファであり反米主義者だと攻撃した。その理事たちはもちろんアンチファではなく、地域のほとんどの大人と同じくごく普通の保守派の共和党員だったし、プランの内容も非白人の教員を増やすことや人種差別的ないじめの対処など大した内容ではなかったが、そうした事実には見向きもされなかった。
そうした状況が続くなか、プラン反対派の親たちは政治組織を設立、次の選挙で改選を迎えた現職理事を追い落とすだけでなく、市長選などその他の選挙にも影響力を及ぼす。何度かの選挙と、理不尽な攻撃にさらされることを嫌った理事の辞任などを経て学校区理事会を掌握した反対派は、プランを廃止するだけでなく、学校の図書館から人種問題に関する本を撤去し、また人種差別について取り上げる教師を解雇しはじめる。そうした動きが奴隷制やホロコーストについて「一方的な見解を押し付けるのではなくさまざまな意見を取り上げるべきだ」とするアプローチが批判を浴びて失速すると、ルフォーが推奨するとおり標的を「批判的人種理論」から「ジェンダー理論」に変更し、同性愛やトランスジェンダーに肯定的な本、それらに少しでも触れる本を「ポルノ・わいせつ物」だとして撤去するとともに、LGBTの生徒たちに対するサポートやいじめ対策を禁止、それに抵抗する司書や教師たちを「子どもをグルーミングする児童性愛者」として攻撃した。こうした動きに対して人種差別に反対しLGBTの子どもたちを守ろうとする親たちも政治組織を作り、対抗しはじめるが、サウスレイク市ではまだ成果を出すことはできていない。しかし右派による公教育へのデマだらけの攻撃に反発する親や住民の運動は全国的にも広がりつつある。
本書はLaura Pappano著「School Moms: Parent Activism, Partisan Politics, and the Battle for Public Education」が描いている全国に広がる公教育への理不尽な攻撃をその震源地の一つに注目して時系列を追って紹介しており、パニックが起きると地域のムードがこんなに短い期間に変わってしまうのか、という恐ろしさをより感じた。また著者は学校への攻撃に参加している親たちが、学校で好成績をおさめて表彰されている生徒たちのあいだにアジア系の名前が増えていることに不満をもらしていることも指摘しており、裕福な白人の居住地域にテキサスでさかんなテクノロジー企業で働くアジア系アメリカ人の家族が増えていることが白人たちの不安の背後にあることも示唆しており、アジア系住民たちがこれにどう関わっていくのか今後が気になる。