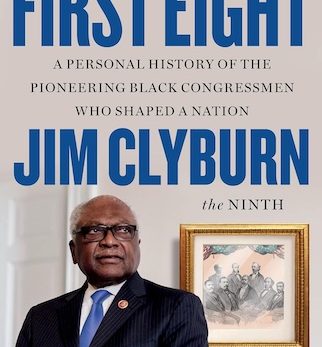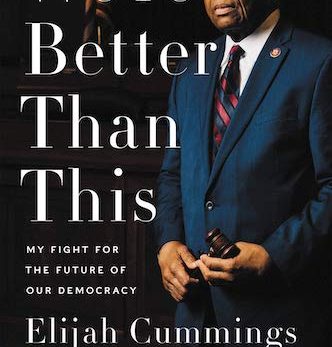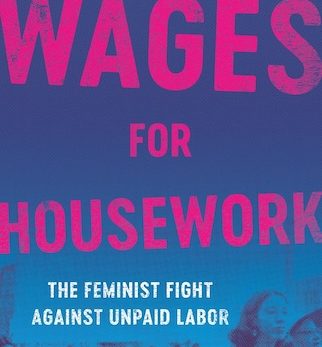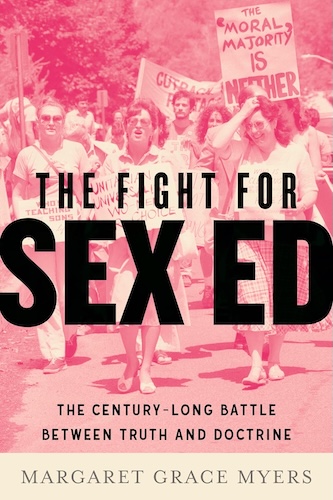
Margaret Grace Myers著「The Fight for Sex Ed: The Century-Long Battle Between Truth and Doctrine」
19世紀末から現在までの性教育をめぐる100年を超える論争の歴史についての本。時代を追って細かくどういう議論があったか説明されるのだけれど、まあアホみたいに同じことの繰り返しで嫌になる。
性教育をめぐっては、望まない妊娠や性感染症を防ぐための公衆衛生からの視点と、性道徳をどう教えるか、性にまつわる価値観をどう伝えるかという宗教的な視点が衝突してきた。19世紀末から各地で起きた性感染症の流行や「処女相手なら安全だ」さらには「処女とセックスすれば性病が治る」といったデマに起因する幼い子どもに対する性虐待の頻発などを受け性教育の必要性は認識されつつあったが、それが国家レベルで注目されたのは二度の世界大戦がきっかけ。ヨーロッパやアジア・太平洋に派遣された米兵が派兵先で女性を襲ったり買春したりしたことから性感染症が蔓延し、継戦能力に支障が出るほどになったことから米国政府は若い兵士に対する規律を強化し結婚している配偶者以外とのセックスを禁止する(前線に配偶者を連れてきている人はいないので実質的に全面禁止)と同時に、本来ならば必要ないはずのコンドームを配布するなど一見矛盾した対策を取るようになる。そうした政府や軍の啓蒙活動のなかで現地の女性や性労働者たちが道徳的に劣った存在であるというだけでなく、病原体そのものであるかのように扱われたが、それはまた別の話。
戦後、平時からの性教育の必要性が受け入れられ、一部の地域で公教育にもそれが取り入れられる。しかし当初から婚外交渉を道徳の面から否定する禁欲教育を行うべきだとする保守勢力によって性についての正しい知識の普及を目指す性教育は攻撃され、ジョン・バーチ・ソサエティ(Matthew Dallek著「Birchers: How the John Birch Society Radicalized the American Right」参照)など極右・白人至上主義勢力によって性教育とその推進者たちに関するデマが広められた。たとえば「性教育が行われる学校では図工の時間に性器を見て粘土で再現する授業が行われている」みたいな荒唐無稽なデマは、その後何十年にもわたって極右勢力のなかで繰り返し宣伝されることになる。
性教育を批判する政治勢力は、性教育はフリーセックスや同性愛など変態的なセクシュアリティを子どもたちに押し付けていると批判したが、実際にカリキュラムを調査した研究は性教育はそれが行われた時代においてごく一般的な性的な価値観を反映してきたことを明らかにしている。たとえば歴史のほとんどにおいて多くのカリキュラムは性的な欲望や快感について一切触れていなかったし、結婚した異性のあいだで行われるものだという前提から踏み出すようなものではなかった。また性については家庭で教えるべきだと考える親たちへの配慮として、子どもが性教育の授業を受けるかどうかは親が決められる制度が一貫して採用されてきたが、性教育反対派がそれで満足することはない。
性教育と禁欲教育のどちらが効果的なのか、という話になるが、ここで重要なのはなにが性教育の目的だとして検証されるべきなのかという問題。性教育と禁欲教育はともに生徒たちの性行動を抑制する効果はないか、あったとしてもごく短期的だとされるが、きちんとした性教育はコンドームを使う確率を上昇させ、望まない妊娠や性感染症を抑止する効果は確認されている。いっぽう禁欲教育は、いざセックスをするとなった時にコンドームを使う確率を減らし、また罪悪感を抱かせて秘密を生んでしまうほか、ペニスとヴァギナの接触がなければセックスではないので安全だと考えてより危険な行為に及んでしまう生徒を生み出す。しかし性教育反対派は、性教育には性行動を減らす効果はない、という部分だけ取り上げ、既に失敗が確定している性教育より、より新しく成功する可能性のある禁欲教育を試してみるべきだ、と、何十年ものあいだずっと主張してきた。
禁欲教育や、禁欲を主軸としつつ一応コンドームなどについての教える「禁欲プラス」の教育は、クリントン・ブッシュ両政権で政策に取り入れられ(ビル・クリントンはまず自分自身が率先して性教育を受けろよと思うけど)た。それに対してリベラルな州では従来の性教育をさらに発展させた「総合的性教育」が支持を集める。これは妊娠や性感染症のメカニズムやその予防についてだけでなく、ドメスティック・バイオレンスや性暴力、性的合意、性的トラウマ、性的欲求、性的指向や性自認といった性に関係するテーマについて広範に教えるもので、民主党が議会と知事の座を独占している州のいくつかで正式に採用されている。わたしの住むワシントン州でも2020年に総合的性教育の実施を定めた法律が成立した(というかわたしも推進に関わった)が、反対派によってこの法律を施行すべきかどうか住民投票にかけられ、多数派の支持により実施されることになった。これにより、ワシントン州は総合的性教育の実施を住民投票によって実現したはじめての州となった。
歴史は繰り返すというけれど、まあこんなに短いサイクルでよく何度も何度も繰り返すものだと思うほど、性教育をめぐる議論はほぼ同じパターンで100年以上も続いている。そしてここ数年、性教育そのものに対する攻撃とともに、学校で性的指向や性自認について話題にすることや、それらに触れた本を図書館に置くことまでもが叩かれるようになり、州によって受けられる性教育の内容の格差がさらに広がっている。冷静に歴史を追う記述を続けていた著者は最後の最後でこうした現在進行中の攻撃に対して怒りをぶちまけるが、強く頷いてしまった。