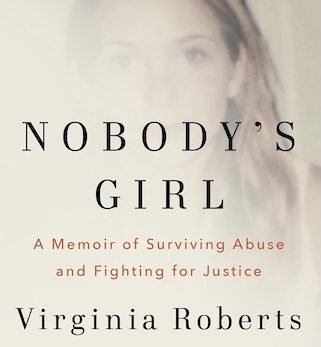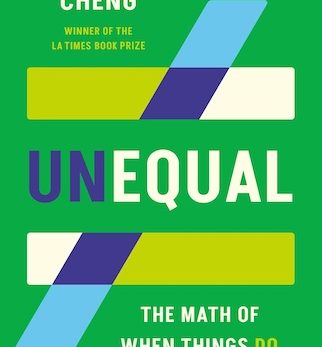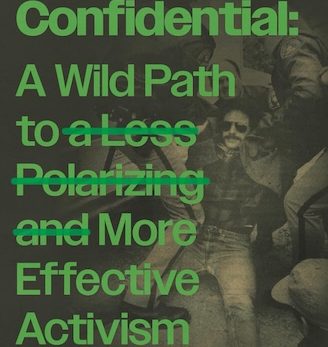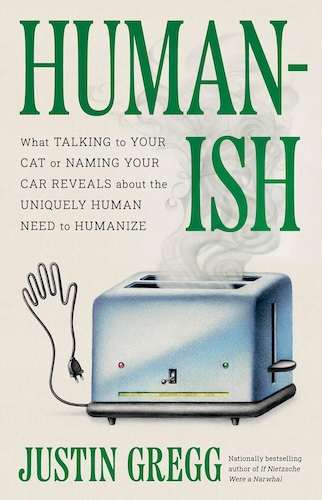
Justin Gregg著「Humanish: What Talking to Your Cat or Naming Your Car Reveals About the Uniquely Human Need to Humanize」
人間が人間でないものに人間的な認知を見出し、人間であるかのように扱う「擬人化」(anthropomorphism)についての本。著者は動物の行動と認知の研究者で、動物と人間の認知の違いについて書かれた前著「If Nietzsche Were a Narwhal: What Animal Intelligence Reveals About Human Stupidity」はイッカクと角を生やしたニーチェが角を交わしているシュールな表紙が印象的だった。
本書の最初に触れられている、去勢手術で睾丸を摘出されたオスの犬が「寂しそうにしている」と感じた飼い主が代わりに入れる人口睾丸を開発して起業した話(ぜったいそいつ本人が抱いている男性性の不安を投影してるだろそれ)にはじまり、人間ではない動物に人間と同じような認知や感情、思考を見出すエピソードは数多い。しかし擬人化の対象となるのは人間のそれと同じかどうかは別として認知や感情を持つとされる動物に限らず、ぬいぐるみや石、「地球」や「大自然」、神様や人工知能(AI)にまで及ぶ。本書は擬人化が生じた進化心理学的な背景やその発動条件、文化的な差異、動物倫理や環境倫理における効用と危険について論じる。
さらに本書は、擬人化の反対側にある「反擬人主義」(本書では単純に「dehumanization」と書かれているけれど、Susana Monsó著「Playing Possum: How Animals Understand Death」ではanthropectomyという用語が紹介されている)についても取り上げる。動物が感じる痛みや恐怖を人間のそれとはかけ離れた取るにたらないものとして扱う考え方は、動物研究の進歩とともに否定され、動物倫理が活発に論じられる背景ともなっている。動物の感情や認知を過小評価する考えは、植民地主義や人種差別を背景として動物だけでなく「劣った人類」とされた人種的・民族的マイノリティに対しても適用され、これまで多くの人権侵害を引き起こす口実となってきただけでなく、Anushay Hossain著「The Pain Gap: How Sexism and Racism in Healthcare Kill Women」にもあるように現在でも無意識の偏見として女性や黒人らが医療などにおいて受ける対応に影響している。
擬人化は科学的事実に基づかない思い込みや迷信としてバカにされがちだが、それより警戒すべきなのは人間や動物に対する侵害を正当化する反擬人主義だと著者はいう。そのうえで、無生物に対する擬人化は多くの場合それが擬人化であることを本人が理解したうえで心の支えや遊び、レトリックとして行っていることが多くそれほど問題ではないが、AIは感情や思考を持つ人格のように演じることができるので心理的に依存したり影響を受けすぎないために擬人化を行っていることを常に認識しておくことが必要だとか、人間のそれとは異なるけれども感情や思考、認知を持つ生物に対しては擬人化および反擬人主義の行き過ぎによって加害しないために(たとえば些細な例だけれど犬に人口睾丸を入れることに飼い主の自己満足以外の効用はなく、不要な医療であり加害行為)生物学の研究を参照すべきだというような、しごくまっとうな主張をしている。角を生やしたニーチェに続いて今回はトースターが手を振っている(ように見える)表紙も良い。