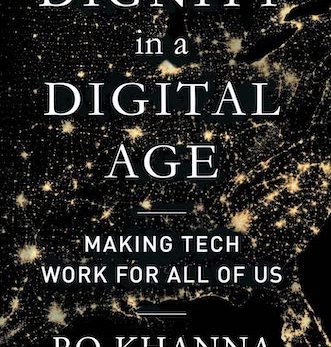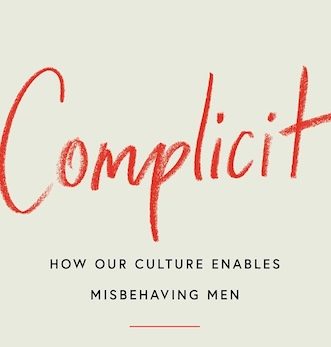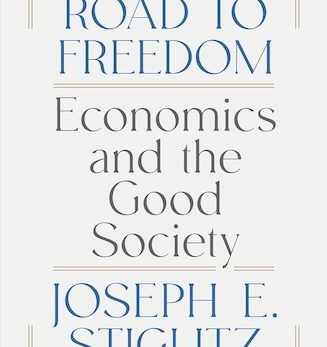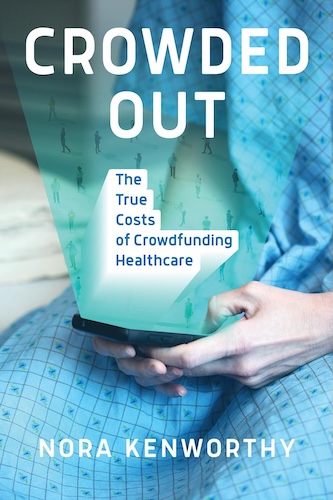
Nora Kenworthy著「Crowded Out: The True Costs of Crowdfunding Healthcare」
自分や家族の医療にかかる費用を捻出するためにクラウドファンディングサイトを使って支援を募ることが日常的になったいま、クラウドファンディングによる医療へのアクセスがどのような問題を引き起こしているか、クラウドファンディング黎明期からの長期にわたる研究を通して論じる本。著者はワシントン大学看護学科の教員で公衆衛生研究者。
コミュニティの中で事故や病気その他の困難を経験している人を支援するミューチュアル・エイド(相互扶助)の営みは、はるか昔から存在した。クラウドファンディングのプラットフォームは自らをその現代版だと称し、いざという時に誰にでもアクセスできるセーフティネットであり、政府や教会・財団を運営する大富豪らに受給資格を認められずとも支援を受けられ、また支援する一人ひとりがその対象や金額を自由に決めることができる民主的な社会支援の仕組みだと宣伝する。しかしその実態は、「誰が支援を受けるに相応しいか」の判断を分散化しただけでその定義は温存され、むしろアクセスできる社会資本の有無が受けることができる支援に大きな格差を生み出してしまった。
クラウドファンディング・プラットフォーム各社は「昨年はこれだけの寄付を集めた、これだけの人が支援を受けた」という自分たちに都合のいいデータは公表するが、具体的にどういう人がどれだけのお金を受け取ったのかは公表しない。またメディアは、銃乱射事件やテロ事件など大きな話題を呼んだ事件の被害者や遺族によるクラウドファンディングや、テイラー・スウィフトら有名人が自分のファンのクラウドファンディングにこんなにたくさん寄付した、といった話題ばかり報道するため、より一般的な、普通に医療費の支払いに困っている人が行うクラウドファンディングについてはニュースにならない。このため一般の人は、クラウドファンディングが大多数の人にどのような恩恵があるのか、どのような問題があるのかを意識しにくい。
著者ら研究者たちは、クラウドファンディング・プラットフォームをスクレープしてデータを収集するとともに、目標金額を集めることに成功した人、全然集まらなかった人、支援した人ら多くのユーザにインタビューしてその経験を聞き取る。また、プラットフォームには支援を求めている人たちの人種や収入、教育、家族構成など個人情報は含まれていないけれど、住んでいる地域は分かるので地域ごとのデータを使うことで裕福な地域と貧しい地域の比較などもおこなっている。クラウドファンディングの多くはほとんど寄付を集めることができておらず、支援を集めることができるページとそうでないページには明らかな傾向があった。
たとえば、事故や自然災害、暴力犯罪など突発的な事態によって一時的な支援が必要となったストーリーを語るページは支援を受けやすく、家賃が払えない、慢性疾患の薬が買えない、といった訴えは「支援を受けたところで来月どうすんだよ」と反発されて支援を受けられない。また、うまく編集された動画や画像があるページは支援を受けやすく、誤字脱字があるページは支援を受けられないが、貧しい人の多くは世代遅れの安いスマホを使っているのでそうした編集をするのが難しいし、小さな画面では誤字脱字も多くなる。支援をする人の大多数はもともと支援対象と現実社会やソーシャルメディアで繋がっている人たちだが、人種や階層によって分断化された社会においてそれは社会資本の有無が受けられる支援に直結することを意味する。
それでも貧困層、とくに貧しい黒人たちは、次は自分が支援を求める側になるかもしれないという意識もあり、仲間のクラウドファンディングを支援しようとするが、コミュニティ全体が貧しければお金はあまり集まらない。とくに地域で大規模な工場や店舗が閉鎖され失業が蔓延したり、パンデミックによって多くの人たちが困窮しているタイミングでは、お互いを支え合う余裕すらなくなってしまう。そもそも貧しい人たちは、クラウドファンディングをするにしても周囲の負担にならないように、あるいは苦境を口実にお金を巻き上げようとしていると周囲に思われないように、目標金額をそもそも低く設定しがちで、仮に目標額が集まっても僅かな足しにしかならないことが多い。いっぽう中流階級以上の人たちは、ほかの中流階級の人たちと繋がっているので、より手軽に(といっても動画を撮ったり頻繁に情報を更新したり労働しているけど)手術費用など緊急的に必要になった資金を集めることができる。さらに、多くの支援を受けているページはそれだけで「これだけの支援を受けているのだから信用できるのだろう」とさらなる支援を集めるため、格差はさらに拡大する。
クラウドファンディングは「誰でもアクセスできるセーフティネット」という技術解決主義的な建前を宣伝することで、本当に必要とされているセーフティネットの整備を遠ざけているし、多くの人が疾患や負傷を負う原因となっている環境破壊や労働搾取、貧困による栄養の偏りという根本的な問題から目を逸らすための道具となっている。シアトル大学の法学者ディーン・スペードは「Mutual Aid: Building Solidarity During This Crisis (and the Next)」のなかで、ミューチュアル・エイドはいま目の前で困っている人を支援するだけでなく、困難を生み出している社会的要因を暴き出し、その変革を目指す社会運動の入り口だと規定したが、クラウドファンディングは既存の不十分な福祉制度や慈善活動の欠点を温存したまま決定権を分散化することでその責任を問えなくするだけ。
そもそもクラウドファンディングは、医療費や食費、家賃など切実なニーズに応えるために生まれたものではなかった。ベンチャーキャピタルなどの投資を受けにくいけれどコアなニーズに応えるような製品を作るためや、ニッチなジャンルのアートやメディアの製作に作家が取り掛かるため、あるいは特別な誕生日パーティやハネムーンの費用を集めるためなど、クラウドファンディングにふさわしい分野はたくさんあるし、クラウドファンディング・プラットフォームは当初そうした活動を支援するために生まれたものだった。しかし福祉が十分に機能しておらず、健康に生活するためのリソースが不均衡な社会においてそれは、政府にかわるセーフティネットの役割を取り込まずにはいられなかったし、そうすることでプラットフォームを運営する企業は大きな利益をあげるようになった。
クラウドファンディングの不均衡を解消するためのアイディアはいくつか提案されていて、たとえばクラウドファンディングで集まる金額に一定の税金のようなものを設けて別の基準で分配するなどといった案もあるが、どう実施するのか難しそうだし、そもそもの問題が解決されていない。必要なのは、わずかにより公平なクラウドファンディングではなく、医療をはじめ健康な生活のために必要なリソースにアクセスするためにクラウドファンディングに頼らなくてはいけない社会的要因の解消。当たり前だけれどとても重要な指摘がデータとともに示される内容だった。