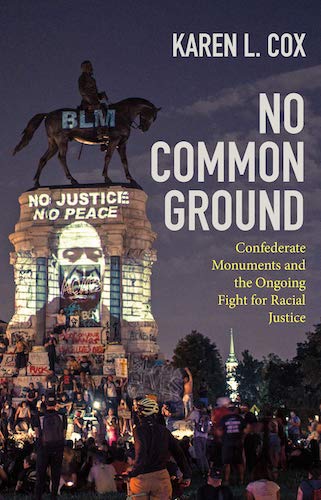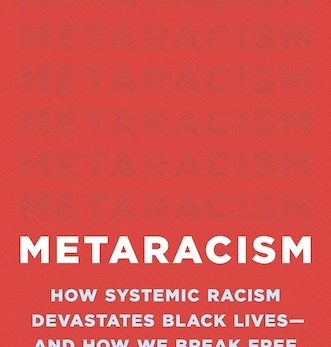Stefan M. Bradley著「If We Don’t Get It: A People’s History of Ferguson」
ミズーリ州セントルイスの郊外ファーガソンで18歳の黒人男性マイケル・ブラウン氏が警察によって射殺され遺体がビニールシートすらかけられずに8時間も路上に放置された2014年の事件が起きたときセントルイス大学の若手黒人男性研究者だった著者が、その後しばらく続いたプロテストに連日参加し、そこで経験してきたこととその教訓をまとめた本。
マイケル・ブラウン氏の殺害は、2012年のトレイヴォン・マーティン少年殺害や2020年のジョージ・フロイド氏殺害と並んで、黒人の命をあまりに簡単に奪う警察や自警団・警備員らに抗議しブラック・ライヴズ・マター(黒人の命を粗末にするな)を掲げる活動が爆発的に広まった事件の一つ。ファーガソンは住民の大多数が黒人だけれど市長や市議、警察署長ら指導層が白人で占められた街で、些細な交通違反や証拠に基づかない嫌疑によって逮捕された黒人たちが支払う罰金で財政を成り立たせていた植民地のような土地であり、激しい抗議活動が起きたきっかけはブラウン氏の殺害だったが普段から黒人市民たちの不満は高まっていた。
抗議活動を先導したのは地元ファーガソンやその周辺に住む若い黒人たちで、学生や若いプロフェッショナルだけでなく、仕事が見つからずに苦しんでいる人や、麻薬の売人やストリッパーなど普段は表舞台にあまり出てこない人たち、さらにはそれまでお互いに抗争していたストリートギャングのメンバーたちも一時的に和解して参加した。中小企業の経営者やプロフェッショナル、牧師ら立派な肩書きのある指導者たちがカチッとしたスーツに身を包んで率いてきた既存のリスペクタブル(品行方正)な黒人団体からは疎外されてきた人たちが運動の中心に立ったことがファーガソンの特徴だった。
そうすると当然、黒人のなかでも世代や階級による対立が起きる。アル・シャープトンやジェシー・ジャクソンJr.ら全国的に著名な公民権運動の活動家らがファーガソンに乗り込むも、かれらが若いころに体を張って白人至上主義者らの暴力に立ち向かってきたことを知らない世代から見れば「なにをよそから来て偉そうに」となるし、逆に既存の黒人団体の人たちは公民権運動のレジェンドたちに敬意を払わず、きちんとした身なりや言葉遣いをしようとしない若者たちに呆れるばかり。またファーガソンへの連帯感から全国からの寄付を集めるブラック・ライヴズ・マター国際ネットワークなどの団体が集めた資金をどう使っているのか透明ではないという不満も広がった。プロテストに参加した若者の多くは学校を休学したり仕事を辞めて運動に全力で打ち込んでおり、経済的な困窮はもともと覚悟していたこととはいえ、ファーガソンから遠く離れた有名な団体が多額の寄付を集めていると聞くと黙っていられないのは当たり前。
寄付金の扱いをめぐる論争は2020年夏のブラック・ライヴズ・マター運動の全国的な盛り上がりでさらに大きくなり、BLM運動を創始した三人の黒人クィア女性たちに対する批判が運動のなかで起きただけでなく、右派メディアやロシアの情報工作でも利用され、BLM運動の後退の要因の一つとなった深刻な問題。寄付金の使い方を決める指導層が十分に現場の活動家たちの声を聞いていない、運動のためにさまざまな犠牲を払っている現場の人たちの生活を支えようとしていない、という批判は正しいと思うけれど、もともとBLM運動をはじめる以前からほとんどお金がない状況で身銭を切って社会運動に関わってきた彼女たちに、いきなり集まった巨額の寄付金をうまくやりくりするスキルがないのは仕方がないとも思う。
また、右派メディアやロシアの情報工作で騒がれたような、寄付金を横領して個人の資産を増やしたという疑惑はほぼデマ。彼女たちの収入が増えたのはBLM運動に対する興味がピークだった時期に本を出版して印税を得たり、講演料やコンサルティング料で稼いだというだけで説明がつく。もちろん彼女たちが運動で名前を売ったあとそれに便乗したサイドビジネスで個人的な利益を挙げているという批判はできると思うけど、運動での実績が認められて有名になった人が著作や講演で儲けてはいけないというのもおかしいように思う。現に、この本を書いた著者自身、せっかくファーガソンの運動に初期から参加してその中心でさまざまなことを見てきたというのに、個人的に利益を得ようとしているとか売名しようとしていると批判されるのが嫌で、この本を書くのを10年ものあいだ躊躇していたそうだけど、かりにかれ個人の名声や収入に繋がったとしてもこの本の出版は十分に運動にとって有益だもの。
お金が絡まなくても、運動のなかではメディアの取材を受けて短く的確なメッセージを発信するのが上手な人や、ソーシャルメディアで運動の情報を拡散し支持を広げるのが得意な人がいる。自然とそういう人たちがメディアにおける運動のスポークスパーソンになるわけだけど、現場で体を張っている活動家たちからは「あいつ偉そうなこと言ってるけど現場であんまり見ないぞ」的な反感も広まる。しかし学業や仕事を中断して運動に毎日参加するのが本物の活動家でそうでない人は本物ではない、なんて意識が広まると、家族を持つ人や障害のある人らが参加できなくなるし、毎日現場に出ている人だっていつまでもそうしていられるわけがなく、運動が先細りするだけ。
またBLM運動創始者たちに対する反発にはホモフォビアやミソジニーも関連しており、BLM運動がホモフォビアやトランスフォビア、ミソジニーに対する批判をしていることに対して「なんで黒人の命を守れだけじゃだめなんだ、ゲイはゲイで別のところでやってくれ、女は活動家のための食事でも作ってろ」という意見も出ている。実際にはファーガソンの現場にももちろんたくさんのクィアやトランスの活動家がいたし、のちに下院議員となった(しかしパレスチナへの支持を公言したことで親イスラエル団体から対立候補に多額の資金を集中され再選されなかった)コリ・ブッシュ(「The Forerunner: A Story of Pain and Perseverance in America」著者)ら女性たちも中心で活躍していた。
本書は運動内部の実態とそこで命をかけて戦った現場の活動家たちの実像や声を紹介しつつ、いまでも解決されていないさまざまな課題がまとめられていて、運動に関わる人にとってはとても参考になる内容。運動内部にも世代や階級による対立やジェンダー・セクシュアリティによる差別などがあり、ときに内部批判は必要だけれど、お互いもうちょっと相手の立場を理解していきたいよね、と思った。