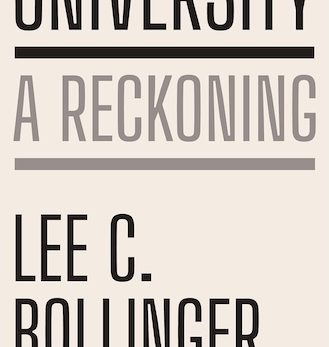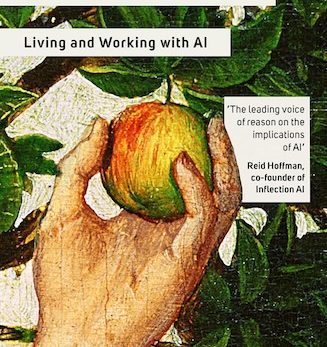Clarke Rountree著「Overturned: The Rhetoric of Overruling in the United States Supreme Court」
アメリカの歴史において最高裁が過去の判例を覆した300以上の判例を対象に、どのような場合判例が覆されるのか、それはどのようにして正当化されてきたのか論じる本。過去の判例破棄について細かく取り上げ分析するなかで、妊娠中絶の権利を認めた50年前の判決を破棄した2022年のDobbs判決がアメリカの歴史のなかでもいかに特殊で例外的なケースだったかあらためて示される。
最高裁は決して無謬ではない。300件もの裁判において最高裁が過去の判例を覆してきたという歴史は、最高裁が判断を間違えたり時代の変化とともに過去の判例が現実に当てはまらなくなったりした事実を指し示しているし、ときには最高裁判事の顔ぶれが変わることで判例が変更されることもあった。いっぽう最高裁の判例があまりに簡単にコロコロ変わるようだと、人々が安心して生活や事業を行えないし、法律の専門家である弁護士が顧客にどのようにアドバイスすればいいかわからないので、ある程度の法の安定性は必要。判例を変更することはタブーではないけれど安易に行われるべきではない、既に決着がつき人々が生活の前提としている法的論点はよほどのことがない限り取り上げないという原則がstare decisisと呼ばれる。
ちなみにロバート・ライシュ元労働長官が書いた「Coming Up Short: A Memoir of My America」によると、イェール大学法学院の授業でstare decisisの議論が行われたとき、もっとも積極的に手を上げて的確な発言をしていたのが ライシュの友人で同級生のヒラリー・ロダム(のちのヒラリー・クリントン)であり、同じく同級生でのちに最高裁判事として妊娠中絶の権利の破棄に加担したクレランス・トマスは一切手をあげていなかったという。うわー。
アメリカの歴史の最初の100年くらいのあいだは、連邦政府の権限を制限していた判例が破棄された例がほとんど。たとえば南北戦争にかかる費用を捻出するために政府が紙幣を発行する権利をリンカーン大統領が求めて認められたケースなど。大恐慌のなかフランクリン・ルーズベルト大統領が導入したニューディール政策が次々に最高裁によって違憲と判断されると、ルーズベルトは最高裁の定員を増やして自分の政策を通そうとしたが、結局定員増は実現しなかったものの高齢の判事の引退や長期政権によって多数の判事を任命したことでニューディール政策は実現した。定員増で最高裁を脅すことで自分の政策を通した、というストーリーが当時のメディアで伝えられ一般にも広く信じられたが、歴史家たちの多くが「あれはそもそも必要なかった、むしろ失態だった」と評価している、という話はLaura Kalman著「FDR’s Gambit: The Court Packing Fight and the Rise of Legal Liberalism」により詳しい。
ルーズベルトが任命した最高裁は戦後、黒人の市民権を否定した判例や人種隔離政策を容認した判例などを破棄し、犯罪容疑者の権利や女性の権利を推進するなどしたが、その大きな成果の一つが妊娠中絶の権利を認めた1973年のRoe v. Wade判決だった。そこから右派勢力は50年かけて中絶の権利への攻撃や司法の私物化を推し進め、ついに2022年にその判例を破棄させることに成功したが、これまで300件以上ある判例破棄のなかでもこれは異例中の異例。50年ものあいだ保障されてきた権利が最高裁によって奪われた例はまったく前例がないし、そもそも過去の判例破棄はおおむね保護の対象とされる人権の範囲を拡張するものだった。妊娠中絶の権利はアメリカの伝統において一切認められて来なかったとするサミュエル・アリート判事の判決文には歴史家たちから事実に反するとして否定されている。判例破棄に賛成したクレランス・トマス判事はRoe判決破棄の論理は避妊の権利を認めたGriswald v. Connecticut (1965)、同性愛を合法化したLawrence v. Texas (2003)、同性婚を実現させたObergefell v. Hodges (2015)などの再考にも繋がると主張したが、そこに異人種間の結婚を認めたLoving v. Virginia (1963)を含めないあたりが白人女性と結婚している黒人男性のトマス判事の卑怯なところ。
結局、Roe判決の破棄は最高裁が右派勢力によって乗っ取られたから以外に理由がなく、最高裁への信頼を著しく傷つけるものだと著者。stare decisisの原則は人々によって人生やビジネスの将来設計に組み込まれているものをあとから変えるのはよくないからであり、妊娠中絶は長期的に計画して行うものではないから判例を変更しても影響はない、というアリート判事の論理は、女性の身体や権利よりビジネスの戦略のほうが保護に値するという最高裁による価値判断の表明であり、めちゃくちゃ腹立たしい。しかしロバーツ裁判長が率いる現在の最高裁は政治資金規制を撤廃させ環境保護や労働者保護の制度を形骸化、黒人や貧困層の参政権を制限するなど、妊娠中絶以外の面でも過去の判例を変更しており、今後も数十年にわたってその影響が続きそうなことを思うと、本当にもう最高裁を増員するしかないんじゃ、と思う。