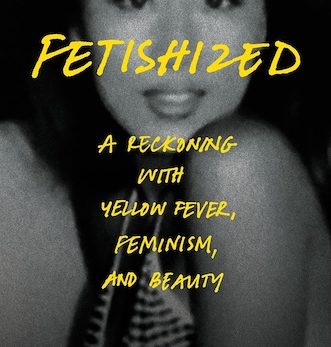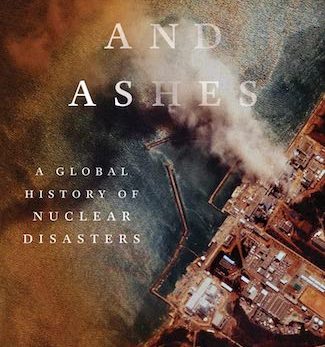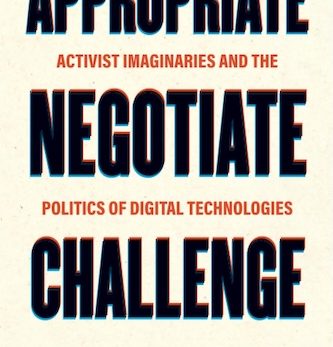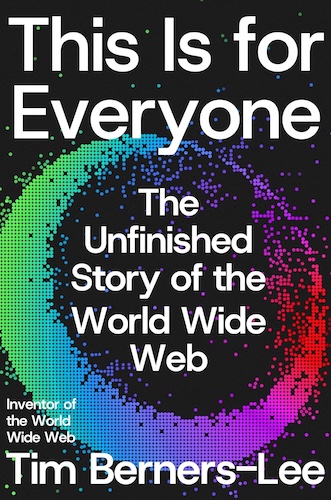
Tim Berners-Lee著「This Is for Everyone: The Unfinished Story of the World Wide Web」
ウェブ(ワールドワイドウェブ、WWW)の考案者ティム・バーナーズ=リーの自叙伝にしてインターネット史の本。
両親も数学者にして初期のコンピュータ研究者でかのアラン・チューリングとも知り合いだったというコンピュータ研究のエリート家庭出身。なんでCERN(欧州原子核研究機構)という物理学研究施設のなかからWWWが生まれたのか不思議だったけど、内部のカルチャーの話やアメリカの研究機関にインターネットの覇権を取らせまいとするヨーロッパの研究者たちの思いなど、初めて明かされるというわけでもないのだけれど著者の視点から語られる。
WWWより先行して広まっていたGopherが、開発元であったミネソタ大学がライセンス料を取る可能性があることを発表したことをきっかけに人気を落としたことを見て、著者はCERNにかけあってWWWから利益を得る権利を放棄。誰もが自由に使えて発信できる未来を目指したが、マーク・アンドリーセン率いるネットスケープによる独自の拡張などによりオープンな仕組みが脅かされ、また広告を売るために第三者クッキーを通して収集されたユーザの個人情報をもとに異なるコンテンツを提供するなどウェブが囲い込まれていく。HTMLからXHTMLへの移行をめぐってアップルやモジラとグーグルが衝突して著者が創設した標準化団体W3Cが分裂したときの話なども。
その後もソーシャルメディアによる社会分極化の加速やメンタルヘルスへの悪影響、一部のプラットフォーム企業による寡占からAIによるコンテンツ生成まで、著者は自身が望んでいた状態とは異なる発展を見せたインターネットやウェブを嘆きつつ、自由で多様な発信を可能としたウェブのレイヤー自体に対する信頼は失われていない。ただ著者はその良い例としてポッドキャストを挙げ、RSSというウェブ上で展開されたオープンな仕組みを使って配信されていること、独占的なプラットフォームが存在しないことなど、ポッドキャストが著者が本来目指していたウェブのあり方を引き継いでいると言うが、実際のところアルゴリズムで自動化されていないだけでポッドキャストがゲストやコラボの形で過激化を促進し社会分極化に加担している影響は少なくないし、そろそろAI生成ポッドキャストによる市場氾濫も無視できなくなってきそう。ていうかNotebookLMのあれなんやねん。
はじめてインターネットに触れたときはGopherでLynxやNCSA Mosaicの時代からウェブに触れていた自分にとって、著者の語りは懐かしいとともに、もしタイムマシンが手に入ったら1990年代前半に戻ってアンドリーセンを早いうちになんとかしないとあかんなと思った次第。そういえばAIが人類にもたらす影響について悲観的な人たち(doomer)と楽観的な人たち(boomer)という分類について著者はあまり意味を持たないとして、「doomerと言ってもAIの悪い面しか見ていない人は一人もいないし、boomerと言ってもAIの利点しか考えていない人は…一人だけいた、マーク・アンドリーセンだ」って本書には書いてあったりと、全体を通してアンドリーセンが悪役として大活躍している。