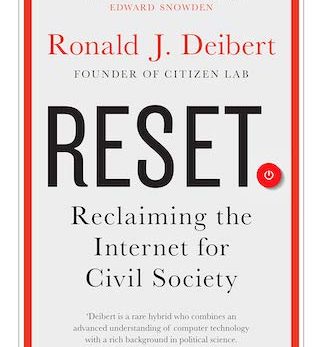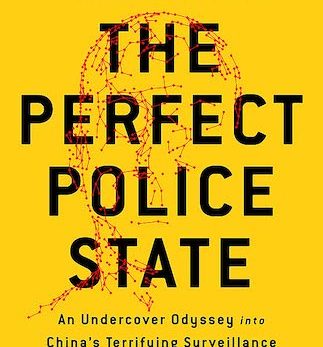John H. Richardson著「Luigi: The Making and the Meaning」
2024年12月、保険会社のCEOを暗殺して世間に衝撃を与えたルイジ・マンジョーネの生い立ちと思想形成に迫る本。世界で最も医療費が高額なのに成果が伴わないアメリカの医療制度において、その利益の多くを掠め取り、人々が受けられる医療を制限し多くの人を破産に追い込んだり見殺しにする医療保険会社への怒りから、かれの犯罪は広い共感を呼び、いまのアメリカを象徴する事件となった。
犯行から数日後に容疑者として逮捕されたマンジョーネはまだ20代の若い男性。裕福な家庭出身のエリートで、コンピュータエンジニアとして働いていたかれは、テクノロジーに管理され主体性を奪われた生活と環境の行き詰まりに息苦しさを感じ、またビデオゲームへの依存を自覚していた、そしてジョー・ローガンやイーロン・マスクら覇権的男性性を押し出すインフルエンサーらに魅力を感じ、白人や男性が「ウォーク」によって迫害されているという意見にも影響された、この世代の白人男性としてはごくありふれた存在でもあった。
本書はなかでもマンジョーネの行動に直接影響を与えた存在として、連続爆破犯ユナボマーとして知られるテッド・カジンスキーが若い世代のラディアルな男性たちに与えた影響に注目する。ユナボマー逮捕のきっかけとなったカジンスキーの論文『産業社会とその未来』はテクノロジーによる人間の自由と尊厳への侵害に警鐘を鳴らす内容だったが、本書ではそれに影響された若いラディカルな活動家たち(産業文明を否定する環境団体ディープ・グリーン・レジスタンスの人を含む)が複数紹介され、かれらとマンジョーネの類似性が示される。
マンジョーネはエンジニアとして人工知能の発達に期待を抱きながら、同時にそれに脅威を抱き、サム・バンクマン=フリードらによって知られるようになった効果的利他主義に近寄るなど、テクノロジストとしてどうテクノロジーと接するか悩んでいた。ほかにもマーク・アンドリーセンやピーター・ティールらシリコンバレーの極右的なテック富豪たちや、「ウォーク」を叩く右派メディアらの影響も受けつつ、テッド・カジンスキーの産業社会否定論にものめり込んだマンジョーネは、右翼や左翼という括りでなく迷走する男性性に突き動かされ、その結果として暴力に訴えるしか出口を見いだせなかったのかもしれない。
わたし自身、もちろん殺人は悪いことだというのを前提としたうえで、何万人という人を殺し続けている保険会社のCEOが射殺されたことに喝采を送りたい気持ちは抑えられなかったし、保険会社の非人道的な決定によって実際に家族や友人を失った人たちが涙ながらにマンジョーネに感謝し称えるのも理解できる。しかしマンジョーネ自身は保険会社によって愛する人を殺されたわけでもないし、かれ自身も強い痛みを伴う持病に苦しんでいるとはいえ保険会社によって不利な決定をされたというわけでもない。むしろかれ個人の怒りはかれの痛みを取り除いてくれない医療そのものに向けられていて、その関係から医療業界を攻撃する反ワクチン論者のロバート・ケネディ・ジュニア(現・保健福祉長官)を応援していた時期もあるほど。マンジョーネはかれの支持者が求めていたような民衆の英雄ではないようだが、現代の白人男性性の混迷を象徴する、裏のトランプ現象・裏のイーロン・マスク現象のようなものだと感じた。