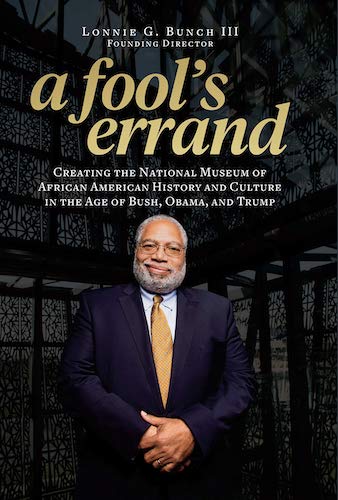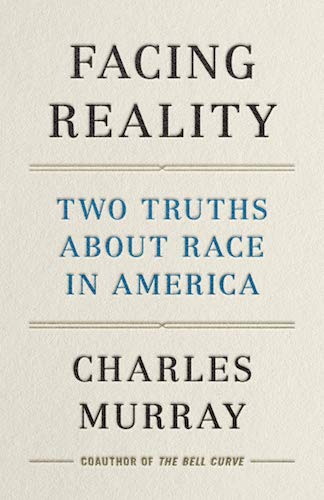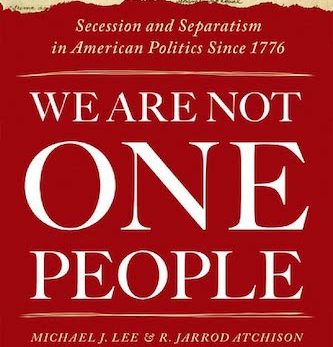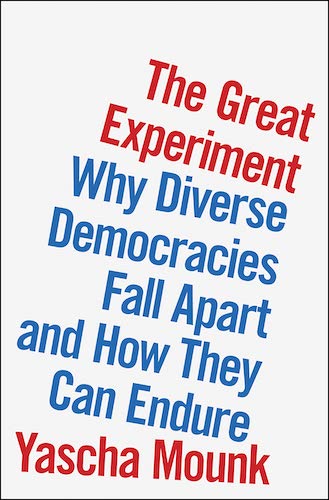
Yascha Mounk著「The Great Experiment: Why Diverse Democracies Fall Apart and How They Can Endure」
多様性の高い社会における民主主義という「歴史的に稀有な社会実験」への脅威を訴え、それを成功に導くための呼びかけの本。著者はドイツ出身でアメリカ在住のポーランド系ユダヤ人の政治学者。この「歴史的に稀有な社会実験」というのは著者がドイツのニュース番組でインタビューを受けた際に口にしたフレーズなのだけれど、すぐに世界中の右派メディアによって「ユダヤ人の学者がついに白人を社会の中心から追い出す実験が行われていることを自白した」というかたちで、いわゆる「リプレースメント理論」(人数では白人キリスト教徒にかなわないユダヤ人たちが、途上国からアジア人やアフリカ人や中東人や中南米人の移民や難民を殺到させることで、欧米社会を乗っ取り破壊しようとしている、という陰謀論)の証拠として拡散され、炎上した。たしかに「実験」という言葉は科学の分野では研究者が対象に干渉することで結果を観察するという意味合いが含まれるけれど、著者が言っているのはもちろんそういう意味ではなく、結果がどのように転ぶか分からない新たな社会的な変化の方向、くらいの意味。
著者いわく、歴史的に古代ギリシアにせよフランス革命にせよ、民主主義は同質的な共同体を前提としてきて、多様な民族や宗教を支配下に置いた大帝国においてその支配地域の人々一般に民主制が適用されることはなかった。現在先進国で移民やその子孫の増加の結果起きている、民主制における民族的その他の多様性の拡大は、その意味では歴史的にかつてない社会実験であり、著者はその成功を強く願い、そのために必要な条件を主張する。著者は本書の前半で、どういう政治的条件において民族紛争や宗教戦争が起きるのかという研究を紹介したり、多様な人たちが多数派文化への同化を強いられるのでも、それぞれの文化をそのまま温存しお互い不干渉になるのでもない、新しい共存と相互影響のモデルを提唱したりしたあと、後半において「多様な民主主義」という社会実験に対する悲観主義(ペシミズム)への批判を展開する。
著者は移住したアメリカでバラック・オバマの大統領当選に感銘を受けた一人の移民でもあり、アメリカ社会が多様になることを文明の崩壊や白人の迫害に繋がると恐れる右派のペシミズムに批判的なのはもちろんだけれど、同時に「アメリカは本質的に白人至上主義的であり、ほんとうの意味で多様な民主主義にはなれない」という「左派のペシミズム」をも批判する。多様な民主主義が成功するという保証はないけれども、それが失敗したときのリスクの大きさ(民族浄化やファシズムの危険)を考えると、成功に導くためのあらゆる努力を払うほかの選択肢はない、と著者は力説する。そのためには右派のペシミズムをただ差別主義だと批判するだけでなく、多様な民主主義によってみんながいまより文化的にも経済的にも豊かな社会を生きられるという楽観的なヴィジョンを主張するべきで、アメリカにおける「多様な民主主義」という社会実験の結果が出るまえから成功の可能性を否定するような左派のペシミズムは有害だという。
また著者は、左派のペシミズムは政治路線として間違っているだけでなく、事実にも反している、と指摘する。たしかにアメリカ社会の人種差別やその他の差別はいまでも深刻だし、まだまだ改善しなくてはいけないことがたくさんあるけれども、それでも数十年前に比べれば確実に世の中は少しずつ良くなっている、として、著者はさまざまなデータを紹介する。でもそうしたデータの多くは、これまでのさまざまな時代において移民たちが最初は差別されて苦労したがそのうち主流社会に受け入れられて行った、というものであって、移民としてではなく所有物としてアメリカに輸入されてきた黒人奴隷やその子孫たちが同じように主流社会に溶け込んでいるというデータは(バラック・オバマのような例外––そもそもかれは奴隷とされた人の子孫ではないけれど––を除くと)少ない。著者が「左派のペシミズム」を繰り返し批判しながら、黒人特有の経験に基づいた「アフロペシミズム」の思想に一切触れていないことにも気になる。
「204X年にはアメリカ社会において白人より非白人が多くなり、白人は多数派ではなくなる」という言説に対しても著者は、それは「白人」と「非白人」が固定した画一的なカテゴリだという誤った想定に基づく試算で、実際には白人とアジア人の親を持つ子どもたちなど統計上の「白人」「非白人」で括れない人たちが増えていることや、スペイン系のメキシコ移民やその子孫など「ラティーノ」に含まれる白人もいること、なによりアイルランド人やイタリア人やヨーロッパ系ユダヤ人が「白人」のカテゴリに含まれるようになったように今後アジア人やラティーノの一部が「白人」というアイデンティティを持つであろうことなど説明し、単なる統計的動向によってアメリカ社会がより「非白人」中心の社会になることはない、と指摘していて、それ自体は正しいと思うのだけれど、より本質的な対立項は「白人」と「非白人」ではなく「非黒人」と「黒人」である、という批判的人種研究の見解にも触れていない。「非白人」は画一的なカテゴリではないと言いながら、そして「アメリカは本質的に白人至上主義的だ」などとは言わないほうがいいと主張しながら、アメリカという国の本質に関わる先住民に対するジェノサイドと黒人奴隷制度というそれぞれの集団に特有の経験を無視し、かつての南欧・東欧系移民やいまのアジア系・中南米移民の話と同列に並べているのは疑問に思う。
リベラル民主主義を守る立場からリベラルや左派のペシミズムを批判する、という構図は、数日前に読んだ(レクチャーにも行った)Francis Fukuyama著「Liberalism and Its Discontents」とも共通している。わたしはMounkやFukuyamaの主張に全面的に反対ではないというか、かなりの部分同意しているのだけれど(とくに、右派のペシミズムに対抗するためには経済成長と福祉国家が必要だという点)、かれらが「左派」、とりわけ黒人研究者や黒人活動家の主張に正面から向き合わず、「ウォーク」という言葉を使って貶めている点には納得いかない。てゆーかフクヤマはもともとそういう人だけど、この著者は違うんじゃないの?って思った。