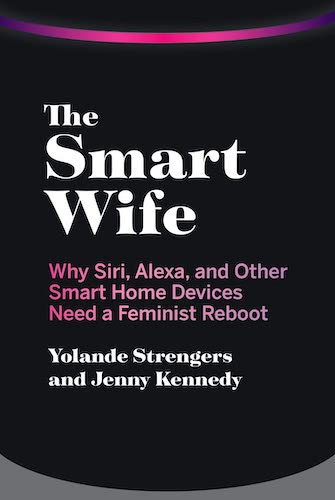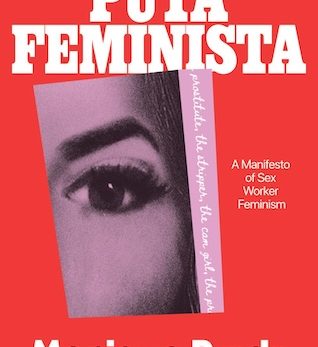Oliver L. Haimson著「Trans Technologies」
トランスジェンダーの人たちが抱える社会的・身体的な課題を解決し、またトランスの人たちの生を肯定することで新たな世界を切り開く、トランス・テクノロジーについての本。著者はトランス男性の情報科学研究者で、エンジニアやデベロッパーとして働く人たちを含め、多数のトランス当事者のテクノロジー開発や利用を追う。
トランスジェンダーの存在は現代で言うところのテクノロジーに依存しないが、ホルモン治療や外科手術などの医療を含めたテクノロジーの発展によって大きく影響を受けてきた。しかしそうしたテクノロジーへのアクセスは均等ではなく、テクノロジーどころか基本的な情報にアクセスする権利すら、学校図書館の検閲や社会的なバッシングによって脅かされている。本書で紹介されるのは、そうした現実に立ち向かい、情報を共有し、必要なリソースにアクセスするためにトランスジェンダーの人たちが開発し、利用しているテクノロジーの数々。
古くはトランス女性に向けて医学的・社会的トランジションの情報を広く発信してきた「TSロードマップ」のウェブサイトから、トランジションをサポートするスマホアプリ、各州で提案されている反トランス的な法案をマップ上にまとめて対抗するための運動を起こすためのデータベースまで、さまざまな話が取り上げられているが、正直「そんなものか」という感想を持った。いやそれらが必要とされているのは分かるのだけれど、あんまりワクワクするような話ではない。てゆーか、90年代から2000年代前半までのトランス活動家業界って、男性としてテック業界で出世したあとでトランジションしたえらそーな白人トランス女性がけっこう多くて、そのあたりの人たちに良い感情を持ってないので、彼女たちの名前がたびたび出てくるとなんか嫌な思い出が浮かび上がってくるという事情もないこともない(私情)。
トランス当事者でない人が「トランスジェンダーの人たちのために」と思って(あるいは「トランスで金儲けしてやる」と思って)作ったアプリが当事者のニーズに応えていないことが多い、というのはまあ当たり前だけれど、当事者だからといって全ての当事者のニーズを把握しているなんてことはもちろんない。とくにテック業界は中流階級出身の大卒白人が多く、かれらが「自分が欲しかった」テクノロジーを開発するとそれは非白人や貧しい家庭出身のトランス当事者たちのニーズとはかけ離れたものになりやすい。たとえばあるトランス男性が開発した、男子トイレでほかの男性と並んで目立たずに立ちションするための器具は、想定しているユーザの肌の色や体格が限られるが、より多くのトランス男性たちのニーズに応えられるようにラインアップを増やすことはコストがかかるので難しい、と放置される。
このように、どのようなテクノロジーが開発され、また実用化されるかは、資本主義の論理で決まってしまう。一部のデベロッパーがトランスコミュニティの中でも購買力のある客層を狙ったアプリを開発しベンチャーキャピタルからの投資を受ける一方、研究者などが開発に協力しより多くのトランス当事者たちのニーズに応えようとするアプリは資金不足で実用化されなかったりする。自分たちのニーズを汲み取ったテクノロジーが開発されると信じてアンケートに参加するなどして協力した当事者にとっては、ただ研究に利用されただけになってしまう。
最初に書いたように、本書ではトランス・テクノロジーという言葉に「トランス当事者の課題を解決するためのテクノロジー」のほかに「トランスの生を肯定することで新たな世界を切り開くテクノロジー」という第二の定義が当てられているが、この第二の部分も正直期待外れ。ホセ・エステバン・ムニョスの言うところの「いま・ここ」ではない地平のテクノロジーを構想することが難しいのは分かるけれど、どうも「身体の改造が自由自在に行われる世界」くらいしかアイディアがないようで、どうもわたしが期待する新しい世界とは違うような気がしている。