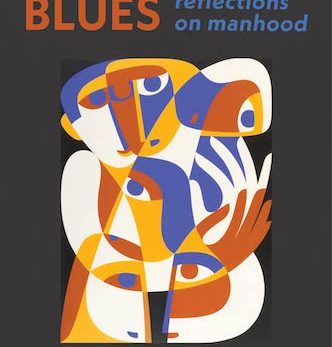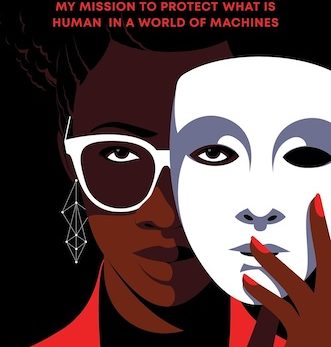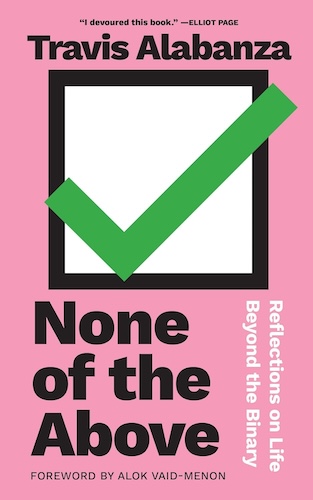
Travis Alabanza著「None of the Above: Reflections on Life Beyond the Binary」
イギリスに住む黒人ミックスでトランスフェミニンなノンバイナリーな著者が、トランスフォビアがメディアに溢れ、トランスやノンバイナリーの当事者たちが防衛的な自己プレゼンテーションを強いられるなか、それに抵抗して自分たちのための言葉を取り戻そうとすると同時に、ジェンダー二元性がどのようにしてすべての人たちの可能性を狭めているか訴える本。イギリスで2022年に出版されたけど、わたしが読んだのは2023年に出たアメリカ版なので表紙画像とリンクはそちらへ。
わたしがSNSやブログで読書報告をはじめていらい3冊目の「予想をはるかに上回ったすごいトランス本」で、2021年のShon Faye著「The Transgender Issue: An Argument for Justice」と2023年のSchuyler Bailar著「He/She/They: How We Talk About Gender and Why It Matters」に挟まれる2022年のベスト・オブ・トランス本。毎年のようにこんな良質なトランス当事者によるトランス本が出ているの、嬉しい。
トランス当事者に対するバッシングが猛威を振るうイギリスにおいて、トランスジェンダー当事者が期待される自己プレゼンテーション、すなわち自分の性自認は生まれつきこうだった、子どもの頃からずっとそう感じていてこれからも一生まったく揺るがない、そして男性なら男性、女性なら女性としてあらゆる面で一貫している、といった、「正しいトランスジェンダーのあり方」に対して、著者は自分には当てはまらないと公言する。ノンバイナリーというアイデンティティやジェンダーを超越したファッションなども著者にとっては確固としたものでも一貫したものでもなく、自分がどうありたいのか、そしてそれはどこまでが自分本来の希望でありどこまでが社会との軋轢や面倒を避けたり潜在的なパートナーに欲望されるためのものなのか、判然としないことを率直に語る。「どうしてトランスジェンダーになったのか、いつそう分かったのか」という質問や「ちゃんとしたトランス」というマイクロアグレッションなど周囲の質問やコメントに対して、うまく躱しながらそれらがトランスやノンバイナリー当事者から自分の人生を語る言葉を奪っていることに抵抗し、ジェンダー二元性がトランスやノンバイナリー当事者だけでなくすべての人から自由を奪い、だからこそ自由に生きようとしているトランスやノンバイナリーの人たちが攻撃の対象となってしまう構図を指摘する。
黒人たちが多く住む貧しい地域で育った著者が女装をはじめたとき、トランスジェンダーを白人中流階級の文化だと思っている近所の大人たちから警告されたり、ノンバイナリーだと母親にカミングアウトして「それは大学で知ったの?」と聞かれた著者は、アフリカのさまざまな文化や労働者文化に伝統的に存在した多様なジェンダー文化が植民地主義や階級制度によって抑圧された歴史と、現在でも反トランスジェンダー的な主張が白人至上主義と結びついている一方で、現実にトランスジェンダーやノンバイナリーのコミュニティが白人中流社会のものとなってしまっている現状について考える。英米のLGBTコミュニティではアメリカの先駆的なトランスジェンダー活動家として黒人のマーシャ・P・ジョンソンやラティーナのシルヴィア・リヴェラの名前がよく挙げられるが、彼女たちが自分のことをゲイ、ドラァグクィーン、ストリートクィーン、トランスヴェスタイトと呼んだことは無視されて、「ブラックやブラウンのトランス女性」として言及される。たしかに、もし彼女たちがいまの時代に生きていたらトランス女性と自称していた可能性は高いとは思うのだけれど、彼女たちが当時ノンバイナリー的に、そして時期や文脈においてさまざまに揺れ動く自称を用いた事実は抹消され、白人中流LGBT史にとって扱いやすいものに改変されている。
著者がショッピングの最中、女子試着室を使おうとして店に拒否され抗議したところ、実際にはその店にはもともと性自認に応じた試着室を使用できるポリシーがあったのに著者の抗議のせいでポリシーが変更されたと間違った前提のもと著者に対するバッシングがメディアで広まった事件についての一章は読んでいて息苦しい。白人女性フェミニストが書いた「トランス・ロビーにすり寄るために子どもが犠牲にされた」というタイトルの記事では、黒人女性の髪型に対するレイシスト的な表現を含め著者の外見を攻撃する内容だったが、著者は「ジェンダー二元性によって子どもが犠牲にされている」という現実に基づいたものにタイトルを読み替えていく。最終章では、目に見えてノンバイナリーな人物として有名になった著者が、自分は自分が望むままより女性的に外見やプレゼンテーションを変えてしまってもいいのか、それはどこまでが本当に自分の希望なのか、それとも社会との軋轢に疲れてしまっただけなのか、と悩んだうえで、どのように生きようと社会の視線からは自由になれない一方、社会のためではなく自分のために生きたいという希望を語る。
自分は男性だから男性、女性だから女性、というトランス当事者本にありがちなパターンのままに、自分はノンバイナリーだからノンバイナリー、的なノンバイナリー本も多いなか、本書はノンバイナリーを生み出しているバイナリー(二元性)の暴力性と(女性差別はもちろん)白人至上主義や階級制度との繋がりを指摘し、バイナリーからの自由をトランスやノンバイナリーだけでなくすべての人の自由として論じる。あんまり「予想を上回るすごい本」とばかり言っていたらわたし自身がトランス系の本に対して期待値を下げすぎているんじゃないかという疑惑が浮かびそうな気がするけど、実際つまらない本も多いし、良い本は良い本としてもっと多くの人に広めたい。