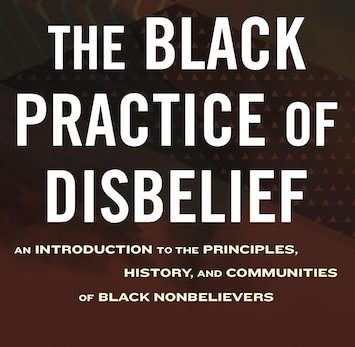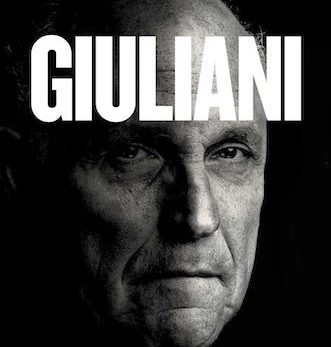Cass R. Sunstein著「Campus Free Speech: A Pocket Guide」
大学のキャンパスにおける言論の自由をめぐる論争について多数のパターンをあげて現時点でのアメリカ最高裁の判断を解説しつつ、物理的にも内容的にも薄い本を大量生産しているサンスティーンせんせーが2024年に出版。
憲法には政府が言論の自由を脅かしてはいけないと書かれているが、それが絶対の権利でないことは、言葉を使った脅迫や詐欺やセクハラの自由が認められていないことからも明らか。公立大学も憲法上の制約により学生や教員の言論の自由を尊重することが義務付けられているが、大学の教育・研究という使命を脅かす発言についてはその限りではなく、ヘイトスピーチや陰謀論などの扱いについて議論が分かれることもあるが、本書は現行の最高裁の判例をもとに多数のシナリオを通してその原理原則を解説する。
本書が出版された時期に著者はニューヨーク・タイムズ紙に学生たちによるパレスチナ連帯運動と言論の自由についての論考を寄稿しており、大学におけるパレスチナ連帯運動とそれに対する大学当局や警察による弾圧が本書が書かれた背景にあることは確実。著者は学生たちには政治的主張をする権利があるとしながら「違法行為を扇動する言論は憲法の保護を受けない」という原則論を挙げ学生たちがキャンパスに(違法に)設置した抗議キャンプの排除やそれに関わった学生の処罰を正当化するが、抗議そのものに正当性があるかどうかについては踏み込まない。憲法上の判断としては政治的主張の是非は言論の自由が認められるかどうかに関係がないというのは正しいが、著者は憲法上の保護を受けるかどうかを排除や処罰の正しさと混同している。
ヘイトスピーチ規制を認めていないアメリカの法制度において、差別発言を行う自由と差別に抗議する自由は法律上等価に扱われる。著者はこれを肯定的に評価し解説しているのだが、現実社会には社会的属性や階層による権力の不均衡があり、それ以外の側面での平等も対等な言論も保証されない。人種隔離のように極度に不公正な法が存在したり、あるいは極度に不公正な状態が法によって放置・温存されているとき、違法行為を伴う抗議活動の是非は法だけによっては判断できない。学生たちがキャンパス内にテントを張って抗議活動を続けたのは、イスラエル政府によるジェノサイドがガザで進行するなか、自分たちが通う大学が運営基金の一部をイスラエル政府と繋がりのある企業に投資していることを知り、パレスチナ社会からの要請に基づいて投資の撤収を大学当局に求めるためだ。そうした学生たちの排除や処罰が正しいかどうかは、学生たちの行動が言論の自由として認められるかどうかだけでは判断できない。
著者は「言論の自由はフレームワークであってアルゴリズムではない」と言い、また著者が働くハーヴァード大学など私立大学は憲法上の制約を受けないとして言論の自由より教育的使命を優先することがあり得ることも指摘しているように、憲法における言論の自由だけが基準でないことは認めているのに、現に各地のキャンパスで戦っている学生たちに対しては突き放すような扱いをしている。そうするうちに政権がかわり、ハーヴァード大学が政府による猛烈な攻撃を受け大学自体の自由を守るために戦うことを強いられるようになっているが、いまの最高裁は今後言論の自由を大幅に制限する判決を下す可能性が高く、著者自身の言論の自由もそれほど安泰ではないように思うのだけれど、そうなったとき著者は何と言うんだろうか。