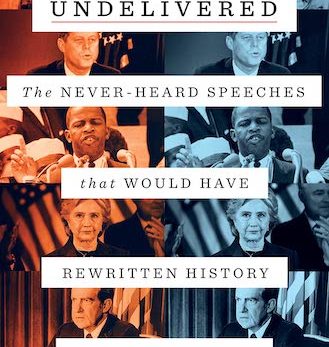Rebecca Tuhus-Dubrow著「Atomic Dreams: The New Nuclear Evangelists and the Fight for the Future of Energy」
近年、気候変動の原因となる化石燃料を使った発電を置き換える現実的なオプションとして再び注目を集めている原子力発電とその復権を熱狂的に支持する「核主義者」たちについての本。
環境運動と原子力との関係は複雑。まだ環境運動という言葉がなく、公害による健康被害や酸性雨、オゾン層破壊、気候変動といった問題が関心を呼び環境保護が叫ばれるようになる前には、シエラ・クラブなどによって残された僅かな人の手が入っていない自然環境をできるだけそのまま保護すべきだという自然保全運動が主張されていた。第二次世界大戦で広島・長崎で核兵器が使用されその脅威が広く知られたあとも、アメリカの自然保全運動が最も問題視したのはダムの建設によって自然環境や生態系の破壊につながる水力発電であり、それに比べて原子力発電は「自然に優しい」と考える人たちも多かった。
環境運動が原子力発電を積極的に批判するようになったのは、ヴェトナム戦争やウォーターゲート事件を経て政府に対する信頼性が崩され、グリーンピースなど新たな環境団体が登場する1970-1980年代以降。原子力発電が実は核兵器開発のための表向きの口実に過ぎないのではないかという疑いとともに、スリーマイル島やチェルノブイリ(最近ではウクライナ語でチョルノブィリと呼ばれることが増えているが本書ではロシア語のチェルノブイリと表記されている)の事故を経て原子力発電に対する警戒心が高まり、また仮に事故がなかったとしても長期的な解決の見込みがないまま増え続ける放射性廃棄物の扱いをめぐっても原子力発電に反対する人が増えていった。しかし気候変動の影響が加速度的に深刻になるなか、化石燃料の使用をできるだけ早く減らすためにも、温暖化ガスの排出が少ない原子力発電を再評価すべきだという声が一部の科学者や政治家たちから出ている。
本書は原子力発電をめぐる科学者や一般市民、政治家たちの議論を追いつつ、原子力発電の拡大を熱狂的に支持する人たちやその運動に取材し、その実態を明らかにしている。もちろん原子力発電を推進する人たちのなかには、既存の原子力発電所を運営している電力会社やそこで働いていて失業を恐れる労働者もいるが、真剣に気候変動について取り組み、また電力不足によって生じる人々の健康や生活への被害について考えたうえで、再生可能エネルギーとともに原子力の採用が少なくとも短期的には不可欠だと考える一般の人たちもいる。しかしそのどちらよりも目立つのは、原子力支持の運動に巨額の資金を提供している、シリコンバレーのヴェンチャー起業家や投資家、そしてマーク・アンドリーセンが言うところの技術楽観主義(テクノオプティミズム)に共感するテックブロたち。
原子力を支持する一般の人たちの多くは、再生可能エネルギーへの転換を行いつつ、それでは気候変動を止めるのに間に合わないから、とりあえず様々な問題を後回しにして原子力を併用するべきという立場だが、技術楽観主義者たちはそうではない。かれらはことさらに再生可能エネルギーを攻撃するばかりか、世間は原子力発電の危険を極端に過大視しており、懸念されている点は新しい技術の開発と採用によって解決できると考えている。たとえばチェルノブイリの事故で放射線被爆によって亡くなった人は数十人に過ぎず、福島では一人も亡くなっていない、として、健康や精神面での被害はむしろ放射線被曝の危険を過大視した非理性的な反応によって生まれたと主張する。
かれらは原子力こそ気候変動への解決策だと言うが、実のところかれらは気候変動の弊害すらも大したものだとは思っておらず、だから原子力というすでに実績のある技術だけで解決できるとして、電力消費を減らすような対策には反対している。とゆーかぶっちゃけ、かれらが原子力発電の拡大を求めるのは、化石燃料の使用を減らすことより、人工知能の開発や暗号通貨のマイニングのためにさらなる電力が必要だからじゃないかと。と思ったら、本来ならかれらはリベラルや環境運動の支持者に対して原子力が気候変動への解決策の一部になると説得しなくちゃいけないはずなのに、FOX Newsなどはじめから原子力を支持している右派メディアに頻繁に登場して原子力支持と同時にトランスジェンダー叩きとかやってたりして、わけがわからない。
このように原子力を支持する勢力のなかには、実際のところ多分気候変動なんてどうでもよくて、リベラルに対する逆張りをしたいだけのシリコンバレーのテックブロたちがいて、かれらが資金を提供しているが、一方で気候変動について真剣に考えている科学者や一般市民たちも増えているのも事実。著者自身、取材を続けるうちに再生可能エネルギーは思っていたほど良いわけではないし、原子力も思っていたほど悪いわけではないと気づき、気候変動に対応するためのエネルギー体制の転換の一部として原子力を採用することは否定しないが、仮に原子力発電所が新たに稼働するとしても、発電所や廃棄物保管所が設置される地域の住民たちやそれらの土地の本来の持ち主である先住民部族がそうした決定に参加し自由な意思に基づいて受け入れるかどうか決めるべきだと主張する。現にバイデン政権は廃棄物の最終貯蔵所を決めるための枠組みとしてそうした仕組みを導入しようとしていた。また、より多くのエネルギーを消費することが本当に良いことなのか、人工知能や暗号通貨のために原子力発電を導入することが本当にそのリスクやコストに見合うほど人々の幸せに繋がるのか、きちんと論じるべきだ。
本書はまた、2022年に稼働延長が決まったカリフォルニア州ディアブロキャニオンにある老朽化した原発をめぐる動きを詳しく解説しており、ギャヴィン・ニューサム知事がどのように延長反対から賛成に立場を変えたのかという部分が興味深い。ニューサムは次の大統領選挙に立候補するのではないかと思われている野心家だけれど(わたしサンフランシスコ市長時代のかれに会ったことあるけど野心とカリスマが溢れ出ているやばすごい人だった)、2003年に知事だったグレイ・デイヴィスが州内で起きた大規模な停電の責任を問われ解任選挙を起こされてアーノルド・シュワルツェネッガーに負けたことがニューサムの頭の中にあったことは明らか。当時の停電はのちに史上最大規模の粉飾や不正が表面化して倒産したエンロンの市場操作によって起こされたことは後からわかったけれど、大規模な停電は次の選挙で当選しなければいけない政治家にとっては死活問題。
気候変動がこれだけ騒がれても原子力の復権がそれほど進んでいない理由の一つは、気候変動の被害が将来どれだけ拡大しても個々の政治家が責任を取らされる危険はない一方、原子力発電所で事故がもしあったらそれを推進した政治家が個人的に責任を取らされるというインセンティヴの不均衡さがあるけれど、何年もたったあとに起きるかどうか分からない原発事故よりも自分の任期中に起きるかもしれない停電のほうが政治家にとってのリスクとなるという判断がニューサムにあったのではないか、というのは確かにそう。エンロン云々が判明する以前からデイヴィス知事の解任は気の毒だと思ってたけど、そういった事情によって社会にとって長期的に重要な問題が決定されてしまうというのは民主主義の困ったところではある。