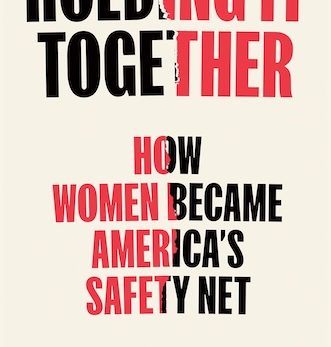Julie Guthman著「The Problem With Solutions: Why Silicon Valley Can’t Hack the Future of Food」
あらゆる問題に政治的な働きかけや運動を通さずテクノロジーによる解決を目指す、場合によってはテクノロジーが先にありそれによって解決できる問題を逆算して求めてしまっている技術解決主義(テクノソルーショニズム)が約束する食糧問題の解決を批判する本。
技術解決主義といえば、気候変動を押し留めるために政治的に困難な国際的な取り決めの実現や経済活動の変革ではなく、太陽光が地表に届かないように大気に工作しようとするジオエンジニアリングや、犯罪を抑止するためにその根本的な原因を取り除くのではなく監視技術による効率的な取り締まりを行ったり、同様に警察による黒人の一般市民への暴力を減らすために人種差別への取り組みではなく警察官にボディカメラの着用を義務付けるようなものが、かねてから批判されている。それらは根本的な原因に取り組むよりも政治的な抵抗が少なく、より効率的に望ましい結果をもたらすとされているが、実際にはそうした言説そのものが本来必要とされている取り組みを遠ざけ、政治的に不可能な領域に押し込めている。
食糧問題は明らかに、近い将来の人類にとって重要さを増している問題だ。気候変動によって従来どおりの食糧生産が難しくなるとともに、産業畜産はその気候変動の大きな原因の一つでもある。シリコンバレーでは食糧問題を解決する、あるいは産業畜産を過去のものにするとして、代替肉や人口培養肉をはじめさまざまな技術が注目を集めている(というか、集めていた––もう代替肉のブームは終わってビヨンドとインパッシブルの大手ニ社すら維持できなくなりかけている)が、著者はそうした技術がピッチされる投資家向けの説明会や、その学生版となる各大学の技術発表会などに出席し、農業や食糧生産の現状を破壊すると称する技術的解決の大半が実際には問題の解決には繋がらないばかりか、一部の巨大企業による寡占化をさらに推し進めるだけに終わる可能性が高いことを示す。
食糧生産における技術開発主義の先例として記憶されるのは、20世紀中盤にロックフェラー財団などが中心となって推し進めた「緑の革命」だ。アジアを中心とした各地での食糧生産の拡大を目指した品種改良や化学肥料・農薬の大量投入は、その目的自体は達成したものの、農業のコスト上昇と農産物の価格下落を引き起こし、小規模な農家の多くが廃業や自殺に追い込まれた。また「緑の革命」の結果、伝統的な農業が廃れ、化学製品への依存を生んだほか、土壌の劣化や環境汚染などの問題も生まれた。食糧生産の増加自体は良かったが、そこで生まれた富の公平な分配に失敗した––とまとめるのは簡単だが、そもそもそれ以前の時代においても食糧生産自体が不足していたわけではない。もともと食糧不足に悩む貧しい人たちにとっての問題は、十分に生産されていた、あるいは生産されるキャパシティがあったはずの食糧が公平に分配されていないことだったのに、富の不平等という根本的な問題に取り組むのではなく、技術解決主義によって食糧の増産を目指したところ、全体としての水準は上昇したかもしれないが、富の不平等はさらに拡大してしまった。
こうした歴史を踏まえないままテクノロジーによって気候変動など農業と食糧生産における新たな問題を解決しようとすることは、最大限うまくいったとしても、まったく同じ状況をもたらすだろう。とはいえ「緑の革命」はあれはあれでその「最大限うまくいった」例なのであって、実際のところ大半の農業テクノロジーや食糧生産テクノロジーはそこまでたどり着くこともない。将来性があるかどうか分からない、というより大半は失敗するだろうけれどほんの一部だけでも大当たりすれば儲けもの、というベンチャーキャピタルの論理で動くシリコンバレーはともかく、農業や食糧生産を大局的に研究し、それらが置かれた政治的・社会的背景も理解したうえで、貧しい農民たちが犠牲とならないような提言を行うべき学界までもが産業界からの資金提供を受けて短絡的な技術解決主義を推進しているのは深刻な問題。「緑の革命」がそうであったように、実際に問題に直面している当事者ではなく、そこから遠く離れた技術者たちが勝手に何が問題であるか判断し解決を押し付ける植民地主義的な側面も技術解決主義にはあり、大学がシリコンバレーと異なる論理で気候変動や食糧問題に取り組む必要がある。