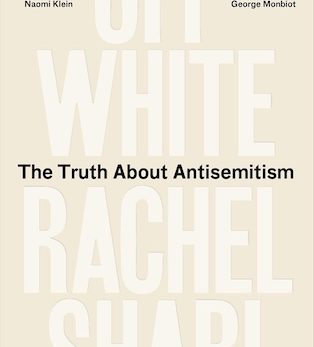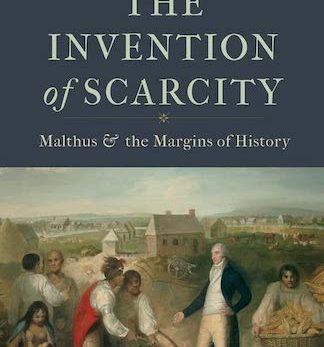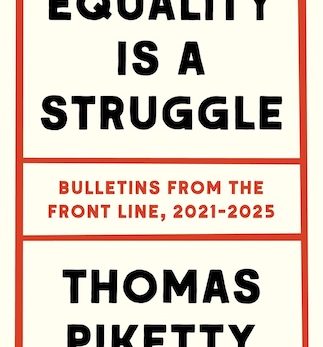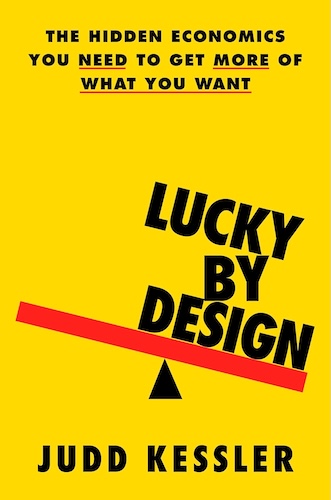
Judd Kessler著「Lucky by Design: The Hidden Economics You Need to Get More of What You Want」
ビジネススクールの教授でさまざまな市場の設計に関わってきた著者が、マーケットデザイン(市場設計)やシグナル理論など経済学的な概念を説明しながら、わたしたちが市場の設計を理解することでどう有利にふるまうことができるようになるのか、そして自分が市場を設計する側にまわったときにどういうことに気をつければよいのか解説する。
ここで市場というのはお金でモノやサービスを売買する場だけでなく、入試や就職、結婚、家庭内の役割分担や兄弟姉妹のあいだでお菓子やおもちゃをどう分け合うかという話、選挙など、限られたチャンスやリソースをめぐって多くの人が望むものを得ようと競合する場面を指す。入試や就職で最も高い金額(あるいは安い報酬)を提示した人を合格させるような大学や企業はないし、議会の議席も一応はお金で売買できるような仕組みにはなっていない。、また、お金で売買されているものであっても、テイラー・スウィフトのコンサートチケットやニンテンドースイッチ2のように値段が市場価格より低く設定されていて必ずしも高いお金を出せば買えるわけではない(そこを狙って転売業者が暗躍してしまう)市場もある。
本来、市場がうまくデザインされているならば、市場に参加している一般人がそのデザインを意識する必要なんてないし、意図的にシグナルを送信する必要もない。うまく設計された市場においては、人々が裏をかいたり戦略的にふるまわなくても、シグナルなんて非効率的なことをしなくても、それぞれ自分が望むものを追求すれば自然と全てはおさまるべきところにおさまり、全体の効用が最大化されるはず。しかし現実には市場設計は万全ではないし、効率性だけでなく公平性や簡易性という三つの目的のバランスを取ろうとする結果、どうしても非効率性が生じてしまう。だからこそ個人が市場の設計を分析し戦略的に行動することで、有利な立場に立つことができる。
たとえば著者は、自分が教えている人気の授業について、教えられるクラスの定員に上限があるなか、どのようにすれば本当にその授業に強い興味を持ち、多くを得て将来のキャリアに役立てることができ、そしてディスカッションなどを通してほかの学生たちにも良い影響を与えることができる学生を優先的に受講する機会を与えられるか、というマーケットデザインに日々取り組んでいるけれど、本書でその設計について書いてしまった以上、攻略法が将来の学生にバレてしまっている。しかし世の中には制度を作っている側すら意識していないものも含め、なんらかの前提に基づいて設計されたさまざまな市場があるので、マーケットデザインの思考を頭の中に入れておくことでさまざまな場面で有利に立てる。逆に制度設計を行う側に立ったときは、効率性・公平性・簡易性という三つの目的を意識することで、完全ではなくてもよりマシで参加者に負荷や不公平感を与えない設計が行えるようになる、と。
本書が扱っている経済的な話の実例は、医学研修生の勤務先や移植される肝臓のドナーと患者のマッチングに使われるアルゴリズム、マッチングアプリのうまい使い方など、だいぶ聞き飽きた話ばかり。これまで履歴書や志願動機のエッセイ、マッチングアプリで送るメッセージなどで、相手のことをきちんと調べてそれに応じて内容を変えることが自分の本気さをアピールするためのシグナルだとされていたけれど、生成AIの進歩によって労力をかけて書いたのと同じような履歴書やメッセージが簡単につくれるようになったという話はちょっと今的でおもしろいかも。でもわたし的に本書で一番おもしろいと感じたのは、マーケットデザインを研究する著者自身が自分の仕事や家庭でそれをどのように役立てているかという部分。子育てや夫婦の家庭内役割分担にまでマーケットデザインの発想を取り入れていることは、そういう発想がなかったとしても何らかの設計は行われるわけだから意識的なだけマシなのかもしれないと思いつつ、子どもやパートナーの側の言い分も聞いてみたいと思ったり。