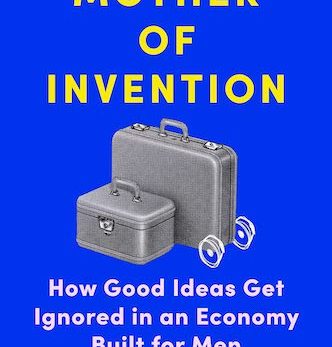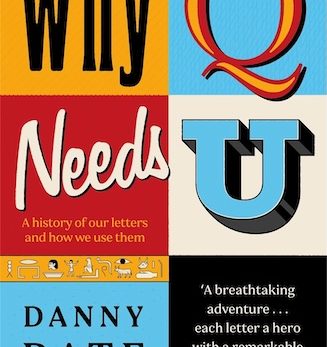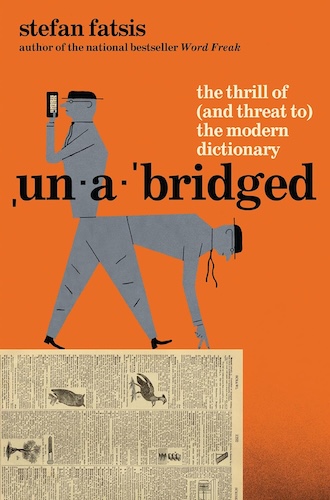
Stefan Fatsis著「Unabridged: The Thrill of (and Threat to) the Modern Dictionary」
辞書好きが講じて19世紀から辞書を出版してきたメリアム=ウェブスター社の辞書編集部で勤務した経験のあるライターが、辞書編集の歴史と現在について書いた本。
メリアム=ウェブスター社の名前のもととなっているノア・ウェブスターやジョージ&チャールズ・メリアム兄弟が辞書を編集・出版したのは、アメリカが独立してそれほど経っていない18世紀初頭。当時すでにイギリス英語から変化した方言が生まれていた新しい国の言葉をまとめ、その基盤にすることが目的だった。ウェブスターはGabe Henry著「Enough Is Enuf: Our Failed Attempts to Make English Eezier to Spell」でも紹介されているスペリングの簡略化・言文一致化を早くから推進した一人でもある。辞書は世間で使われている言葉をそのまま記録するのか、それともより好ましい用法を広めるツールなのか、といったアプローチの違いも。
時は進んで20世紀。辞書にどの単語を含めどの単語を含めないのか、どういった用例を載せるのかなど、それぞれの辞書とその有名編集者たちが信念をかけて編纂を続けていく。大学生向けのコンサイス版が人気となり、メインの辞書本体の編集を続ける財源になったが、辞書の定義が政治的な論争になることも多くなる。fワードをはじめとする性的な用語を含めるかどうか、黒人に対する侮蔑語や女性に対する差別的な言葉の扱いをどうするか、など。21世紀になると辞書をインターネットで提供するかどうか、するとしたら無償なのか料金を取るのか、編集を続けるための財源をどう確保するのかといった問題が生じるいっぽう、WikitionaryやUrban Dictionaryのようなそれぞれ特徴のあるクラウドソースの新しい辞書が生まれてくる。十分なテキストデータがあれば人工知能が言葉の意味を分析して定義を作ることができるのかどうか、その定義は人間の編集者が作る定義とどの程度異なるのか、といった話題も。
わたしも言葉好きなのでおもしろく読めたけど、家に何冊にもおよぶ百科事典や分厚い辞書を置く時代でもないし、アクセスに課金する辞書はどんなに質が高くても無償のサイトに太刀打ちできない。編集者の仕事も末端から順にAIによって置き換えられ、言語学を学んだ新卒の編集者がスキルを磨いて出世する道筋も閉ざされている。経験豊かな専門家が何十年のスパンで編集する従来の辞書は消え去るのは止めるには、政府や大学が公的事業として信用できる辞書の編纂を担うしかなさそうだけど、政治的に揉めることしか想像できない。便利になった一方、いろいろ残念な気持ち。