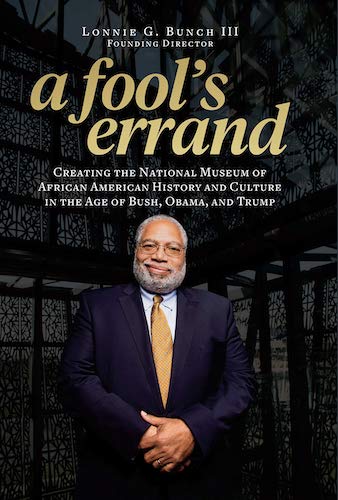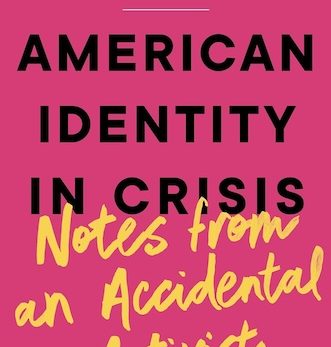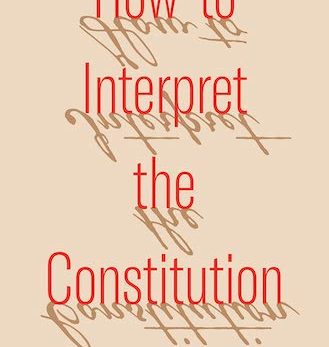Jennifer Heerwig & Brian J. McCabe著「Democracy Vouchers and the Promise of Fairer Elections in Seattle」
10年前の2015年にシアトル市が全国に先駆けて導入した「選挙資金クーポン券」制度についての研究書。全国でもシアトルにしかないこの珍しい制度がどうして、そしてどのようにして導入されたのか、そして制度の導入によりシアトル市の選挙がどう変わったのか、制度が適用された2017年、2019年、2021年の3回の選挙のデータを元に分析する。
政治とカネの結びつきが注目を集め多くの人が政治資金改革を求めるなか、選挙にかかる費用は高騰を続けている。市長や市議などを選ぶローカルな選挙でもこの傾向は進行しており、もともと裕福な一部の富豪やかれらから大口献金を集めることができるその代弁者以外にとって選挙に立候補するハードルは高い。2008年のバラック・オバマの選挙運動以来、ネットを通して広く支持を募り小口の寄付を集める手法が注目を集めているが、全体から見ると政治献金総額のごく一部でしかなく、またあまり注目を浴びない、あるいは党派的・イデオロギー的に大きな対立として意識されないローカルな選挙ではさらに大口献金者の役割が大きい。一般社会とくらべて政治家に裕福な家庭出身の白人男性の割合が多いのは議会の構成を見れば明白だが、かれらの選挙運動に政治献金を出す人たちは議会の構成よりもさらに裕福な白人男性が多い。このため裕福な白人男性たちは目に見えている以上に政治に強い影響力を持ち、民主主義を歪ませている。
こうした現状を是正するための方法は、政治学や市民運動のなかで議論されてきた。これまでアメリカで導入された制度には、署名を集めるなど一定の支持を示した候補に公的な選挙資金を支給する仕組みや、小口の寄付を集めた候補にその寄付と同額あるいは何倍かの公的資金を支給することで小口献金をブーストする仕組み(最近のニューヨーク市長選予備選でも大きな影響があった)などがある。ただし公的資金を受け取る条件としてその他の(大口)寄付を含めた選挙運動資金総額に制限がかかるので、大口献金者からより多くの寄付を集めることができる候補を相手にすると不利になってしまう。2000年の大統領選挙で大富豪のスティーヴ・フォーブスが自身の財産を投入して共和党予備選に出た際、フォーブスの資金に対抗するためには総額制限が足かせになるとジョージ・W・ブッシュが公的資金を拒絶したのにはじまり、現在では連邦政府レベルの選挙ではほぼ使われなくなっている。また、小口の寄付を公的資金によって何倍にもブーストする制度は選挙における小口献金者の影響を強化するが、それでもやはり寄付をする人はごく限られた一部の人たちだけで、本当に貧困に苦しんでいる人などは小口であれ選挙運動に寄付している余裕はない。
シアトルでも1978年以来、小口の寄付をブーストする制度が何度か導入されたがそのたびに抵抗にあい、廃止されたり州によって禁止されたりしてきた。2013年の住民投票で再導入を目指す提案が僅差で否決されると、ブースト制度以外のさまざまな制度について議論され、その結果多くの人の支持を集めて実現したのが選挙資金クーポン券制度だった。この制度では、選挙の年にはアトルに住んでいる有権者一人ひとりに25ドルのクーポン券を4枚支給され、一定数の署名を集めるなどの条件を満たした候補にこの4枚のクーポン券を寄付することができる。クーポン券はどの候補に何枚と指定してシアトル選挙委員会に送り返してもいいし、候補に直接渡してもいい(最近ではオンラインでもできるようになった)。クーポン券を受け取った候補はシアトル選挙委員会から額面と同額の選挙資金を受け取ることができる。つまり、シアトル市では全ての有権者が潜在的に100ドルの政治献金者であり、候補たちにとって無視できない相手となった。
この制度が実現して今年で5度目の選挙がいま行われているが、本書はその3回目までのデータを元にその影響を分析。クーポンを利用する人はまだ少数だが年々増えており、ローカルな選挙において(クーポンを含めた)小口献金を行う市民の割合はアメリカのどの都市よりも高い。寄付を行う層は市全体と比べるとまだ白人や中流層が多いが、その差も縮まりつつある。また立候補するハードルも下がり、同時期のほかの都市と比べて候補者が増え、なかでも女性や非白人の候補が大きく増加した。過去の選挙では一度選挙で選ばれた政治家はめったなことでは引退せず圧倒的に有利な現職という立場で再選に挑んできたが、クーポン券の導入によって現職以外の候補もそれなりの選挙運動を展開することができるようになり、現職の有利さが軽減された。コミュニティに根付いた草の根市民運動が有力候補を生み出し何人もの市議を輩出しているのは、そうした運動がイベントや普段からの繋がりを通してクーポン券の利用を呼びかけた結果でもある。2019年にはシアトルに本社を置き自社にかかる税金に反発したアマゾンが市議会の乗っ取りを企て、その年行われていた市議選7議席の選挙に多額の政治資金を投入したが、クーポン券制度のおかげもあり対立候補が出なかった1議席以外は全敗した。
クーポン券制度はこれまで政治から見放されてきた人たちにより平等な政治参加の機会を与え、候補たちがかれらの声に耳を傾け、現職が自分の地位にあぐらをかかないインセンティヴを生み出し、より社会全体を代弁できる多様な候補や政治家を生み出してきた。本書の報告は、わたしをふくめ地元の政治に関わる人たちがこれまで感じてきたことをデータを通して肯定しており、とても納得がいく内容。もともと10年間の期限付きで導入されたクーポン券制度は来月3日の予備選挙で今後も延長するかどうか住民投票にかけられていて、おそらく市民によって延長が決められるだろうということはあんまり心配していないのだけれど、それでも制度の将来はあまり安泰とも言えない。まず第一に、2010年の連邦最高裁判決Citizens United v. FECによって候補者以外の企業や団体が選挙結果に影響を与えようとして行う活動に対する制約が禁止されたため、候補自身の選挙運動と無関係に多額の政治資金が投入されローカルな民主主義が脅かされている。2019年にはアマゾンが推薦する候補を落選させることができたけれども、本書で扱われていない2023年の選挙では市議会がアマゾンなど地元ビジネスが推す候補に席巻された。
また、クーポン券制度やその他の公的な選挙資金制度によって自分たちの利権が脅かされる大富豪やかれらにおもねる現職議員らからの攻撃も続いている。かれらは「自分の税金を自分が支持していない候補に分配するのは許せない、言論の自由に対する侵害だ」として公的選挙資金制度や小口献金ブースト制度などを裁判に訴えてきており、これまでのところ連邦最高裁はこれらの制度を合憲だと判断だれたのだけれど、いまのアレな最高裁が過去の判例を踏襲するかどうかは不透明。そうでなくとも財政難により住居政策や交通政策の予算が削減されるなか、民主主義という漠然としたもののために税金を投入することの意義は伝わりづらい。現に、シアトル市以外でもクーポン券制度の導入を求める運動は各地で起きており、オークランド市では実際に条例が可決されたけれども、財政難によりいまのところ実施されていない。
ところでシアトル市でこの制度が導入される前の段階にラリー・レッシグせんせーの影響があったことを本書ではじめて知った。早い段階でインターネットと法や著作権とイノベーションの関係について発言したりクリエイティヴ・コモンズを設立して注目を集めた法学者ローレンス・レッシグは、2000年代末に突然「政治腐敗の問題に集中する」と言い出して2016年には大統領選挙で出たりとよく分からない行動をしていたのだけれど、実のところ全国を精力的に回って選挙制度改革について語っていたらしい。クーポン券制度はレッシグが考えたわけではないけれど、クリエイティヴ・コモンズ以来シアトルのテクノロジー業界ではレッシグのファンが多く、そこからレッシグが紹介したクーポン券制度の案が広まっていった様子。著作権の縛りを緩和して文化をリミックスする話をしていたレッシグせんせー、「これはただのフェアユースです、人間がほかの人の文章や作品にインスパイアされるのと同じです」として著作権を無視した学習データ収集と利用を正当化する生成AIブーム来てますがどうしてますか?と思っていたけど、ちゃんと政治腐敗の問題について良い影響を与えていたんだ!と再評価しました。