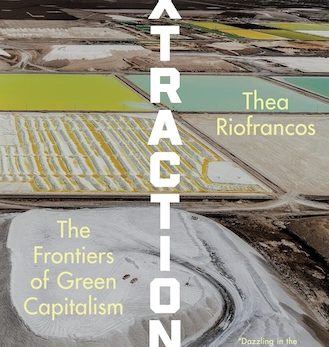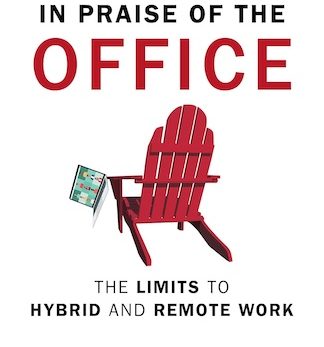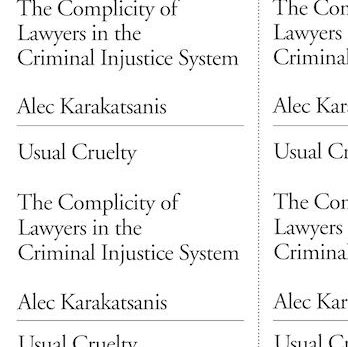Emile Suotonye DeWeaver著「Ghost in the Criminal Justice Machine: Reform, White Supremacy, and an Abolitionist Future」
若いころストリートギャングに加わり殺人罪で21年間をカリフォルニア州刑務所に収容されて過ごした黒人男性のライター・活動家が、白人至上主義と対決しないリベラルな司法改革や収容者たちに向けた「更生」プログラムを批判し監獄廃止を訴える本。刑事司法制度の抜本的な改革や監獄廃止主義を訴える運動のなかでも実際に長期にわたって刑務所に収容されていた人の声が中心に据えられることは少なく、とても貴重な告発と提言が含まれているすごい本。
著者は警察による嫌がらせや違法な取り締まりが頻発するオークランドの黒人コミュニティで育つ。父親は医師だったが、お金がないコミュニティの人たちを無償で診断するせいで一家は貧しく(とはいえそのおかげで刑務所内で「ああ、あの医者の息子か」とほかの収容者たちに良くしてもらえた)、学校や店に行くために道を歩いているだけで警察に止められ犯罪者扱いされる日々。警察は生意気な若い黒人男性を見かけると麻薬を仕込んででっち上げ逮捕したり、わざわざ敵対するギャングの縄張りに連れて行ってそこで解放して襲わせたりなどの日常的な危険に晒されるなか、身を守るためにはストリートギャングに加入して味方を作らざるをえなかったし、どうせ売人扱いされるならギャングスタ・ラップの登場人物みたいにドラッグの売人として成功するしかないと考えるように。その行き着いた先が、仲間を銃撃した(とされた)敵対するギャングのメンバーを殺害して67年の実刑判決だった。
一般に刑務所は、危険な犯罪者を社会から遠ざけると同時に、かれらを社会の一員として更生することを目的としている。当時レーガンからクリントンに続く犯罪取り締まり強化・刑罰重罰化の流れのなか前者の目的が強調されていたが、それでも収容者たちを同じ人間として尊重し更生を手助けしようとする非営利団体もあったし、刑務所の看守や責任者のなかにもそうした活動に協力的な人が少なくない。しかしそうした取り組みは多くの黒人たちが刑務所に収容されている根本的な理由から目を逸らし、収容者たち個人の人格や資質に問題があったからそれを矯正することで社会に適合させるべきだという、白人至上主義的で監獄主義的な論理に支えられている。実際、看守や刑務所運営者の側がそうした民間のプログラムを歓迎することがあるのは、それが刑務所内での治安を向上するのに役に立つからでしかない。
たとえばあるプログラムでは、収容者たちに演劇を教えることでかれらに人間性を取り戻させることを目的としていたが、かれらから人間性を奪い続けている社会的な暴力は問題視されない。あるときプログラム支援者たちの前で公演が行われ、収容者たちの必死の演技は多くの人たちに感動を与えたが、支援者たちは収容者たちの境遇を改善するための行動は一切取らずに、そのプログラムを実施した非営利団体への寄付を増やしただけ。また著者は刑務所内の新聞を編集する仕事を得たが、記事にしていいのは個々の収容者たちがどれだけ自分の行動を反省し更生したかという美談ばかりで、警察による人種差別的な取り締まりや刑務所による人権侵害など肝心な話は一切書くことができなかったし、そういうことを考えているとバレるだけで「反省が不十分」と判断されてしまう。
カリフォルニア州には刑期満了以前に条件付きで社会に出ることができる仮釈放の制度があるが、その審査は厳しく、ほとんどの仮釈放申請は却下される。その審査でもっとも重要視されるのは収容者による再犯の可能性であり、収容者はどれだけ自分が犯行を反省しているか、どれだけ自分が更生したか示す必要がある。これは反省を促す仕組みであるように見えて、実のところ監獄制度とそれを支える白人至上主義に疑問を持たない人を選別する仕組みでもある。制度が求める「反省」や「更生」は実際のところ本当の個人的な成長ではなく、制度に対する絶対的な服従を強要する道具だ。
著者自身、制度に順従でなかったために反省が足りないとされ仮釈放は認められなかったが、刑務所内新聞のジャーナリストとしての功績や刑務所内ではじめたアート・プロジェクト、そして刑務所外の活動家たちと連携して刑事司法制度改革運動を推進したことで注目を集め、カリフォルニア州知事ギャヴィン・ニューサムによって減刑が認められた。その経緯において著者は白人至上主義や監獄主義に妥協し、いかにも反省し更生しているようにふるまったが、それは本心とは異なる苦痛の決断だった。しかし著者は自分の過去の選択を反省していないわけではない。対立するギャングのメンバーだからと人を殺していいはずがないし、のちに自分が殺した相手は仲間を銃撃した人物とは別人だったと知って最悪の気分になった。また女々しい奴らだと見下していたアジア人男性に自分と対等な顔をされたことに怒って暴行したり、自分は絶対に女性に手を上げたりはしないと思っていたのに殴ってしまった過去など、監獄制度による評価が必要ない今だからこそ、何らかの利益のためではなく本心から自分の過ちを反省することができた。こうした反省を促すことができるのは、かれを認め尊重してくれる仲間やコミュニティに囲まれた環境であって、自由もコミュニティも取り上げ、反省しているふり、更生しているふりを強要する監獄制度ではない。
著者は監獄制度はコミュニティを安全にしないと指摘し、監獄廃止主義がどのようにして加害行為が起きる社会的要因を解消するのか、そしてどうしても起きてしまう加害行為の責任をどう取らせるのか説明する。かつてブラック・パンサー党が黒人コミュニティの問題を解消するために無償の食事や医療を提供していたオークランドで生まれ育った著者が、その歴史を一切知らされずに、ギャングスタ・ラップに自由な生き方を見出してしまったのはそもそも白人至上主義や監獄主義による黒人運動に対する弾圧が原因であるように、白人至上主義や監獄主義は黒人たちが自分たちの安全と自由のために自ら生み出した取り組みを叩き潰し、そのかわりに刑務所こそが人々の安全を守ると騙してくる。警察の不法行為によって人々の安全を脅かし、ギャング同士の対立を扇動し、警察に頼らなければ自分たちの命が危ないと思わせようとする。本書はそうした白人至上主義や監獄主義に善意から加担する非営利団体や人道主義的な改革論者たちを白人至上主義の協力者だと告発し(そして自分も収容されていた当時は不本意ながら協力者とならざるを得なかったと打ち明けつつ)、本当の解決策を提示している。