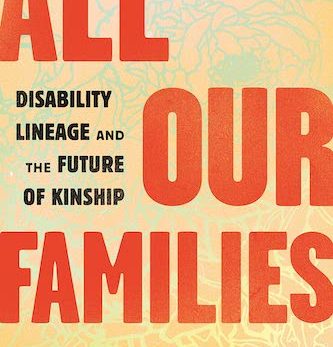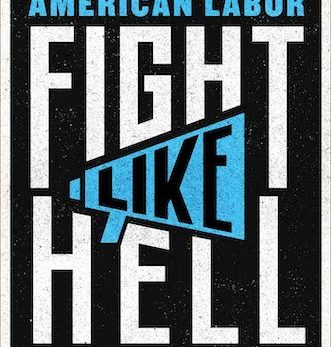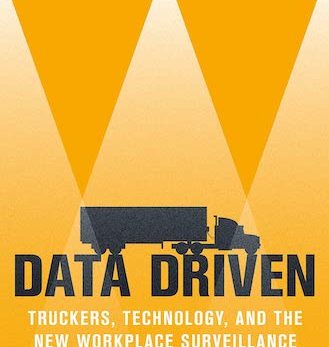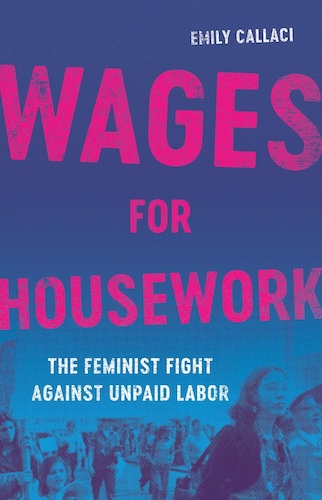
Emily Callaci著「Wages for Housework: The Feminist Fight Against Unpaid Labor」
「家事労働に賃金を」求める運動が1970年代のイタリア、イギリス、アメリカなどの女性運動のなかでどのように広がりそして衰退していったか、そしてコロナウイルス・パンデミックを契機に主に女性が行うケア労働への注目が高まる現在にどのような影響や示唆を与えているのか論じる本。著者はウィスコンシン大学の歴史学者。
本書ではセルマ・ジェイムズ、マリアロサ・ダラ・コスタやシルヴィア・フェデリーチら「家事労働に賃金を」運動のなかで大きな役割を果たした理論家や活動家たちを中心として、その運動の歴史が語られる。資本は(男性)労働者に賃金を払って一定時間雇用するが、その労働者を生み出し、育て、食事や掃除洗濯など日頃のメインテナンスを行い労働に送り出す(主に)女性たちによる再生産労働には賃金を払わずただ乗りしている、という気付きから、家事労働に対する正当な賃金を要求するだけでなく、その要求を通して資本主義が女性による無償労働を搾取しなければ成り立たないことを暴き立て、資本主義を自壊に追い込むことが彼女たちの狙いだった。とはいえ自分たちが日々行っている労働の価値を認めてもらいたい、自分の自由になるお金を得たい、という当たり前の気持ちが多くの女性たちを運動に引き付けたのも事実で、家事労働を行っている女性たちがお金を手にすること自体も重要だとされた。
「家事労働に賃金を」の運動が広まった1970年代から1980年代にかけては、ニューヨーク市が財政破綻しかけるなど不景気や財政赤字拡大からサッチャリズムやレーガノミクスがもてはやされ、世界各地で緊縮財政が進められた時代でもあった。一家の収入が減ると食費を浮かすために複数の市場や店を回って安い食材を見つけ時間をかけて調理する必要があるし、託児所や幼稚園が閉鎖されれば子育ての負担は重くなる。医療へのアクセスが削られても自宅での家族に対するケアはやめられないし、ゴミ収集の頻度が減らされると家庭内でのゴミ処理にかかる手間が増える。途上国では水の配給が止まると遠くの井戸や川から生活に必要な水を持ってくるだけで重労働になる。このようにして財政支出削減は政府の支出を減らすかわりに各家庭にその負担を押し付け、結果として女性が担う無償労働を格段に増やしていた。女性に対するそうした社会的要求は、実際に家庭で家事を行う女性だけでなく、独身女性やレズビアン、セックスワーカーらを含めた全ての女性に対して無償のケアを期待する要請として女性の地位を貶めている。
しかし「家事労働に賃金を」運動には女性の賃金労働への進出を進歩と考えるリベラルフェミニズムを中心に、フェミニズム内部からの批判もあった。家事労働に賃金が生じるとなると家庭内の性役割分担を固定化してしまうのではないか、賃金を受け取るかわりに家事労働を拒否することができなくなるのではないか、さらには子育てが社会化されると子どもは親ではなく国家のものにされてしまうのでは、といった懸念などが挙げられた。しかしフェデリーチが著書のタイトルを「Wages for Housework」ではなく「Wages Against Housework」と名付けたことに象徴的なように、彼女たちはむしろ女性の自然な役割とされていた家事、さらには資本主義における労働を拒否するための段階として賃金の要求を掲げていた。
「家事労働に賃金を」運動で特筆されることは、「家事労働に賃金を求める黒人女性の会」を設立したマーガレット・プレスコッドら黒人女性たちの運動や、自分の子どもを育てる権利を求めるレズビアンの運動、性労働の非犯罪化を求めるセックスワーカーの運動らを包摂し、強固なネットワークを築いていたことだ。事実、わたしが「家事労働に賃金を」運動についてはじめて知ったのは、性労働者運動のなかで「家事労働に賃金を」運動の一部でもあった「アメリカ売春者共同体」(US PROS)のメンバーたちと出会ったことがきっかけだった。当初は不勉強なせいでよく分からなかったけれど、あとになって彼女たちがすごい国際連帯運動の一員だったことに気づき、性労働者運動のあり方の一つとしてとても感銘を受けた。
その後、運動は衰退していくわけだけど、そのあたりは著者のインタビューに答えたくないという人も少なくなかったということから分かるとおり、まあありがちなグダグダな感じ。白人女性たちが「主婦は黒人奴隷と同じ」みたいなことを言って黒人女性たちから顰蹙を買う、みたいな理由のはっきりした衝突だけじゃなく、誰々が誰々の手柄を奪ったとか個人的な諍い、そして若い活動家たちが結婚・出産していったときに、料理や掃除はなんとか拒否できてもさすがに育児はボイコットできないのでやむなく折れていったりなど、いろいろ難しい。「家事労働に賃金を」運動の中心にいた人たちも別の運動や仕事にシフトしていき、いまでもこの運動をホームグラウンドにしている人は多くない。
それでもコロナウイルス・パンデミックによって(主に)女性が無償で行うケア労働の重圧が悪化すると、それへの救済策としてバイデン政権によって子育て支援が実施され子どものいる家庭の経済的困窮が劇的に改善された(けど恒久化できなかったのですぐに終了して、また貧困率が上昇した)など、フェデリーチが言っていたほど急進的ではなくても、家事労働を社会がどう支えるかという議論は今に続く。家事労働の搾取は女性や子どもの貧困と直結した問題であり、子育てや家事への金銭的支援は弱者への施しではなく労働者として当然受け取るべき権利であるという考え方は、現代でも重要。