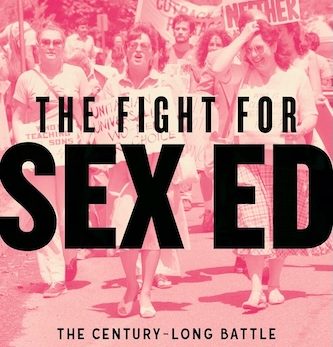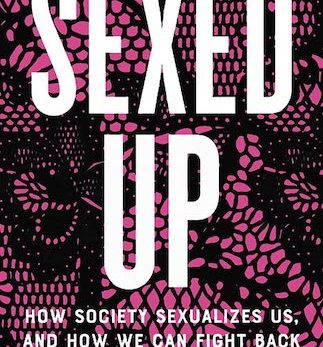Caroline Darian著「I’ll Never Call Him Dad Again: By the daughter of Gisèle Pelicot: Turning our family trauma of Chemical Submission into a collective fight」
2020年にフランス・アヴィニョンで発覚し世界中に衝撃を与えた長期に及ぶ性暴力事件で、実名を出し公開での裁判を選んだ被害者ジゼル・ペリコ氏と彼女の加害者であり夫のあいだで育てられた娘による手記。2024年末に裁判が行われ元夫に有罪判決が下ったが、本書は裁判前の2022年にフランスで出版されており、英語版は2025年になって出版された。
ペリコ氏は少なくとも2011年から2020年にわたって夫によって繰り返し薬を盛られ、意識がないところを夫や夫がネットで知り合った他の大勢の男性たち(警察によって72人の加害者が確認されており、そのうち50人が特定・起訴された)に性的暴行を受けていた。彼女はたびたび記憶障害やその他の体調不良に悩まされ、脳障害がいつ起こるかわからないのに運転するのは危険だということで運転免許を返上させられたが、夫が薬を盛っているとは誰も気づかず、身近な人が薬を盛っているなどとは考えもしない医者も家族もその原因に気づくことはなかった。事件が発覚したのは夫がスーパーで見知らぬ女性のスカートの中を盗撮しようとして逮捕されたことがきっかけで、警察がかれの携帯などを調べたところ意識のないペリコ氏が多数の異なる男性に暴行を受ける映像や動画が大量に発見された。また夫の携帯から出てきたメッセージの履歴からは、かれがそうした写真をネットに投稿し、参加者を募集したり、どの薬をどれだけミックスすれば被害者の意識を奪うことができるか指南した記録が見つかった。
お金の管理にだらしなくて、自分がバイトして貯めた貯金をこっそり盗むような父親だったけれども、それなりに両親の愛を受けて育った著者。父親が想像を絶するほどの邪悪な暴力を母親に対して長年行っていたことを知り、世界がひっくり返るような思いをしながら母を支えなければいけないと決心するが、警察が父の携帯をさらに調べたところ、眠っている著者自身のものと思われる写真が発見される。少しの物音で起きてしまう自分が布団を取られ下着をはだけさせられて起きないとは考えにくく、父は自分に対しても薬を飲ませ暴力をふるっていたのではないかと彼女は考え出す。のちに彼女の全裸の写真も見つかったが、既に見つかっていた母親の写真と同じポーズ、同じ構図が並べられ、体つきについて批評する父のコメントがついていた。父はそれらの写真について最初無関係だと言い、そのうち興味本位で撮るには撮ったが自分は若い女性には興味がないから性的な意味はなかったと言い逃れようとした。
著者が自分自身も父親の被害者だと認識したことで、程度の差こそあれ同じ立場であるはずの母親との関係にも亀裂が走る。自分が受けた被害については「自分に恥じることはない」と堂々と実名を公表した母だったが、自分の娘が被害を受けていたことは彼女にとっては受け入れがたく、かれがそんなことをするはずがない、という希望にすがろうとする母。また父は家族や関係者への連絡を禁じられているにもかかわらず刑務所内の別の囚人を通して一家の友人に連絡を取り、母の同情を求めつつ、娘である著者がいかに冷酷か印象付けようとするメッセージを送り、かれ自身が生み出した傷をさらにえぐり出し家族を分断させようとする。お互い支え合おうと母と話し合うも、父が母を説得して刑務所からの脱走に協力させ、二人で娘を責めるという悪夢に悩まされる著者。精神科に相談すると、薬で眠らせられることが怖いというのに睡眠薬を処方される。夫と離婚し事件の責任を追求する姿勢を見せながらも、なんとかして「夫はもともとそういう人ではなかった」と考えようとし、自分に何かできたのではないかと言い出す母。また、著者の幼い息子に優しかったおじいちゃんがおばあちゃんに対して許されないようなひどいことをしたせいで会えなくなることを説明しようとして苦労したり、当初はそれを信じようとしなかった息子が少しあとになって自分の記憶からおじいちゃんを消し去りたいと言い出すあたり、性暴力が最もひどい被害を受けたペリコさんだけでなく家族や親戚、友人たち全員を傷つけていることがこれでもかと示される。
本書の訴えで最も重要なことは、わたしたちの社会が性暴力事件に対して加害者を逮捕して処罰することばかりに熱心で、その処罰のために証言者として呼ばれる被害者やその関係者たちへのケアをほとんど行えていない事実だ。とくにこの事件では、被害者がたびたび検察や裁判所に呼び出されて自分が知らないうちに暴行されている映像や画像を一つ一つ確認して「これは自分です、このような行為に同意した記憶はありません」と証言しなければいけないし、加害者が残した多数のメッセージについて意見を求められたりするが、取り調べや聞き取りが終わったら「ご協力ありがとうございました」の一言で放り出されるだけ。どう考えてもおかしい。著者はたまたま親戚に医師がいてアドバイスを得ることができたし、カウンセリングを受けるだけの資産もあったが、それでも母親は(全国のサバイバーたちからの共感と支持を得ながらも)あまりの衝撃を受け止めきれずに娘の被害を否定したり夫の行為を過小評価しようとせざるを得なかったし、著者も母と自分と息子を守るために苦しみ、そして母が父を赦してしまうのではないか、追求をやめてしまうのではないかと恐れる日々を過ごした。身近に相談にのってくれるプロフェッショナルがおらず、カウンセリングを受けるだけの余裕がないサバイバーたちは、さらに孤独に被害の後遺症と向き合うことになる。
また著者は、薬物を使った性暴力が多くの人が思っているより身近なものであり、バーで飲みものに薬を入れられないように気をつけているだけでは不十分であることを主張している。使われている薬には一般に処方されているものやパーティドラッグとして容易に入手できるものが多数あり、その(決して安全とは言えないが意識を摘み取るために必要な)分量についてもネットで調べることができる。著者の父親の犯行が長年発覚しなかったのは医師をふくめ誰もそうした性暴力の存在を意識していなかったからで、誰か一人でもそれを疑い母に検査を受けさせていればもっと早く事実が明らかになっていたはず。性暴力の加害者はバーや路地裏で出会う赤の他人より家族や友人・知人、教会やコミュニティの一員であることのほうが圧倒的に多いのだから、安全なはずの家庭内であれ不審な事実が積み重なった際には薬物の使用を疑うくらいにはこの問題の存在は意識されていい。
昨年末の裁判の際にはペリコさんへの支持や感謝の声が広まり、フランス中から女性たちが裁判所の前に押し寄せた。メディアの報道に登場する彼女は今年72歳でありながらいつも力強く堂々としていて、まさにサバイバーの英雄として憧れを感じていたけれども、娘の立場から書かれた本書にはそうした彼女の弱い部分、どうしようもなく感情に突き動かされてしまう部分、すべてを投げ捨てて逃げ出したくなる部分、完璧なヒーローではない部分が描かれており、より親しみを感じた。彼女に一方的に憧れるのはやめて、彼女と一緒に歩んでいきたいと思った。