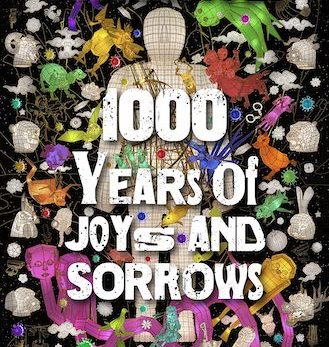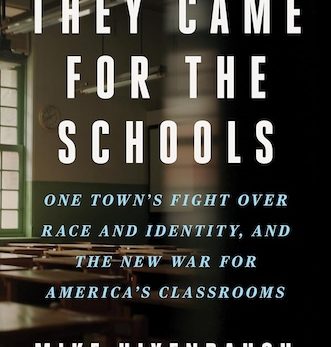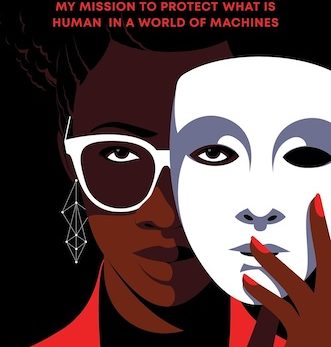Abi Maxwell著「One Day I’ll Grow Up and Be a Beautiful Woman: A Mother’s Story」
トランスジェンダーの子どもを持つ母親が学校や地域社会との戦いの日々について綴った本。
著者はニューハンプシャー州の田舎の静かな街で豊かな自然と親密なコミュニティに囲まれて育ち、結婚・出産したあとは自分の子どもも同じような環境で育つことができることに幸せを感じていた。しかし子どもが6歳のとき、男の子だと思っていた子どもが自分は女の子だからピンクの靴をはきたい、ドレスを着たいと言い出す。もともと自閉症スペクトラムの傾向があり学校でもさまざまな困難を経験していた子どもだったけれども、本人の強い願いに根負けしてピンクの靴を買い与えると、これまで見たことのないくらいの満面の笑顔を見せ楽しそうにしていた。しかし学校では男の子なのにピンクはおかしいといじめられるし、親も「男の子だってピンクを着ていい」と自分に言い聞かせるようにしていて、本人は女の子として認められないことに不満を募らせる。ハロウィーンのときに魔女のコスチュームとしてドレスを着ることを許されると最初は幸せそうにしていたけれど、その日の終わりにはどうして自分はハロウィーンにしかドレスを着られないんだ、と泣き出す。
著者にはゲイの弟がいて、かれがカミングアウトしたときに軽くあしらってしまい、のちにかれが自殺未遂を起こしたこともあり、著者はかれを姉として親身になって支えようとしなかったことを後悔していた。単に女の子のものとされている服が好きというのではなく、女の子だと認めてほしいと繰り返し訴えるわが子に弟と同じ孤独を経験させてはいけないと著者はカウンセラーの話を聞いたりLGBTの人たちの家族会に参加するなどして、トランスジェンダーの子どもたちについて学ぶ。子どもがトランスジェンダーだと受け入れたあとも、彼女が望む名前を親戚の前では使わず隠すようにしたり、いじめの対象となることを恐れて学校に着ていく服を制限しようとしたりもしたけれど、次第にどうすることが彼女を支えることになるのか考えを深めていく。
学校にも話を通してその子は女の子として通うようになったけれど、残ったのはトイレの問題だった。学校側は彼女に保健室のトイレを使うよう指示したが、できるだけトイレを使わないようにしていたところ、あるとき間に合わずにおもらししてしまう。学校は彼女を男子トイレに連れていき、汚れたタイツとスカートを脱がせて男子の服を着せたが、そのことで結局学校は彼女を女の子としては認めていないことがはっきりしてしまう。ちょうどニューハンプシャー州でLGBTの子どもたちを守るための法律が成立したことを知った著者は、法律に従って彼女がほかの女の子たちと同じく女子トイレを使うことを認めるよう求める。
法的にはこの要求を拒否できないと悟った学校側は、しかし全校生徒の親にメールを出し、「ある親が身体的に男子の生徒に女子トイレを使わせるよう要求しており、新しい法律によってこの要求を拒否できない」と通知する。これを聞いた地域の親たちは学校区の理事会に押しかけ、「女の子たちを守れ」という運動が巻き起こる。子どもは精神異常を抱えており、著者は子どもをトランスジェンダーに仕立て上げるグルーマーだと批判されたが、そうしたことを言っているのは著者が昔からよく知るコミュニティの人たちだった。著者の子どもをめぐる論争は子どもたちにも影響を与え、それまで以上に彼女は学校中の子どもたちからいじめにあう。学校区は教師に対してトランスジェンダーという言葉や概念を使うことを禁止し、いじめから彼女を守ろうとすると職を失う危険があるという意識が教師たちのあいだに広がる。
結局著者ら一家はこの街から追い出されるようにして脱出したが、LGBTの生徒に理解がある地域・学校を探して引っ越した先では、著者の子どもははじめから女の子として登校する。ある程度溶け込んだあと、娘が「やっぱり自分はトランスジェンダーだということを説明したい」と言い出したので学校とその方法について協議。その結果、ダイバーシティについての授業のなかで、自分がユニークだと思うところについて一人ひとり発言してください、という場面を作り、そのなかで彼女は「わたしはトランスジェンダーです」とカミングアウトする。「それってどういう意味?」と疑問に思う周囲に教師がすぐに説明を行うと、それを聞いた他の子どもたちは一斉に「へえ、クールじゃん」と受け入れた。子どもたちの考え方の柔軟さに感心するとともに、学校がすべての子どもを守る意思を持ちきちんと準備すれは、これだけ違った対応ができるんだ、と希望を感じた。
本書を通して強く感じたのは、トランスジェンダーの子どもたちを支えようとしている親たちも、必ずしもはじめからそうだったわけでもない、という事実。ましてやもちろん陰謀論者やヘイターたちが言うように「わが子をトランスジェンダーに仕立て上げようとする変態親」などでもない。最初のうちは「自分は女の子だ」という本人の訴えを無視して無理やり「ピンクが好きな男の子」として扱おうとしたし、せっかくピンクの靴を買ってあげても「いじめの対象にならないように」という考えのもと、家の中だけで履かせたりしていた。また親戚やコミュニティを失うことを恐れて子どもがトランスジェンダーであることを隠そうともしていた。しかし著者は、このようにして彼女がトランスジェンダーであることを隠すことは「あなたは世間に見せられないような恥ずべき存在だ」と教えているようなものであり、ゲイであることでその親戚やコミュニティから孤立して自殺未遂を起こした弟と同じような孤独を自分の子どもに経験させてはいけない、と気づき、自分自身が社会的ないじめを受けることになっても子どもに寄り添うことを選んだ。ちなみに父親も基本的な姿勢は同じなんだけど、娘に対する攻撃によってメンタルをやられて打たれ弱さを見せてしまっていた。
「トランスジェンダーの子どもを持つ母親の本」というのは結構以前からあるジャンルで、あんまりおもしろくないものが多い印象があるんだけど、「どうしてもっと早く女の子だと認めてくれなかったの?」という娘の問いに向き合い、自分が何をどう守ろうとしていたのか、それによって何を失いかけていたのか自問する著者の姿勢にとても感銘を受ける。このジャンルの中ではこれまで読んだなかで一番いいかも。