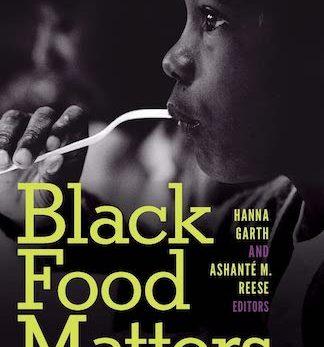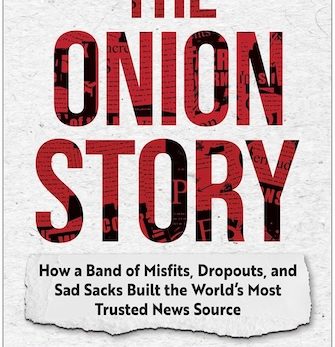Sam Bloch著「Shade: The Promise of a Forgotten Natural Resource」
気候変動により多くの土地で猛暑が激しくなるなか、人々の命を守るために重要性を増す「日陰」という公共財の供給増とより公正な分配を求める本。これまで都市計画の政策論議の中で断片的に聞いて気になっていたいくつもの話がきれいにまとめられていて、めちゃくちゃ勉強になった。
本書は過度な直射日光から生命を守るための生物界の進化の歴史から、屋外で働く労働者たちの命を守るために暑い時期のある地域で発達した建築様式などの話にはじまり、それが冷房の誕生と普及によってどう変わってきたのか論じていく。冷房がなかった時代、暑すぎる地域にはそもそも人口はそれほど集まらなかったし、そういった地域では直射日光から人々を守り風通しを良くすることで体感温度を下げるような建築や都市設計が自然と広まったが、冷房の普及により建物は冷やした空気を逃さないよう密閉され、熱くなった空気を建物の外に排出するように。屋内で働くホワイトカラー労働者たちが快適に仕事ができるようになるとともに、屋外で働く労働者の健康や安全は軽視されるようになる。
さらに、屋外に日陰があると労働者たちが仕事をせずに休憩ばかり取るとか、ろくでもない若者がたむろして良からぬことをやるといった偏見により日陰が積極的に排除されるようになると、冷房の普及をその要因の一つとする都市の分断化はさらに加速。同じ屋外でも白人富裕層が住む地域では木々がたくさんある公園や歩道が整備され人々の憩いの場となるいっぽう、そうでない地域では防犯の名目のもと日陰が減らされていく。そのうえ冷房を動かすために必要な電力を生み出すための化石燃料の利用が温暖化を悪化させる原因の一つとなり、かつては穏やかな気候だった地域でも冷房がなければ人々の命が危険に晒されるようになってきている。
本書ではポートランドのわたしが以前住んでいた地域の話がたびたび出てきているが、その地域は2021年の熱波によりポートランド市内でもっとも気温が高くなり、またもっとも多くの健康被害が生まれた地域でもある。当時のポートランド市内各地の気温を地図にすると、それはかつて黒人や移民、貧困層が住む地域として政策的に見放されてきた地域とほぼ完全に一致する。それは植えられた木々の数や密度、公園や道路の設計、人々が集まる場が奨励されたか排除されたかといった歴史的な扱いの違いに直接関係している。つい最近も小さな犬専用のドッグパークができたと聞いてその地域の公園にキティちゃん(うちのチワワ)と一緒に出かけたのだけれど、だだっぴろい草原に日陰となる場所が一切ないのでほかに利用者もおらず、短時間ですぐ帰らざるをえなかった。キティちゃんの遊び相手が欲しかったのに。
人々の健康に関わるほど暑くなる地域や時期では誰もが冷房にアクセスできるようにしなくてはいけないけれど、冷房を使わずに人々の体感温度を下げるような都市設計や建設規制も進めていかなくちゃいけない。わたしがこれまでシアトルで見てきた議論では、そうした政策を実施すると建設コストが上がるから住居が建てられなくなる、深刻な住居不足を放置していていいのか、と言われるのだけれど、日陰や体感温度を下げるような建築のデザインを公共財として奨励していく必要があるし、それらが生み出す正の外部性による社会的利益を何らかの形で関係者に還元する(あるいは日陰を無くしたり体感温度を上げる設計の負の外部性による社会的損失を責任者に負担させる)のも大事。
本書は最後に気候変動と日陰の重要性に関連する話題として、大気中になんらかの粒子をばらまくことで太陽光の影響を軽減するジオエンジニアリングについて触れられていて、いやそれは別の話じゃ?と思ったけれども、Thomas Ramge著「Dimming the Sun: Why We Need Geoengineering to Keep the World from Falling Apart」でも書かれていたような民主的な決定や意図せざる悪影響に対する補償システムの不在を指摘するなど一応納得できる内容。でもやっぱり全然違う話のような気がするけどどうなの。
まあとにかく、シアトルで住宅不足やホームレス増加の問題に関する論争のなかで、住宅供給増を主張する人たちと木を守ろうとする人たちが対立させられる構図が最近目立っていたので、とても参考になる内容だった。全力で周囲におすすめしていく。