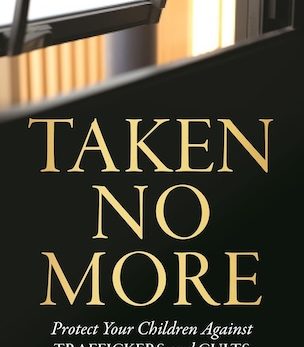Victoria Smith著「(Un)kind: How ‘Be Kind’ Entrenches Sexism」
女性に対して「優しさ」を求める社会的圧力はフェミニズムの成功により軽減されたと思いきや、フェミニズムや左派運動内部に取り込まれ、女性の権利を脅かしている、と論じる本。
本書は女性に理想の母親であるよう求める風潮にも少しだけ触れているけれど、著者が批判の対象とするのはトランスジェンダーの権利、そして性産業やポルノおよび代理出産制度。女性はトランスジェンダー女性やその他さまざまなマイノリティたちに「優しく」しろと包摂を押し付けられ、女性の身体的自己決定権を根拠に妊娠中絶の権利を訴えるなら性労働する権利や代理出産する権利もそこに含めろと言い寄られている、と著者。その結果、買春する男性やトランスジェンダーだけに優しく、女性に厳しい社会的状況が、フェミニストや左派によって作られていると訴える。
人種や宗教などに基づくほかの運動はそれぞれ自分たちの権利だけを訴えているのに、どうしてフェミニズムに限って全てのマイノリティへの配慮を求められ、女性の権利だけを訴えてはいけないのか、と著者は言う。しかしフェミニストたちが(フェミニズムだけでなく、あらゆる運動や社会情勢に対して)求めているのはマイノリティへの「配慮」や「優しさ」ではなく、どのような社会に住みたいかというヴィジョンであるはずで、著者の抱くヴィジョンが異なるというならまだしも、それを「配慮」や「優しさ」と言い換えて家父長制的な性役割の強要の継続とするのはおかしい。トランス女性を「女性」に含めないというのが著者自身の判断かもしれないが、当然含んでいると考える人は別に「配慮」や「優しさ」で含めているわけではないもの。
また、トランス女性は「女性」をこのように定義している、としてKai Cheng Thom著「Females」という前衛的で一見支離滅裂な書籍をそうとは明かさずに引用してくるのは、Janice Raymondによる古典的な反トランス本「The Transsexual Empire: The Making of the She-Male」(1979)がトランス陰謀論のパロディとして書かれたサタイアをまるで本物のトランスによる陰謀の証拠であるかのように引用した学術的不正を思い出させる。同様に、性労働の合法化や非犯罪化を訴えるフェミニストや代理出産の禁止に反対するフェミニストの主張やその論理を一切取り上げずに「男性に対する優しさ」「マイノリティへの配慮」だと決めつけるのも不誠実。
いちおう、トランス女性や性労働者を支持するフェミニストたちが見落としがちな重要な指摘もいくつかある。たとえば妊娠中絶をめぐってフェミニストが訴える「わたしの身体はわたしのもの」という主張は妊娠という緊急的でジェンダー的に不均衡な状況における権利についての主張であって、文字通りに解釈してどのような状況であっても女性が性や生殖能力を売ることに一切疑問を抱いてはいけないという意味ではない、など。「サバイバーを信じよう」や「やられたほうがやられたと思ったらセクハラです」なども、サバイバーの声を踏みにじろうとしたりセクハラ被害者を泣き寝入りに追い込もうとする社会に対抗するための言葉であって、女性は常に正しいという意味ではないのと同じ。(てゆーかそれを言うなら、「トランス女性は女性です」とか「性自認を尊重しましょう」も同じなんだけど、ややこしくなりそうだからこれ以上言わない。)
また、トランス女性を女性に含めることはそれ以外の女性からなにも奪わない、という主張に対して、たしかにトランス女性を女性と受け入れたとしてもそれ以外の女性が女性性を失うわけではないとしたうえで、しかし「女性であること」の意味が変質する、と著者は反論する。同性婚をめぐる議論において、「同性婚が実現してもそれ以外のカップルにはなんの影響もない」と言われたけれども、厳密にはそれは間違いで、結婚とはなにか、家族とはなにかという意味が変質した。フェミニストは同性婚が結婚や家族の意味にもたらすラディカルな変革の可能性を支持していたはずで、誰かの権利を認めることはほかの誰かの権利には影響しないというのは成り立たないと主張する。実際、一部のトランスジェンダー論者やフェミニストたちは、トランスジェンダーの人たちの権利が実現することによりジェンダー制度が変質する可能性を受け入れたうえで、それを支持している。
わたしも一応ラディカル・フェミニズムを経ているので、著者のこうした指摘にはとてもよく分かる部分もあるのだけれど、著者が批判する相手の論理をあまりに無視している、場合によってはおかしな引用により読者に誤解を広めようとしていることはどうしても気になる。しかしそれは逆に、仮に相手の論理を正面から取り上げた場合「だってだってトランス女性は女性じゃないもん、性産業なんて認めたくないもん」より先に主張が展開できない可能性に感づいているのかもしれない。