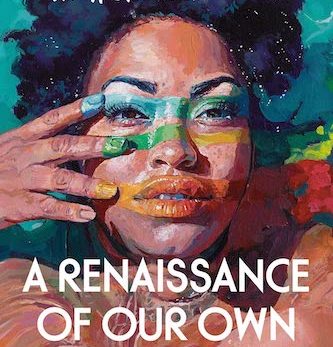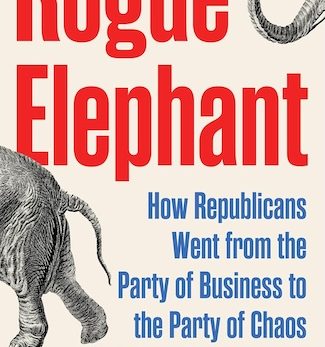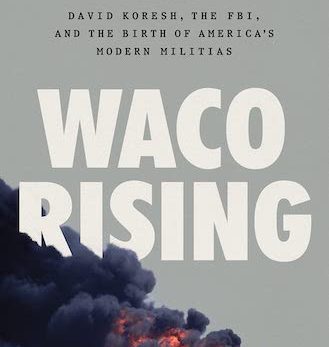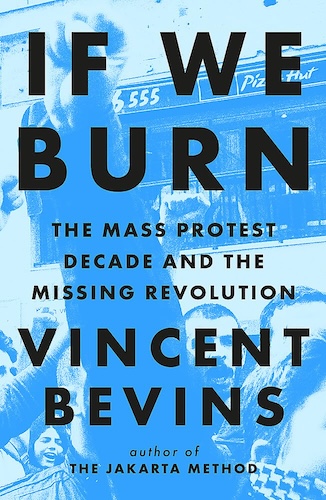
Vincent Bevins著「If We Burn: The Mass Protest Decade and the Missing Revolution」
2010年代を市民による大規模な抗議活動が歴史上もっとも活発だった10年と位置づけたうえで、それらの運動が大きく盛り上がり一部では時の政権を打倒しながら、新たな政治体制の構築には至らなかった事実に、それらの運動に参加した人たちの声をもとに向き合う本。著者はロサンゼルス・タイムズやワシントン・ポストの記者としてブラジルやインドネシアに長期間滞在したジャーナリスト。ブラジルの政治の話がとくに詳しく書かれている。
本書がケーススタディとして取り上げるのは、チュニジア、エジプト、バーレーン、イエメン、トルコ、ブラジル、ウクライナ、香港、韓国、チリといった西欧や北米以外の国で起きた10の大規模な抗議運動。チュニジアやエジプトで独裁者を倒し「アラブの春」と呼ばれた運動や、ヤヌコヴィッチ大統領がロシアへの逃亡に追い込んだウクライナのユーロマイダン革命、パク大統領が弾劾追訴されるきっかけとなった韓国の退陣要求デモなど、なかには成功したように見える運動もあったが、その多くの国ではそうした盛り上がりのあと、軍部や宗教右派、外国勢力、権威主義的なナショナリストらが権力を奪還し、元より悪い状況に陥っている。エジプトはムスリム同胞団が選挙で勝ったあと軍事クーデターが起き、ウクライナはロシアによる国土の切り取りと侵略を受け、ブラジルやトルコでは右派政権が権威主義的な傾向を強め、香港は中国政府により民主主義を否定され、バーレーンやイエメンはサウジアラビアの支配を強化された。
本書が取り上げた抗議運動の多くは、20世紀後半以降先進国のアナキズムや新左翼の運動が称揚してきた「フラットな運動」を体現していた。すなわち、特定の指導者や組織のもとに団結するのではなく、さまざまな考えを持った個人が共通の目的のために集まりともに行動し、また離散していくモデルの運動だ。とくに「アラブの春」はツイッターやフェイスブックなどを通して繋がるソーシャルメディア的な運動として注目を集め、世界中のさまざまな運動に影響を与えていった。ソーシャルメディアがフェイクニュースの拡散を通してミャンマーでの少数民族に対するジェノサイドやイギリスのブレグジット、アメリカのトランプ当選を後押ししたと指摘されるまでの数年間、ソーシャルメディアは自由と民主主義を世界に拡張すると多くの人が信じた。香港の2014年雨傘革命やその後の民主化デモでは特定の形を取らない流動的な運動のあり方が地元の英雄ブルース・リーの言葉を引用して「水のようになれ」と表現された。
特定の指導者や組織によらない運動はしかし、いくつかの弱点を露呈した。運動の目的や思想を説明する主体が存在しないことは、その解釈を他人に任せることになり、多くの場合その役割は欧米型民主主義への移行こそが正しい道筋だと考える欧米のメディアに担われてしまう。また、そうした運動によって権力者が打倒されたとしても、特定の指導者や組織を持たない運動はそこに生じた権力の空白を埋めることはできず、かわりにエジプトのムスリム同胞団のように組織的に動ける既存の政治集団や、近くの大国など外国勢力によって主導権を奪われることも多い。2010年代の市民運動は各国で一時的な盛り上がりを見せながら、それぞれがそうした敗北していった。
本書で取り上げられた運動の共通点の一つは、それらが警察による抗議活動への弾圧など公権力の暴力が画像や映像でソーシャルメディアで拡散され、それが運動の爆発的な拡大に繋がった点だ。これはアメリカからはじまったブラック・ライヴズ・マター運動の広がった経緯とも共通している。また香港の運動が「ハンガー・ゲームズ」をはじめとするハリウッド映画や「新世紀エヴァンゲリオン」のような日本のアニメをオマージュした映像を拡散したことに象徴的なように、ネットの「バズり」を通して実社会での動員が行われた。しかしそれらの運動に参加した多くの人たちが今痛感しているのは、ネットでのバズりは実際の政治にはほとんど影響を与えない、という冷酷な事実だ。一種の趣味として政治活動に没頭し、それが終わったら日常生活に戻ればいい欧米の若者と違い、多くの国では運動に参加した若者たちは政府によって殺されたり逮捕されたり国外逃亡を強いられたりしている。
運動が成功した時はその機会をつかみ取り、また一時的な盛り上がりを失っても活動を継続して次のチャンスを待つことができるような組織を作らなければいけない、というのは2020年の盛り上がりを経たブラック・ライヴズ・マター運動のなかでも言われていることであり、2010年代のさまざまな運動を起こしてきた世界中の人たちが同じ認識に至っているというのはよく分かる。著者によると、もちろんいまでも「フラットな運動」を支持している人もいるけれど、それでもインタビューを受けた全ての人が「少なくとも以前よりは」組織の重要性を意識しているという。とても貴重な証言が書かれている本。