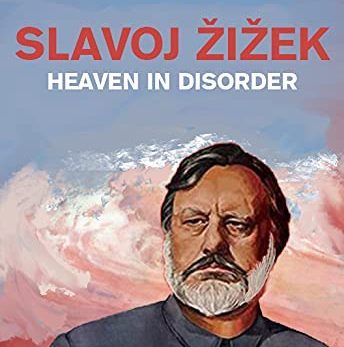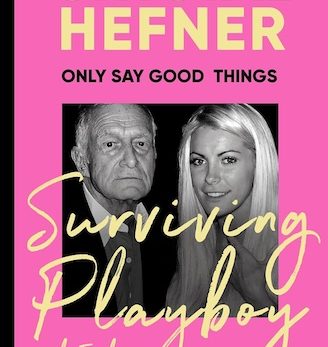Tracy Rosenthal & Leonardo Vilchis著「Abolish Rent: How Tenants Can End the Housing Crisis」
住宅不足は解決されるべき社会問題ではなく戦い勝利するべき階級闘争である、として借家人による運動への参加を呼びかける本。著者らはロサンゼルス借家人組合の共同創設者。
「家賃の廃止」という一見過激に見えるタイトルだけれど、言っていることの一つ一つはまっとう。住居を持つ権利が基本的人権の一つであるならお金のあるなしでその権利が守られないのはおかしいし、家賃の支払いに追われていなければどれだけの人たちが毎月末に不安を感じずに生活できるだろうか。労働者が安い賃金や劣悪な職場環境に不満を抱いていても家賃を払えなくなると困るので退職できないし、労働組合がストライキを起こしても一月も収入がなくなると住居を失ってしまう人が多いため、家賃の存在は労働者の搾取が定着する理由の一つになっている。
そもそも住居の価値はその土地や建物だけでなく、そこに電力や上下水道が通っていて、道路があり、近くに学校や公園や図書館があり、消防・救急・警察などの公的サービスが存在することによって成り立っている。いくら家賃が安くても、それらが全くない土地や家に住みたいという人はほとんどいない。そして住居の価値の大部分を構成するそうした社会的インフラは、政府や公共の投資によって生み出され運営されているものだが、経営者が労働者から余剰価値を搾取するのと同じく、家主たちは家賃を通してかれら自身が投資した額を回収するだけでなく、公共の投資によって生まれた余剰価値の多くを自らの利益として吸収する。エンゲルスが論じたとおり、住居不足を解決するには支配層による労働者の搾取と抑圧を終わらせる必要があると著者たち。こうしたマルクス主義的な分析だけでなく、本書では著者たちが関わってきた実際のさまざまな闘争がどのように戦われたのかという報告が多く紹介されている。
住居不足の問題を解消するために政府はデベロッパーや一軒家の家を建てようとする人たちにさまざまな優遇税制を設けたり資金援助をしつつ、アパートの一部を一定期間のあいだ低所得者向けに割り当てより安い家賃で貸し出すように義務付けたり、市場で決まった家賃が払えない人が入居できるように本来の家賃と低所得者が払える額の差額を借家人にかわって家主に直接払うプログラムなどを実施している。しかしどちらも現実の住居不足を解消するにはスケールがまるで足りておらず支援を必要とする人のごく一部しか救済されない。低所得者向けに割り当てられていたり自治体の条例により家賃の上昇率に制限がかけられているアパートも、住民が「自主的に」退居したら以後は制限が取り払われるので、ジェントリフィケーションなどによって周囲の家賃が上がってきたら、住民を騙したり必要な修理修繕を行わない、住民を警察や移民局に通報するなどの嫌がらせによって退居させようとするアパート運営業者も多い。
労働者たちにとってかれらが政府や政治家に頼らず経営者に要求を飲ませるために取れる最終手段がストライキであるのと同じく、ほとんどが自宅を所有しており何割かは家賃収入のある家主でもある政治家たちに頼らずに借家人が戦うための武器は、集団的な家賃不払い運動だ。百軒以上あるような大きな集合住宅であれば、住民たちが一緒になって家賃を不払いにすればアパート運営業者のキャッシュフローに大きなダメージを与えることができる。しかし多くの人たちは家賃は払うものだという道徳を深く内面化しているし、不払いに参加して立ち退きさせられるのは怖い。そうした心理的な抵抗や恐怖を乗り越え多くの人たちが一斉に不払い運動に参加するには、運営業者による悪質な嫌がらせや急激な家賃上昇、メインテナンスの放棄など重大な問題に対し住民たちが連帯することが唯一の解決策だという認識と、実際に不払いしたらどうなるのか、運営業者が取る手段にはどんなものがあるのか、立ち退き請求されたとしてどう対抗できるのか(どうプロセスを遅らせ損失をふくらませるのか)といった正しい知識が必要。それは実際にそこに住んでいる住民たちが借家人組合からの支援を得ることで可能となる。
住民たちの利害もそれぞれバラバラ。なんらかの解決金を出してもらえばよそに引っ越してうまくやっていける人もいれば、その地域を離れたら生活が成り立たなくなる人もいるし、なんなら長期的に見れば割に合わなくても眼の前にお金を積まれたら手を出さざるをえない人もいる。運営業者側も一部の人たちにだけお金を払うことで自主的に退居してもらい、不払いに参加している人数を減らし連帯を崩そうとする。立ち退き請求されたらすぐに警察が来て逮捕されるとか、移民局が来て家族を引き離されると脅されることも少なくない。運動を成功させるには多くの住民たちがただ合理的に納得して家賃を不払いにするだけでは十分ではなく、それ以外の場面でも困っていたら助け合う仕組みを作ったり、地域の祭りを行うなどして連帯感を深める必要がある。そうした運動が実際に成功して家主側に条件を飲ませたり、住民の共同組合が所有権を買い取ったケースもある。
本書はさらに、住居のないホームレスの人たちに周囲の住民たちがどう連帯するかも、その実例とともに書かれている。各地で「公共の場で理由なく座ったり寝転がったりしている」ことを犯罪とする条例が成立するなど、ホームレスの人たちを犯罪者として投獄しては釈放してまた元の場所に戻すといった残虐性の充足以外になんの理由があるのか分からないサイクルが繰り返されているが、それに対するオルタナティヴとして提示されるシェルターやミニハウスなどは一人あたりの空間が刑務所と変わらないものだったりするなど人々の自由には繋がらない。家を借りられない状態にあるホームレスの人たちと、現時点では家を借りていたとしても家賃が払えなくなることを常に恐れて生活しなければいけない多くの借家人たちが連帯することが必要。公共の投資によって生み出された余剰価値を私物化している大手の家主や不動産運営業者をその地位から引きずり下ろし、協同組合やソーシャルハウジングを拡大させることにより住居を投資対象ではなく人が住むためのものに取り戻すために著者たちが呼びかけるのは、政治家への働きかけではなく、借家人たちによる連帯と直接行動だ。